
目次
COREZO コレゾ「 鉛は金に変わらない、文政10(1827)年創業以来、原料と製法にこだわり抜き、ホンモノの味を追求し、GEN-B、食育、千枚田の保存活動他を通じて、日本の食文化を伝え続ける、ちくわ兄弟(味見担当) 」賞
佐藤 元英(さとう もとひで)さん
プロフィール
ヤマサちくわ株式会社 代表取締役
動画 COREZOコレゾチャンネル
佐藤 元英 さん・善彦さん/ヤマサちくわ(その1)「さかな屋さんが始めたちくわ製造」
佐藤 元英 さん・善彦さん/ヤマサちくわ(その2)「おいしいものしかつくらない」
佐藤 元英 さん・善彦さん/ヤマサちくわ(その3)「鉛は金に変わらない、原料へのこだわり」
佐藤 元英 さん・善彦さん/ヤマサちくわ(その4)「ヤマサちくわのおいしさをより多くの人に」
佐藤 元英 さん・善彦さん/ヤマサちくわ(その5)「ヤマサちくわ工場見学」
受賞者のご紹介
文政10年(1827年)創業
ヤマサちくわ株式会社は、文政10年(1827年)創業の老舗のちくわやかまぼこ他の練りもの製品会社。
GEN-B(げんび~)の会
佐藤 元英(さとう もとひで)さん、佐藤 善彦(さとう よしひこ)さんご兄弟とは、堀田 雅湖(正子/ほった まさこ)さんが世話人をしておられる「豊・食・人 GEN-B」(げんび〜)」の会、に参加させていただいて、知り合った。
「げんび〜」は、三河弁で食いしん坊を意味するそうで、自社の練りもの製品を中心に、食いしん坊も納得の美味しい食が振舞われる。

練りもの製品は、何がはいっているかわからないのと、美味しいと感じたことがないので、筆者は、ほとんど好んで口にしないのだが、社長の元英(もとひで)さんが目の前で焼いて下さるちくわは、素直に美味しい。

それに、毎回、社長の元英(もとひで)さんのちくわ講釈があるのだが、

「おでんのタネは良く煮込みますよね、だしの味がよくしみて美味しいとか云いますけど、つなぎのでんぷんをたくさん使っているからで、ウチのちくわやごぼ天、はんぺん他の練りもの製品をおでんのネタにするときは、つなぎのでんぷんはできる限り使っていないので、だしで温めるだけで、決して煮込まないでください。せっかくの美味しさが全部、だしに出ちゃって、鰹節の出し殻のようになっちゃいます。」

と云う話が妙に耳に残っていて、一度、工場見学をしたい、と堀田さんにお願いしていたら、2018年11月に実現した。
元英社長の弟さんの善彦さんは、広告代理店で働いておられたが、呼び戻されて、現在、生産事業統括の常務をしておられる。 工場見学では、元英社長と善彦常務がご案内くださった。
ちくわ・かまぼこの歴史は古く、神功皇后が三韓渡航の途中、九州生田の杜(現在の小倉)で、鉾の先に魚肉をつぶしたものを塗りつけ、焼いて食べたという伝説があり、この食べ物が蒲の穂(がまのほ)によく似ているところから、「蒲穂子」と呼ばれ、「蒲鉾(かまぼこ)」に転じたと云われている。ところが、蒲の穂の姿は現在のちくわとそっくりで、その昔、「蒲鉾」といわれていたものが、ちくわの始まりだったそうだ。
文献に登場するのは室町時代になってからで、享祿元年(1528年)に著された「宗吾大双紙」には「かまぼこはナマズ本也、蒲の穂に似せたるなり」と記されており、貞享元年(1684年)に著された「雍州府志」には、「はも肉を取って細敲し、石臼にこれを摺り塩を加へて、尺許の円竹茎を心となし、外面円長にこれを塗り、焼いてこれを食す、これを蒲鉾という、されば則ち竹輪は古式にして、杉板に貼るところのものは近世の製也」と書かれている。
かまぼこからちくわへ

昔は、大名、旗本しか食べられないほど高級品だった蒲鉾も、江戸時代中期以降には、武士、商人、町人へと順次広まっていき、幕末になると下級武士は貧しくなり、旅先等では蒲鉾が食べられなくなった。一方、商人は金持ちになり、蒲鉾だけでなく贅沢な食事をするようになった商人たちを見て、「下級身分の分際で、武士の魂である鉾を食べるとは、何ごとぞ」と嫌がらせを言う武士がいたそうだ。
そこで、武士に気を使った庶民たちは、蒲鉾と呼ばれていたちくわの切り口が竹の様であるところから、竹輪と書き、武士にはわからない隠語として「ちくわ」と名づけ、いつしか、ちくわの方が、昔からの正式の呼び名のように定着し、板に付け蒸した板付蒲鉾が蒲鉾と呼ばれるようになったとのこと。

吉田宿(豊橋)で魚問屋を営んでいたヤマサちくわの祖先が四国の金比羅様に代参した際、その地の名物として売られていたのがちくわで、目新しく、食べてみると味もよく、海産物に恵まれた地である豊橋地方は原料となる魚には事欠かないと、さっそく製造にとりかかった。

ちくわの販路は、当時塩を運んでいたルートである「塩の道」を使い、魚類が不足している信州にも広げられた。そこで生まれたのが「塩漬けちくわ」で、徒歩か馬で物を運んでいた時代のこと、ちくわを一日でも長く保たせるために、塩を使った。ちくわの穴に塩をつめ、さらに上から塩をふった「塩漬けちくわ」は、豊橋のちくわ発展の源となった。このちくわを谷川の水に一昼夜浸して塩気を抜き、ほどよい塩加減にして食べたそうだが、大変な人気となった。
活気あふれる吉田宿の魚市場
吉田(豊橋)の地は、かつて伊勢の領地とされるほど、豊富な海の幸に恵まれており、伊良湖より東海道・新居の宿にいたる片浜十三里の海で獲れた魚は、必ず熊野権現神社境内で売り買いしなければいけないと決められていたため、魚類が一定の場所に豊富に集荷され、大いに賑わった。
当時は魚市場という名前はまだなかったが、慶長5年に正式な許可が下りて、活気あふれる魚市場が誕生し、この熊野権現神社周辺は、魚町と呼ばれ、ヤマサちくわもここに本店をかまえている。
原料の違いが、そのまま味の違いに
現在、練り製品の多くには、原料に冷凍したスケソウダラのすり身が使用されているようだが、ヤマサちくわでは、ちくわなど練り製品の味を決める上で重要なのは、まず原料である「魚」だと、原料にグチ、エソ、ハモを使用し、これを工場でさばき、すり身に加工している。

さばいてすり身に加工した原料は、臼で練り合わせ、味を調えるのだが、大切なのは、これらの工程をすばやく行い、その粘性を利用して型成して、加熱する。
焼き加減も味を決める重要ポイントで、その時々の天候に合わせた調整を始め、長年の修練と経験を持つ職人の技が味を決定している。

生魚は、獲れる時期によっても年度によっても味は違うものなので、毎回、同じ味加減と云うわけにはいかないが、原料を厳選して、素材そのものの旨みを引き出し、練り具合、焼き加減、手間をかけ、心をこめて、完成させる。機械には真似のできない職人の官能と技こそがヤマサちくわの財産だそう。
以上、元英(もとひで)さんのちくわ講釈でも伺った話だが、ヤマサちくわさんのWebサイトにそっくりそのまま記載されていたので、引用、抜粋、要約させていただいた。
以下は、Webサイトに載っていない講釈。
両端が白いちくわはヤマサちくわがつくった
―ちくわの両端が白いのは?
「ちくわの両端が白くしたのは、ヤマサちくわです。明治になって中央線ができて、東北の竹輪も長野に行くようになって、豊橋の竹輪が一目で見分けられるようにしてほしいと云うお客様からの要望があって、両端を焼かずに白く残した竹輪を作ったのですが、大手メーカーも同じように作り始めたので全国的にそうなりました。」
―各地の練り製品の特徴は?
「東京のかまぼこは山が高く、西に行くほど、平らになります。豊橋や小田原、東京のかまぼこは、生の身を蒸して作りますが、四国や下関など、西の方では、火で焼いてから蒸すので、表面にシワが寄るのですが、そのシワが綺麗だといいかまぼこだと云われています。」
「正月に食べる伊達巻きも硬さや卵や魚の量が地域によって全く違っていましたが、大手メーカ〜の作るハチミツや糖分の多いものが主流になってしまいました。」

「地域によって、姿形は変わるし、美味しいと云う、好みも変わるし、地域の材料でつくっているので、地域性があるのが、練り製品のいいところだったのに、全国一律の味になったのは、残念です。」
―練りもの製品本来の美味しさとは?
「歴史的には、西の方で獲れた魚でつくっていたのが、加工、冷凍技術の進歩で、冷凍すり身をつくれるようになったので、北海道でスケソウダラをたくさん獲るようになって、使うようになりました。」
日本にはいろんな魚を食べる文化があるのを残していきたい
「練り製品の一番の魅力は、味と食感、歯切れ、喉越しとかを含めた複合的なテクスチャーなのですが、それは、魚のすり身に塩だけで、味を決めます。複雑な味ではなくて、単味なのです。」
「噛めば噛むほど、食感も含めて、味わい深い食べ物ですが、歯応えだけ出そうと思えば、今は、そう云う添加物がいくらでもありますが、ウチでは、一切使いません。」
「練り製品の弾力のことをアシと云うのですが、毎日検食して、弾力性の出来がいいのをアシがいいと云います。アシを出すのが、練り製品屋の技術でも一番おもしろくて、腕の見せ所なのですが、原料が一番であり、白身の魚が必要条件になります。」

「魚の白身に塩を加えて、すり潰していくことで、塩によって、魚の白身のタンパク質の中のアクチンとミヨシンがアクトミヨシンに変化して、タンパク質ががっちり握手するように、網状構造が細かくできて、水加減、塩加減を上手くすることで、弾力性のある食感を生み出します。」

「今どきのつくり方は、大きなミキサーにすり身と塩を入れて、撹拌すると、粘り気は出ますが、均一になり過ぎて、歯応えがハム、ソーセージのような食感になるので、それって、私が美味しいと思う練り製品の食感ではありません。」
「ヤマサちくわでは、石臼に勝るものはない、と考えています。石臼が回ってる時に手を入れて、出来具合や加減を見るのですが、ハサップだと、手を入れてはダメ、フタをしなさい、と云うことになって、日本の伝統的な製法ではつくられなくなってしまいます。」
「魚も手で切っています。魚の身は割と柔らかいので、ローラーで狭い所に通し、圧力を掛けて、骨、皮と身を自然と分ける機械があり、これを何回か繰り返すのですが、一番最初に離れたいい身は、かまぼこやちくわに使い、3回目に取れた身は、ゴボ天のような雑味があったほうが美味しい練り製品に使いますし、骨やアラは、飼料や肥料の原料にするので、全く捨てるところがありません。」

「分けた身は、大きな洗濯機で洗い、脂と水溶性のタンパク質を落とし、魚臭が消え、色も白くなります。そのさらす水がポイントで、硬水を使うと身がパサパサになるので、やや軟水がベストです。江戸時代に掘った井戸からひいた石巻山からの地下水をを使っています。

「その井戸水で晒した魚の身のミンチを御影石の石臼に入れ、以前は、真鍮の杵を使っていましたが、緑青が葺くので、重いステンレスの杵で挽いたすり身を焼く、蒸す、茹でる、揚げる、加熱して練りもの製品が出来上がります。」

「この杵や石臼を毎回洗浄するのも大変な作業ですが、美味しいものをつくるには、どんな手間も惜しみません。」
―今後は?
「地元の子供たちにウチの製品のファンになってもらわないと、未来はありません。ちくわ職人と云っても、私ですが、スタッフと一緒に学校へ伺う、『出張ちくわ教室』を積極的に行っています。」
「ヤマサちくわの歴史や製法、ちくわが豊橋の地場産業として成長する過程を東三河の歴史と合わせて紹介し、その後、『ちくわ焼き体験』を行って、生徒さん一人一人が手作りでちくわを作り、炭火で焼いて仕上げます。」
「出来上がったアツアツのちくわを頬張りながら、『おいしい!』とうれしそうに食べる生徒さんたちの姿を見ると、こちらもとても嬉しい気持ちになりますし、毎回、皆さんから元気をもらい、励みにもなります。」

「ちくわ教室を通して、地元の子供達が地場産業について興味を持ってくれるきっかけになればうれしく思います。」
「私は、美味しいものが好きなので、旬の原材料を使った限定品や、新商品を次々に手掛けています。できる限り、添加物は加えませんが、今、自然食品店とコラボして、完全無添加の練り製品に挑戦しています。もう間もなく商品化できると思いますが、保存、流通の問題があり、冷凍での出荷になるでしょうね。」

「今や、カニかまは世界中で大人気なので、やれば儲かるかもしれませんが、『のようなもの』は絶対つくりたくないですね。」
「文政10年(1827年)創業以来、『鉛は金に変わらない』が、私どもの基本精神なので、いいものをつくるには、とにかく原料と製法にこだわり、ちくわやかまぼこにして美味しい、エソ、グチ、ハモを全国の漁港から買い付けて、自社でさばいています。これまでも、そしてこれからも、変わらぬ精神で本物の味を追求し続けます。」

本当に生の魚からさばいておられ、決して効率的とは思えない作業工程を従業員の皆さんが黙々とこなしておられる。
練りもの製品の原料の大半が冷凍すり身になった現在でも、ヤマサちくわの、ちくわ、かまぼこづくりは、魚の捌きで始まり、魚の捌きで終わるそうで、毎日、従業員の皆さん全員がマイ包丁を持って、魚を捌き、もちろん元英社長と善彦常務も、現場に入って、捌いておられたそうだ。

COREZOコレゾ「 鉛は金に変わらない、文政10(1827)年創業以来、 原料と製法にこだわり、 ホンモノの味を追求する、ちくわ兄弟(味見担当) 」である。
最終取材;2018.11.
初稿;2019.01.
最終更新;2019.01.
文責;平野龍平
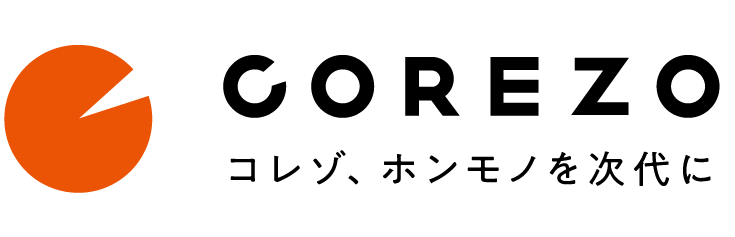
コメント