
目次
COREZOコレゾ「おいしいものは絶やさずつくり続けたい、バイクインストラクターから家業の道へ、他に比類のない、個性的な醤油づくりをどう継承していくのか楽しみな四代目」賞

片上 厚滋(かたかみ こうじ)さん

プロフィール
奈良県御所市森脇
片上醬油 四代目
片上醤油
動画 COREZOコレゾチャンネル
片上 裕之(かたかみ ひろゆき)さん/片上醤油(その1)「旨味成分が普通の濃い口より多い薄口醤油」
片上 裕之(かたかみ ひろゆき)さん/片上醤油(その2)「蔵主も醤油もちょ~個性的」
片上 裕之(かたかみ ひろゆき)さん/片上醤油(その3)「木桶で醤油を仕込むおもしろさ」
片上 裕之(かたかみ ひろゆき)さん/片上醤油(その4)「常に最高の醤油を目指しチャレンジあるのみ」
へんこで一途な片上社長が生み出した個性的な醤油たち
2025年7月の取材で見かけた醤油をご紹介いただいた。
「大和大鉄砲大豆」原料の醤油
「大和大鉄砲大豆」とは?
 元々、片上社長は、奈良の醤油屋なので奈良県で大豆栽培でがんばっておられる農家の皆さんを応援したいと、特別な原料を使う醤油以外の醤油には、ほぼ全量、近隣で採れたものを中心に奈良県産大豆を原料として使用してこられた。
元々、片上社長は、奈良の醤油屋なので奈良県で大豆栽培でがんばっておられる農家の皆さんを応援したいと、特別な原料を使う醤油以外の醤油には、ほぼ全量、近隣で採れたものを中心に奈良県産大豆を原料として使用してこられた。
奈良の農家さんが自家用に戦前から大切に植え継いできた、超大粒の在来種大豆「大和大鉄砲大豆」は、栽培が難しい上に、商売にならない程収量も悪いので、幻の大豆となっていたのだが、それでも農家さんが細々とひそかにつくり継いできたのは、とびっきり「美味しい」からだった。
その美味しさ、神々しいほどの粒の大きさに魅かれ、このまま廃れさせてはならないと奈良の豆腐屋さんが中心となって復活の活動が始まった。片上社長はこのプロジェクトに共感して、一緒に種をまく等の農作業にも参加し、収穫できたら枝豆祭りをしたり、その復活活動をしているグループで、味噌、豆腐、湯葉、きな粉他の大豆製品をつくっている中、大きく実ったその貴重な大豆を分けてもらい、丁寧に、そして慎重に醸造したのが「大和大鉄砲醤油」である。
通常の大豆で仕込んだ片上さんの醤油はクセが強いそうだが、この「大和大鉄砲醤油」は素直な醤油に仕上がり、「大和大鉄砲大豆」には、片上さんの醤油づくりの個性を上回る力強さがあるので、素直な醤油になってしまうのではないか、困ったもんだ、と片上社長。
大鉄砲再仕込み醤油「円熟」
大鉄砲こいくち醤油を作り、そこにもう一度大鉄砲を仕込んだ再仕込み醤油。超濃厚でありながらくせのない味わいで、なおかつ低塩分、まろやかで何にでもよく合い、醤油好きな方には是非試して欲しい、とのこと。
ただでさえ収量が少なく、グループの皆んなで分け合っている「大鉄砲大豆」なのに、2年間、醸造、熟成した「大鉄砲こいくち醤油」を出荷せずに一旦、桶に戻し、再度、1度目と同量の原材料を使って二度仕込みし、更に2年間の醸造、熟成で計4年、「大鉄砲こいくち醤油」の2倍の原材料と時間をかけて、収量は少なくなると云うとんでもない所業の末に生み出された。
これは、2年かけて出来上がった「大鉄砲こいくち醤油」があまりにも素直すぎて、天邪鬼な性格で独創性と個性の塊である片上社長が自分のつくる醤油ではない、と感じ、もう一工夫しようと、つくるつもりのなかった再仕込みをつくることになり、醤油蔵としてはやってられんわ、と云う商品であるが、これに魅せられてしまうお客様が多いため、つくり続けるしかなくなって、自らドツボにハマってしまった醤油、と片上社長。
大鉄砲うすくち醤油
「大鉄砲うすくち醤油」は、実の白い超大粒大豆の特長を生かし、通常の薄口醤油より更に淡い色と穏やかながらもフレッシュな香りが特徴で、白身のお刺身、シラスなど繊細な食材によく合い、特に上質な豆腐に使えば味が引き立つ、とのこと。
片上醤油だけでしかつくられていない、別格の青大豆醤油
青大豆とは
 未熟な若い大豆が枝豆で、枝豆は熟すと普通の黄色い大豆になるが、熟してなお青いのが青大豆。青くてもしっかり熟しているので、豆が丸々としていて、熟してなお青い「万年青年」のような大豆。
未熟な若い大豆が枝豆で、枝豆は熟すと普通の黄色い大豆になるが、熟してなお青いのが青大豆。青くてもしっかり熟しているので、豆が丸々としていて、熟してなお青い「万年青年」のような大豆。
青大豆の味の特長は「甘味」で、黄色い大豆は油分が20%くらいあるが、青大豆は油分が少なく、その代わり糖分が黄色い大豆よりも多いので、蒸しあがった直後の青大豆は本当に旨くて甘くて、美味しいそうだ。
普通の大豆は幹が伸びて枝が張り、その先に鞘(さや)がぶら下がるので、トラクターで根元から刈り取って収穫できるが、青大豆は地表近くに自由に弦(つる)を伸ばして鞘(さや)ができ、全部絡まっているので機械収穫はできず、ひとつずつ鞘を手で摘み取るしかない。
更に、青大豆は病気にかかりやすく、そのせいで全滅ということもありえる作物なので、農家さんにはリスクが高く、大きな面積で栽培できないので、青大豆はまとまった産地がなく、早く涼しくなる(実がなるときに害虫が少ない)東北や北海道で少量作られているだけとのこと。
青大豆醤油

北海道士別市の青大豆の生産者が「この美味しい青大豆で醤油を作ったらどんなに美味しいだろう」と考え、青大豆を託す醤油屋を探しておられたところ、縁あって、片上醤油でつくることになった。
毎年、士別から直接送られてくるのだが、醤油醸造に必要な何百キロという青大豆がまとまって栽培されるなど普通は考えられないので、青大豆醤油は、片上醤油だけでしかつくられていない、と云うことになる。
これまで年末に限定生産し、いつもすぐ売り切れてしまって、幻の醤油だったが、数年かけて仕込み量を増やし、通年販売できるようになった。現在、販売中の青大豆醤油は、桶で4年間熟成したのもので、通常、4年も熟成するとひね臭くなるのだが、そんな古びた臭さがなく、風格が増した中にも新鮮さを残していて、つくり手にもよくわからないが、青大豆は、3年、4年の長期熟成に耐えて、花開くのではないか、4年も前に仕入れた青大豆がようやく商品になるのだから、投資効率は最悪、と片上社長。
青大豆醤油は、こいくち醤油なので、お漬物、冷奴、焼き魚、お寿司、お刺身など、つけ、かけ用途は勿論、煮魚、肉じゃがなど、こいくち醤油を使うお料理に普通に使え、中でも青大豆の甘みが醤油に感じられるからか、この醤油は砂糖との相性が殊更に良く、割り下を使わず、まず、お肉を砂糖と醤油でジュジュ~と焼く関西風のすき焼きで、この醤油が引き出す牛肉のおいしさは、素晴らしく、ただ、この青大豆醤油は、ほかの醤油が物足りなくなる可能性があるので、この点のみ要注意とのこと。
このように醤油づくりに一切妥協しない片上社長の一途なこだわりがどれも個性が際立つ片上さんの醤油たちを生み出していて、それぞれの風味や特色、かけておられる手間と時間を考えたら、どれもこの価格で良いのか?と思う商品ばかりである。
無添加無調整の醤油づくり

日東醸造の蜷川社長から、和歌山に近い方の奈良でおもろいおっちゃんが木桶でおもろい醤油をつくっておられる、と聞いていて、蜷川社長に同行して初めて取材に伺ったのは、2018年のことだった。
片上醤油さんは、昭和6年の創業より、天然醸造の手法を守り、奈良県産大豆を主原料として、杉の大桶(計35本)の中で自然の季節のままに発酵熟成し、もちろん食品添加物等は使わない無添加無調整の醤油をつくっておられる醤油蔵である。主力は薄口だそうだが、濃口、再仕込もつくっておられる。
自称、2.5代目
「私の祖父が創業し、叔父さんが一旦継いだんですが、事情があって、別の仕事を始めてしまいました。私が継げと云われていたら、天邪鬼なので継いでいなかったと思います。しかし云われなかったので、農大の醸造科に進学し、醤油製造論は、あまり良くない成績のまま卒業して、醤油屋を継ぎましたので、3代目でもない、2代目でもない、自称、2.5代目です。」
醤油づくり教室は固定ファン獲得につながる

「最近、醤油のことにも詳しい方が増えていますが、詳しい人ほど、ご存じないところとの谷間が怖いほど深いですね。春先はできる限り醤油づくり教室をしているんですが、何回も続けて参加しているお客さんは、塩水に漬けた麹が醤油になっていくのを実体験されて、そういう谷間が埋まっていくのを実感しています。」
「自分でつくった醬油が無くなったら、自分のつくったもろみの兄ちゃん見に行こか、云うて来てくれはるんです。その時には、大概、友だちも連れて来てくれて、私より上手に説明してくれはるんです。有難い話ですが、そんな私どものファンになって下さるお客様ができるのが、ワークショップのええとこかなぁと思てます。」
蜷川社長がしろたまりのワークショップを始められた時、自分でつくれてしまったら、商品が売れなくなるのでは?と心配したが、自社商品のファンを増やす効果があるようである。
「人間って美味しいものを求めているんですが、頭も納得しないと、本当に満足できないのじゃないかと最近よく思います。」
色は淡くて、“旨い”、製法的には相反する、淡色天然醸造醤油への挑戦

「今や私の得意技は薄口しょうゆみたいになっていますが、そんなに窒素(うまみ成分)出してどうすんの?という、ある意味、薄口の素人やからつくれた品物なんです。」
「一般的にうすくち醤油は、塩辛く旨味も薄い物が多く、使い辛いとの声がありました。そこで、色は淡くて、“旨い”、製法的には相反する、淡色天然醸造醤油を目指しました。」
「丸大豆を使ってうまみ成分も濃口の特級ぐらい高い薄口の最大手メーカーの商品があって、そのうまみ成分を1割ぐらい上回る商品をつくる目標を立てました。原料には、着色成分の少ない麦を吟味し、大豆も着色成分を少なくできる工程を増やし、麹菌も普通は、全ての項目で及第点を取れる優等生タイプが使われるのですが、一芸にだけ秀でたヘンなヤツを使ったり、教えてもらったり、ありったけの技術をかき集めて、いろいろ試し、つくり始めて、10年掛かりました。」

「麹菌のコントロールは難しいもので、胞子着生まで成長すると、色が出るんで、人間で云えば、高校生ぐらいの所で止めたいのですが、成長を止めるために温度を下げると、今度は低温障害がでて、醤油が濁ると云う、どないせいゆーねん!と云う、ギリギリのせめぎ合いで、その狭いところを上手くやりこなさなければなりません。」
補助金を獲得して、麹室の設備を小さくする理由

「その麹づくりの精度を高めたいと、ものづくり補助金に申請したら、採用されちゃって、普通は、麹室の設備を大きくして、生産性も効率も向上するのが普通ですが、天邪鬼なので、小さくして、今の設備の能力を3分割して、一回に手入れできる適量になるようにする予定です。ま、自己資金をどうするか算段せんとあかんのですが…。針の穴を通すようなコントロールで、ピンと透き通った、薄口を安定してつくりたいですね。」
「ウチの蔵の発酵菌を調べてもろたら、初発酵の酵母だけで、熟成酵母がいないらしいんです。発酵始めたら、もっと行かんかい!どんどん行かんかい!全開で行かんかい!って云う発酵管理をしてきたんで、そりゃ、最後、ぼちぼちいくヤツがおらんのは、しゃぁないかなぁってとこです。普通は、乳酸菌がおって、主発酵の酵母がおって、熟成の酵母が最後、じわじわといくんですけど、ウチは、ガーンとわいて、ドーンと止まるんで、案の定、おらんかったんですわ。」

「そんなヘンな蔵なんですけど、蔵を世話する人間のクセとか、人柄とか、もろみとのやりとりとかで蔵の性格も決まるんで、仕方ないですね。それも特徴で、濃口も、オレがオレがと主張して、暴れる醤油なんです。」
「まあ、自分でも病的な天邪鬼だと思っていますが、自分の目の届く範囲で、自分の思うようにやりたいんで、自分の生きざまが蔵にも醤油にも出ていると思います。」
白身の刺身や冷奴にも合う薄口醤油

薄口醬油は、関西で好まれ、主に汁ものや煮物によく使われるのだが、濃口と比べると、一般に、色は薄く、うまみ成分は少なく、塩分濃度が高い。しかし、片上さん渾身の淡色天然醸造醤油は、おっしゃる通り、旨みのある薄口醤油。冷奴にかけてもいける、珍しい薄口で、平目の薄造りにスダチを絞って、ちょちょいとつけてみたが、白身の刺身の旨さが引き立ち、そこらで売ってる薄口とは、ひと味もふた味も違う。
片上さんと片上さんの蔵でしかつくれない薄口醤油である。

四代目 片上 厚滋(かたかみ こうじ)さん

片上 厚滋(かたかみ こうじ)さんは、片上醤油三代目の片上 裕之(かたかみ ひろゆき)さんのご子息。元々、家業を継ぐつもりだったそうだが、前職では、大手バイクメーカー関連会社でバイクのインストラクターとしてご活躍、バイクがますます好きになり、ご自身でも天職だと感じて、仕事に没頭し、バイクは最大で19台も所有されていて、実家に戻る際にも12台連れ帰ったそうだ。
バイクが好きだ、もっと上達したい、苦手意識を克服したい、久しぶりにバイクに乗りたい等々、個人のお客様だけでなく、企業内の指導者養成や学校他のクルマ・バイクの安全運転に関するニーズに合わせて、カリキュラムを組み、プログラムを提供して、楽しく安全運転が学べ、ドライバーやライダーの技能とマナー向上をはかることがインストラクターの業務とのことで、厚滋さんは、白バイ警察官のインストラクターも務めたそうだ。
しかし、社会人になって、いろんなところへ行き、いろんなものを食べるようになって、改めて実家で醸造している醤油の美味しさを認識され、このまま後継者不在で途絶えてしまい、美味しいものがなくなるのはもったいない、実家の醤油づくりの方が大事だ、という気持ちが強くなって、お父様が卒業された大学で研究生として醸造を1年間学んだ後、2025年4月に家業に入られた。
すぐに仕込みをさせてもらったが、発酵、熟成を経て、商品になって初めて、醤油づくりに携わった実感が湧いてくるのだろう、お父様の裕之(ひろゆき)さんは、ビキナーズラックだったのか、一番最初に仕込んだ醤油がとても出来が良かったので、それを超える醤油をつくろうと日々、切磋琢磨されているが、そんな記憶に残る醤油ができたら、とおっしゃる。
厚滋さんは、大学の研究生の頃から、自社が出展する催事やイベントを手伝っていたが、醤油のことも自社の商品のことも教えたことがないのに、既に3年ぐらい醤油屋をやっているような顔をして説明しているのを横から見ていて、「門前の小僧、習わぬ経を読む」ではないが、それなりに受け応えができているので、やりたいようにやったらええわ、と思てます、と片上社長さん。
「門前の小僧、習わぬ経を読む」
寺の門前で遊んでいる子供でも、いつも読経の声を聞いていれば、習いもしない経を誦(そらん)じれるように、繰り返し見聞きできる環境にいれば、自然とその知識がつくようになるものであるという例え
厚滋さんは、学生の頃から、片上醤油と取引のある飲食店を利用する際には、自ら醤油屋の息子を名乗って身内扱いをされていたそうで、その頃から家業の醤油がどう云う方々に好まれ、どのように使われているか、それとなくリサーチされていたようだ。
また、戻られてから、インスタグラムやSNSのアカウントをつくって、既に片上醤油を使ってくださっている飲食店さん等と連携をして展開すると広がりやすいので、先ずそう云うところから始めていて、直接、購入に来られるお客様には、使われる料理やお好みを伺ってご案内やご説明をするのはもちろん、今、自分ができることからやっていきたい、何よりも、おいしいものをつくり続けることが、一番で、大手企業で勤めた経験も活かして、仕事のやり方も変えていけたらと思うし、父の血を引いているので、自分も自分の好きなようにやりたい、と厚滋さんがおっしゃるのを嬉しそうに横で聞いておられる片上社長の笑顔がとても印象的だった。

片上社長が続けてこられた他に比類のない、個性的な醤油づくりをどう継承していかれるのか楽しみな四代目である。
COREZOコレゾ「おいしいものは絶やさずつくり続けたい、バイクインストラクターから家業の道へ、他に比類のない、個性的な醤油づくりをどう継承していくのか楽しみな四代目」である。
最終取材;2025.07.
初稿;2025.08.
最終更新;2025.08.
文責;平野龍平
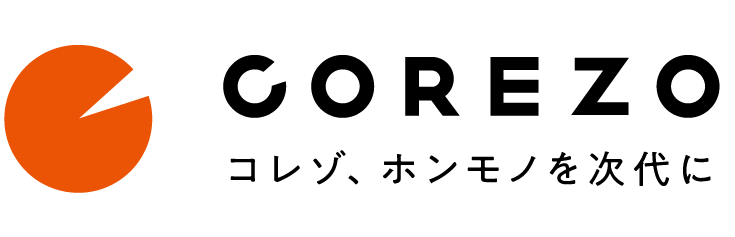
コメント