
F1種のつくり方
前回、「人為的除雄」、「自家不和合性」について書いたが、今回は、現在、F1育種の主流になっている「雄性不稔」について。
下記の不人気ネタを先に読んで頂ければ、よりわかり易いのではないか、と思う。
https://corezoprize.com/seed-4-inheritance
https://corezoprize.com/seed-5-mendels-laws
「雄性不稔」とは?
雄しべがない、もしくは、雄しべはあっても花粉がなく、雄の機能を果たさないこと。
雄性不稔種の発見
1925年にアメリカの農業試験場で花粉が出ない「雄性不稔」の赤タマネギ(イタリアンレッド)株が発見された。さまざまな研究の結果、雄性不稔の個体は、花粉がつく正常な個体と掛けあわせても雄性不稔となり、母系遺伝で子に伝わることが判明した。
この性質を利用して、既存の雄性不稔の母株を使えば、「戻し交配」を繰り返して、掛け合わせた品種も簡単に雄性不稔化することができる。
こうしてつくった雄性不稔株を使えば、人為的除雄や自家不和合性のように手間をかけずに、F1種を効率的、かつ無限に近く増やすことができ、種苗メーカーにとってはドル箱になるので、この雄性不稔の個体を探すのに躍起になっているそうだ。
しかし、自然というのは常に本来の姿に戻ろうとするので(遺伝子組み換えは元に戻らない)、時々、雄性不稔の野菜の中には、雄しべのある正常な花が咲くこともあるそうだが、種苗会社は、それを見つけては破棄してしまうという。
バッククロス(戻し交配)とは?
「雄性不稔」の赤タマネギをメジャーな黄たまねぎにするために、雄性不捻の赤タマネギを雌株にして黄タマネギの花粉をかけると、赤50%対黄50%の子F1ができ、できた子F1も雄性不捻になるので、できた子F1を雌株にして親と同じ黄タマネギを掛け合わせると、F2は、赤25%対黄75%となる。この作業を繰り返すと、次のF3は、赤1対黄7となり、同じことを5〜6回繰り返せば、限りなく黄タマネギに近づいていく、こうして、雄性不捻の黄タマネギが誕生した。
このように、他品種から必要な形質を取り込む方法を、「バッククロス」または、「戻し交配」と呼び、1944年、こうしてできた雄性不捻のF1タマネギが販売開始され、以後、このたった一個の赤タマネギから見つかった雄性不稔因子は、どんどん増殖され、世界中のF1タマネギの母親株として受け継がれているそうだ。
その後、トウモロコシ、テンサイ、ニンジン、ラディシュ等で雄性不捻株が見つかり、母系遺伝の便利さから、欧米のF1育種の中心技術として広まり、その後、日本でもイネやダイコンなど、さまざまな栽培植物で雄性不稔が見つけられ、ネギを筆頭に、日本独自の野菜も雄性不捻になっていった。
雄性不稔とミトコンドリア
近年、核やミトコンドリアの遺伝子の解明が進むことで、花粉を作らない性質(雄性不稔)は、ミトコンドリアの遺伝子の一つが働いて現れることが明らかになった。
細胞質遺伝子
普通の生物、すなわち、細胞核を持たない原核生物以外の真核生物の場合、細胞は、大きく分けて核と細胞質からできていて、ミトコンドリアは細胞質にあり、遺伝子は核と細胞質の両方に存在しているのだが、一般的に遺伝子と呼ばれるのは、核遺伝子の方なので、それと区別するために、植物は葉緑体にも遺伝子があり、それも含めて細胞質遺伝子と呼ぶそうだ。
その生き物の性質のほとんどは核遺伝子によって決められるが、ごく一部は細胞質中の細胞質遺伝子によって決められる。雄性不稔現象は広範囲の作物で見つかっていて、この現象は核遺伝子に由来するものと,細胞質に由来するものとがあり、育種に利用されやすいのは、後者の母系遺伝する細胞質遺伝子に由来する「雄性不稔」であるので、「細胞質雄性不稔」という言葉が使われる。
一般的な遺伝の法則の基本である、メンデルの法則は、核の減数分裂と融合のしくみに基づいているが、細胞小器官に由来する遺伝形質はそれとは独立して伝わるため、その形質はメンデルの法則に従わずに遺伝する。 例えば、動物の受精において、精子のミトコンドリアはほぼ排除されるため、その形質は雌親の持つ形質を伝えることになり、同様に、植物の葉緑体に関する遺伝形質も、雌親の形質が伝わることが知られている。
また、細胞質遺伝因子の突然変異による遺伝病も知られているそうである。
ミトコンドリア遺伝子が母系遺伝するワケ
生物の種によって異なるが、数十から数万のミトコンドリアを持つ精子が卵子と受精すると、卵子内で細胞融合する過程で、精子から運ばれたミトコンドリアは卵細胞の分解酵素によって全て分解されるため、基本的には、全てのミトコンドリアの遺伝子は母系遺伝する。
このことは父系と母系の入りまじった核DNAと異なり、ミトコンドリアDNAでは、確実に何世代か前の1人の母系の祖先の持っていたミトコンドリアDNAに辿り着くことができるので、種の系統関係を復元するのに非常に適しているそうだ。
ただし、全ての生物のミトコンドリアが母性遺伝するとは限らず、異種間の交雑ではミトコンドリアが父性遺伝する生物種もあることが報告されているそうで、このメカニズムは、実際のところよく分かっていない部分もあり、今後の研究成果が期待されるとのこと。
雄性不稔のしくみ
ミトコンドリアは雌性配偶子を通してしか次世代へ伝わらないので(母系遺伝・細胞質遺伝ともいう)、花粉をつくる資源を種子形成に当てさせ、多くの種子をつくらせることによってミトコンドリアは利益を得ることができるが、花粉形成ができないことは、核遺伝子にとっても、植物にとっても不利益であるため、花粉の稔性を回復する核遺伝子(稔性回復遺伝子)を持つことで対抗してきたそうだ。
こうして細胞内では、核遺伝子とミトコンドリア遺伝子がせめぎあってきたわけだが、当然、核遺伝子の方がミトコンドリア遺伝子より強いので、雄性不燃の個体の方が圧倒的に少ないのは云うまでもない。
雄性不稔の品種改良への活用
植物には、ミトコンドリアに花粉を作らせない遺伝子(雄性不稔遺伝子)を持つものと持たないもの、核にその働きを抑える遺伝子(稔性回復遺伝子)を持つものと持たないものがあり、このうち、野生植物では、ミトコンドリアは雄性不稔遺伝子を持ち、核も稔性回復遺伝子を持つ組み合わせが進化し、栽培植物ではミトコンドリアは雄性不稔遺伝子を持たず、核も雄性回復遺伝子を持たない組み合わせが発達してきたことがわかってきた。
そこで、人為的に野生種と栽培種を掛け合わせることによって、ミトコンドリアは雄性不稔遺伝子を持ち、核は稔性回復遺伝子を持たない組み合わせの品種が開発されて、これが品種改良に活用されるようになったたいう。
ミトコンドリアとは?
ヒトの体は、約60兆個の細胞で構成され、その細胞の一つ一つに核があり、核の中には両親から由来する二組の染色体が収められている。染色体は23対46本あり、DNA(デオキシリボ核酸)と各種タンパク質から出来ている。
細胞とは、全ての生物体を構成する基本単位で、さまざまな形を持つが、基本的な形は球状で、生物は単細胞生物と多細胞生物に分類される。全ての細胞は細胞膜で覆われており、その中には核があり、核の周りは細胞質で満たされ、小胞体、ミトコンドリア、リボソームなどの細胞小器官が点在する。
https://corezoprize.com/seed-4-inheritance
ミトコンドリアという小器官は、ほとんど全ての生物の細胞内にあり、細胞が活動するためのエネルギーをつくりだすという、極めて重要な働きをしている。mt(ミトコンドリア)DNAは核DNAと同じ二重らせん構造だが、核DNAが線状(糸のように細長い形状)であるのに対し、一般的には環(リング)状の二本鎖構造をしていると云われる。
ミトコンドリア遺伝子の働き
生命誕生の初期において、ミトコンドリアは、独立した単細胞生物で、エネルギーを効率的に作り出してくれて便利なので、多くの生物はそのまま細胞の中に共生させる道を選び、今の細胞が出来上がったのではないか、という説がある。
元々、宿主の細胞とは異なる生物であり、有性生殖ではないので、細胞分裂に先立ってミトコンドリア自身も分裂し、この時、ミトコンドリアのDNAのコピーは核DNAとは独立して行われるが、実際は、核の遺伝子で厳密な制御を受けているという。
mtDNAには、ミトコンドリアの構築やエネルギーを作り出す機能に必要なタンパク質などに関する情報が主に記録されているが、ミトコンドリアに必要な情報の大部分は核DNAに含まれており、ミトコンドリアは細胞の外で単体では存在できない。また、一方で細胞が必要とするエネルギーを酸素を利用して取り出せるのはミトコンドリアの働きによってであり、細胞自体もミトコンドリアなしには生存できない。これらのことから、ミトコンドリアが細胞内共生由来であるという仮説の傍証となっているそうだ。
参考
http://www.geocities.jp/ikoh12/kennkyuuno_to/002_1mtDNA_2_1iceman.html
ミトコンドリアは、呼吸やエネルギーに変換されるATP(アデノシン三リン酸・高エネルギーリン酸)の合成する働きをしていて、雄性不稔遺伝子は呼吸やATP合成の遺伝子のすぐ近くにあることが多く、それらを阻害する働きを持っていて、植物の成長段階では、この遺伝子は作用しないが、莫大なエネルギーを必要とする花粉を作る段階になると、呼吸やATPの合成の働きを抑制して、うまく花粉を作ることができなくするそうである。
ハマダイコン
日本のダイコンの栽培種の多くは、ミトコンドリアに雄性不稔遺伝子を持たないため、地中海周辺のダイコンを先祖に持ち、ユーラシア大陸を東に渡って、中国を経由して日本にもたらされた種類だと長らく考えられていたが、舞鶴地方などのいくつかの地方の在来種ダイコンは、ミトコンドリアに雄性不稔遺伝子を持っていて、その由来が日本の海岸部に自生する野生のハマダイコンであることが判明した。
日本でも野生のハマダイコンからダイコンの栽培品種をつくりだしていたことが明らかになったことから、現在では、世界の一箇所から広まったのではなく、世界のあちこちで野生のダイコンからダイコンの栽培品種が生まれたのではないかと考えられているそうだ。
ダイコンを使ってキャベツやハクサイの雄性不捻F1種をつくるって⁉︎
ダイコンの雄性不稔を発見したのは、日本の研究者だったが、その性質に注目せず、利用しないでいたところ、フランス人の研究者が細胞融合の技術も使って、同じアブラナ科のナタネと掛け合わせて雄性不稔のナタネをつくり、特許を取得したという。
今では、日本でも、雄性不捻株が出る確率が高い野生品種のハマダイコン(アブラナ科ダイコン属)を使って、同じアブラナ科アブラナ属のキャベツやハクサイの雄性不捻F1種を作っているとのことで、その方法は、「雄性不捻」の大根を雌株に、キャベツを雄株にして、「自家不和合性」の進化形と同様に、ハウス内のCO2濃度を高め、ミツバチを放つと、大根はキャベツの花粉でも受粉して子供を作るそうだ。
その後、「戻し交配」をして、「雄性不捻」のキャベツが出来上がるというのだが、但し、二酸化炭素は受粉し易くするためで、なくても手作業でもダイコンとキャベツ類の交配ができ、雑種は作れるそうだ(育種の専門家である石綿薫さん談)。
こうなると話がややこしいのだが、見た目は同じダイコンやハクサイ、キャベツのタネで、できるのも姿は同じようなダイコンやハクサイやキャベツだが、その遺伝子は、ダイコンともハクサイともキャベツともいえないものに変化しているそうだ。
まとめ
雄性不稔による品種改良技術によって、F1種育種の効率が飛躍的に向上した。
雄性不稔は、野生の品種で見つかることが多いらしく、野生の品種を母株に栽培品種を掛け合わせてつくるようだ。それにも雑種強勢が最大限働くように選抜するのだから、大変な作業であろうことは容易に推察できる。
雄性不稔がミトコンドリア遺伝子の突然変異、異常だという意見もあるが、栽培品種の元になっている野生品種は、ミトコンドリアに雄性不稔遺伝子をもつものが多いらしく、自然界では、細胞内でミトコンドリアの雄性不稔遺伝子と核の稔性回復遺伝子がせめぎあっているという説もあるので、異常かどうかは、皆さんでお考え頂きたい。
ただ、ミトコンドリアが真核細胞と共生するようになったのは遥か10億年以上も前の出来事だそうで、それ以来、もともと別の生き物だったといわれる真核細胞とミトコンドリアは、真核細胞が核に大量の情報を持ち、ミトコンドリアが呼吸やエネルギー生産をするという役割分担をしながら共生を続けてきたのに、植物の長い進化の歴史において、花粉を作るようになったのは比較的新しいらしく、そんな中、核とミトコンドリアがせめぎあっているように見える雄性不稔という性質がどういう理由で発現するようになったのか?自然の摂理は不思議で深遠である。
参考
http://www.kyoto-su.ac.jp/project/st/st17_07.html
関連記事
https://corezoprize.com/seed-6-hybrid
https://corezoprize.com/seed-5-mendels-laws
https://corezoprize.com/seed-4-inheritance
https://corezoprize.com/seed-3-hybrid
https://corezoprize.com/seed-2-tomato
COREZO (コレゾ)賞 事務局
初稿;2015.05.26.
編集更新;2015.05.26.
文責;平野龍平
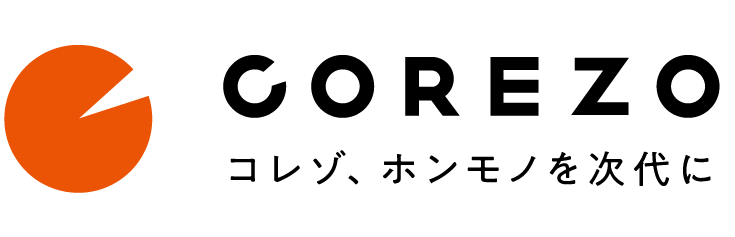
コメント