
目次
育種と自然農のプロ、石綿薫さんの見識
公益財団法人自然農法国際研究開発センターで研究員を務めておられた育種のプロで、自然農法による農園を営んでおられる石綿薫さんの「種タネの話」はとても示唆に富んでいるのでご紹介しておきたい。
https://corezoprize.com/kaoru-ishiwata
アブラナ科野菜の自家不和合性
アブラナ科野菜は自家不和合性を持ち、他家受精の機会を増やしており、結果として近交弱勢を回避することに一役買っている場合が多いとはいえるが、アブラナ科作物には自家受精する作物もあり、それぞれの生存戦略の中で、自家不和合性が果たしている役割は異なるから、アブラナ科野菜は近交弱勢を避ける為に自家不和合性を身につけたとはいえない。
既存のアブラナ科野菜(キャベツ類、ハクサイ、カブ、ダイコンなど)のF1品種の多くは、強い自家不和合性の系統を選び出し、自家不和合性遺伝子型をホモ(純系、全ての対立遺伝子が同型接合していること)化して、雑種を採種する方法を採用している。
例として、あるカブ品種の固定種を想定すると、まず、自家不和合性には強弱があり、固定種品種内の全ての株が他殖するわけではなく、自殖する株もあるし、同じ自家不和合性遺伝子型同士でも交雑する株もあるので、自家不和合性遺伝子型がホモ化している個体というのも固定種内にも存在する。
つまり、カブの固定種に自家不和合性遺伝子型のホモ個体が存在することはあり得ることだが、1つの集団が1つの自家不和合性遺伝子型で揃っているということは起きないだろうといえる。
雑種強勢
通常のアブラナ科野菜の固定種中では、他殖個体が大半を占め、個々体は常に雑種状態といえるが、それは雑種強勢とはいわない。
雑種強勢というのは、自家不和合性とは別のもので、カブの根部の形状が若干縦長であるものと横長であるものが交雑したら、F1は両親の中間の形状で揃い、しかも大きなカブになるといった現象のこと。雑種になれば必ず強くなるわけではなく、雑種強勢が大きく現れる組み合わせがあり、F1品種はこの特定の組み合わせを見出して利用している。
雄性不稔
「正常な生殖能力を持たない異常な株、ミトコンドリア異常で起こる雄花のない異常株は、人間に例えるとインポや無精子症の個体の性質である。しかし、自然にはミトコンドリア遺伝子を修復しようとする働きもあって、花粉をつける株を見つけると、種苗会社はすべて排除する。健康を取り戻そうとする野菜を排除して不健康な野菜を商品とする種苗業は何かおかしいし、我々は、そういう不健康な野菜ばかりを食べている。」
というような論調が世の中にあり、異質な遺伝子に対して何か不健康なものというイメージで捉えているように受け取れるが、遺伝子を人間の判断で健康、不健康と分けることは出来ないと思う。
多くの作物で雄性不稔が知られており、作物一般の性質と考えることができる。しかし、それがその作物にどう役立っているかは、個別的なことで、種族の弱体化を防ぐ場合もあるだろうし、何の役目も果たしていない場合(生存に対して中立)もある。その作物種の生殖様式や周囲の自然環境や人間との関わり方によっても役割は変わってくる。
そのような多様なあり方を通して作物は進化・分化してきたのであり、近交弱勢を避けるためといった合目的的な解釈は出来ない。
異常という表現は、生物学研究としては「異なるタイプ」という意味で、雄性不稔もその生物が持つたくさんの性質の1つであり、実は、雄性不稔の仕組みも多様である。
いくつかの植物の雄性不稔はミトコンドリア遺伝子の特定の型があり、それが雄性の生殖器官の形成時に通常とは異なる発育過程をとらせる引き金になることが知られていて、これは、生物のもつ遺伝子の多様性、形質の多様性の表現であるといえる。
生物種ごとに、生殖方法、花粉や種子、そして1個体の重みは全て異なり、雄性不稔個体が果たしている役割も異なり、その生物種にとって不稔個体が一定割合で存在することが必要な(=正常である)こともあると考えられるので、不稔株を異常と判断して良いかどうかは、その作物種ごとに事情は異なる。
また、植物は、生殖様式も集団の持つ意味も人間とは異なるので、人間に例えることが適切だとは思えない。
ダイコンとキャベツ類の交配
ダイコンとキャベツ類の交配は、手作業でやっても成功する。二酸化炭素は花粉を入りやすくするために使うが、なくても雑種は作れる。一度雑種になれれば、戻し交雑をしていけばいいので、細胞質を入れ替えるのは難しいことではないが、相当な根気が要る。今はそのような丁寧な職人仕事をする人がいなくなったので、細胞融合に頼ることになる。
植物の種の壁はいい加減なので、種がめちゃくちゃにならない程度に、生理学的な壁や生態学的な壁、地理的な壁など様々な壁が組み合わさって、良い加減に調整されている。そして様々なアクシデントが重なった時にエラーが起きる機会を保障しているように見える。ケール類とカブ類の交雑からナタネが生まれたり、2種の開花時期の違う桜品種が交雑してソメイヨシノが生まれたり、事例に事欠かない。
ダイコンのオグラ(花粉ができない)細胞質の由来
ダイコンの近縁種(雑草)にRaphanus raphanistrumという植物があり、ヨーロッパからアフリカ、インド、東アジアの沿岸に自生しており、日本のハマダイコンがそれにあたる。小瀬菜ダイコンはハマダイコンの細胞質に栽培ダイコンが自然交雑し、核遺伝子が栽培ダイコン主体にしだいに置き換わって成立したもの、つまり、小瀬菜ダイコンのオグラ細胞質は、ハマダイコン由来の細胞質だったことがわかった。
同じように、世界のダイコンを調べるとハマダイコン由来の細胞質を持つ自然置換型の品種/集団がいることも分かり、逆に東アジア地域のハマダイコンには栽培ダイコンの遺伝子が多数入り込んでいることも分かっって、ハマダイコンがヨーロッパからアジアへ広がってくる過程で、栽培ダイコンと着かず離れずの関係を保ちながら、適応力を獲得してきた歴史が伺える。
Raphanus raphanistrumの細胞質には、栽培ダイコンとは異なる細胞質遺伝子(ミトコンドリアや葉緑体、色素体)の特性があるので、核遺伝子との相互作用の中で、葉緑体の数が増えにくかったり(葉色が黄色がかる)、雄しべ形成のエネルギー(ATP)生成レベルが若干低かったりなどの、細胞質と核遺伝子間の組み合わせごとの個性を持つ。
ハマダイコンにはRaphanus raphanistrum細胞質の遺伝子との間で正常に雄しべを生じさせる核遺伝子があり、ハマダイコン細胞質を持つ自然置換型ダイコン(小瀬菜ダイコン)の集団中にもその核遺伝子は受け継がれている。
しかし、ハマダイコンの中にも、自然置換型栽培ダイコンの中でも、全ての個体でその遺伝子をホモ保有しているわけではなく、その核遺伝子も1種ではなく、かつ環境の影響を受けるため、完全な雄性不稔から中途半端な雄性不稔、ほとんど正常なのだけど、開花始めだけは花粉が出ないといった強弱がある。
例えば、雄性不稔と思われたが、リン酸肥料をたくさん与えると花粉を生じるといった感じで、主要な稔性回復遺伝子があることは知られているが、その発現・効果に影響する微動遺伝子も多数ある。
オグラ(花粉ができない)細胞質は異常か?
オグラ細胞質は異常ではなく、あくまで核遺伝子との相互作用の中で、雄性不稔という表現になるだけで、Raphanus raphanistrumではそれが正常であり、小瀬菜ダイコンにおいても正常なのである。
栽培ダイコン型、Raphanus raphanistrum型(=オグラ型)という細胞質遺伝子に優劣はなく、どちらもRaphanus属植物の持つ遺伝子の多様性そのものである。そしてハマダイコンにおいては、栽培ダイコンの遺伝子を受け入れることで、集団内の多様性を増して適応力を広げてきた歴史があり、その一部として雄性不稔という性質を獲得したと考えられ、もしかしたら集団の強さの維持に役立っていたかもしれないというものである。
オグラ細胞質自体が異常でないなら、オグラ細胞質との間で雄性不稔を発現させる核遺伝子が異常なものなのだろうか?この核遺伝子は通常の栽培ダイコンが持っている遺伝子そのものであり、どうにも「雄性不稔株は異常株だ」という根拠は分からない。
キャベツ類の雄性不稔系統の作り方
キャベツの細胞質をダイコンと入れ替えると(交配法でも細胞融合でもできる)、ダイコンがオグラ型でなくても雄性不稔を生じることがあるが、これはやってみないと分からないし、また、同時に葉緑体の増殖が悪くなることが多い。いろいろステップを踏むことは面倒で時間もかかるので、キャベツ類の雄性不稔系統は、ダイコン自体が雄性不稔になるオグラ型を用いて細胞融合経由でキャベツへダイコン細胞質を渡し、さらにあとで葉緑体だけキャベツからもう一度もらい直して、作り出された。
核の稔性回復遺伝子はダイコンからキャベツ類へ積極的に移動されていないので、おそらくこの雄性不稔はそう簡単には回復因子が見つからないかもしれない。しかし、採種現場レベルで頻繁に稔性回復株が見つかるなら、キャベツグループ内に回復遺伝子や環境の影響によって雄性不稔を不安定にする微動遺伝子があってもおかしくないだろう。
キャベツの細胞質にダイコンの細胞質が混ざっているというのは、細胞質と核の関係が、栽培ダイコンとその近縁野生種との関係のように容易に入れ替わって出来たわけではないので、短期的にみたら不自然だが、アブラナ科作物の進化史という長いタイムスパンでみたら反自然ではないと思う。アブラナ科作物には、こうした良い加減な種の壁によって、細胞質の多様性を増してきた歴史がある。
現に花粉が生じるものが出てくるということは、キャベツ類側では、新しい細胞質タイプの受け入れが始まっていると見なせるだろう。雄性不稔系統に花粉を生じる個体が混じったとしてもそれがオグラ細胞質が栽培型に変異したのか、核遺伝子側が変異したのか、別の微動遺伝子の作用なのか、環境の影響なのか原因は様々に考えられる。また、現場レベルで原因が追求されることもないので、花粉が生じたことが何を意味するかは不明だ。
元々優劣のない遺伝子を健康とか不健康と色分けすること、遺伝子が修復されたとか、健康を回復したという表現をすることは不適当ではないかと思う。どうにかしてF1品種を有害なものに仕立てあげたいのだろうか?
特定の遺伝子型のみを栽培品種として利用することの危険性
特定の遺伝子型のみを栽培品種として利用することの危険性は、その遺伝子型のみに感染する病害が蔓延する可能性があるなど、遺伝育種学の世界でも昔から指摘されている。
有名な事例として、19世紀のヨーロッパのジャガイモ品種は、南米からもたらされた2品種から全て由来し、特にアイルランドは極少ない品種が全土に作付けされていたのだが、1846年にジャガイモ疫病が大発生し、大飢饉が発生した。また、1970年代のアメリカでは、四分の三のトウモロコシF1品種にT型細胞質の雌系統が使われており、T型細胞質のみを犯すごま葉枯れ病が発生して大被害が出たという歴史がある。
出来るだけ栽培品種の遺伝子が多様なもので構成されていることが望ましいのは言うまでもない。雄性不稔性やそれの引き金になる遺伝子が不健康なのではなく、栽培品種が右へならえで、1つの遺伝子型のみが使われてしまう社会の方が不健全だと思う。
有機農業や自然農法を次世代の農業として推進していくために必要なこと
遠縁交雑や突現変異、雑種強勢利用など植物が自ら変異する仕組みを利用する品種改良は、自然農法、有機農業においても有用な方法であり続けると思う。現状の種苗業界のあり方は、たくさんの問題を含んでいるが、そのことをもって交配種を否定することは筋違いだろう。専業農家が誰でも容易に有機農業に取り組める技術開発の中では、交配種の利用は否定されるものではないと思う。在来種を守り、その自家採種や地域採種を復活推進することと、専業農家の使用に耐える種苗開発を両立させていく必要があると思う。
有機農業や自然農法を次世代の農業として推進していくためには、そうした農業に取り組む人が、その地域の品種を生み出すために参画できる取り組み、仕組みづくりが必要であり、国や地方の試験場はもちろん、民間業者も参加しての有機の種苗開発がこれからの日本農業に活路を与えると思う。種苗の採種そのものが自然農法で行われることが理想的である。
花粉を出さない品種がタネの歴史の終焉につながるワケ
冷涼地の6月中旬まき不耕起栽培に適するニンジン品種の検討に際し、ある種苗会社の品種もこの作型には合いそうなものがいくつかあり、色が濃いとか収量性とかは魅力だが、自家採種をしようとしても、花粉が出ないので、あえて外している。
他メーカーの品種は雄性不稔を利用したF1と言っても、花粉系にRf遺伝子(稔性回復遺伝子)を持つものが多く、花粉が出るのが普通だが、その種苗会社は、ニンジンだけでなくダイコンでも雄性不稔利用を進め、しかも花粉親系統からもしっかりとRfを抜いている品種を出してきているようだ。
F1品種を環境適応性を高めた育種素材と捉えれば、その品種を育種や自家採種の素材に用いるかどうかは使う人次第。種苗会社同士でもそうやって、お互いの品種をライバルとして育種素材にしあうことによって、良い意味での開発競争も悪い面としては似たような品種ばかりになる現実も作ってきた。それがタネの近代史。
花粉を出さない品種は絶対に他人に自分のところの品種を素材としても渡さないという態度。品種による遺伝資源の流通が止まれば、それはタネの歴史の終焉につながる話であり、やがては自らの存在基盤を崩していくこと。その種苗会社の積極的に新しい価値を提案する育種方針自体は好きなのだが、その利己的な態度は問題で、あまり相手にしたくない。
放射線突然変異や細胞融合よる品種改良
自然界でも細胞融合は起き、卵細胞の細胞融合によって、倍数体植物が生じたり、接ぎ木部から異数体化した枝変わりが発生したりする。染色体が何本か落ちたり、核だけ入れ替わったりするので、言わば非対称細胞融合、自然のバイテクである。
放射線突然変異や細胞融合よる品種改良は、実は自然界でもまれに起こる現象をほんの少し出現頻度を上げているだけで、細胞(命)そのものを人間は合成できない。細胞融合で融合して一応植物として成立するポマト(ジャガイモ+トマト)などは、接木部から発生するキメラ(異なる遺伝子型の細胞が共存している状態)植物中から自然発生してくるものである。
通常はタネの出来ないサツマイモや昔から接ぎ木をしてきた果樹などでは突然変異が多く、なぜ作物は突然変異しやすいのかは人類にとってロマンのあるテーマ。これらの技術は無理矢理やっているように見えても、選択権は植物にあり、最終的にはその生物が環境中でその性質をどう使うかということが選抜の要で、植物体に備わる変異性を引き出し、その体の一部を使って行う品種改良にとって、これらのバイテクはそのツールの1つに過ぎない。
遺伝子組み換え農作物
しかし、遺伝子組み換えは事情が全く異なり、遺伝子を任意の配列につなぎ替えて無理矢理タンパク質を作らせる技術は、植物側に選択権がない。またその遺伝子が導入後にどのように挙動するかなど、分からないことが多すぎ、生物自身が環境と関わりながら自ら変わるわけではないことから、遺伝子組み換えは品種改良とはいえないと考えている。
遺伝子組換え作物の開放圃場での商業栽培などの承認申請について
2011年、モンサント社およびシンジェンタ社、ダウケミカル社が遺伝子組換え作物の菜種、とうもろこし、綿の第1種使用(=開放圃場での商業栽培など)の承認を農水省に申請したことに対する、石綿さんのパブリックコメントは以下、
承認に反対。最近、土壌環境中にはウイルス以外に植物や土壌微生物由来の核酸物質が蓄積し、一部は遺伝物質としての活性があり、土壌微生物に取り込まれるなどの動きがあることが分かってきている。生物遺体(作物残さ)-土壌-微生物間の遺伝物質の動きに関して、我々はその全容が分かっていない。植物の遺伝子組み換え自体が完全な制御ができるわけでもなく、生物工学の安易な実用化は慎むべき。
また、食糧問題や農業コストの改善には社会構造の見直しや環境経済学的観点からの社会コスト計算という取り組みが必要であって、GM作物による栽培法が必須といった技術問題ではないことは明白。
食糧の安定供給に資する作物育種に関する技術課題としては、作物品種を地域の生態系に合わせるためのローカルな育種こそ必要であり、世界企業の開発する少数品種による作物品種の多様性の貧相化はこれに逆行する。
使用申請の不承認を徹底することにより、開発企業は品種開発の方向性を地域農業の応援や品種の多様性の増進に向けていくことが期待される。企業活動に対して単なる規制をするのではなく、地球環境や人類全体の幸福を鑑みて在るべき方向へ企業の活力を向けていくことが重要。不承認は未来の企業活動の在り方を決める1過程であると考えられる。日本の自然・生態系、それと深くつながる地域農業に禍根を残さぬように対応していただきたい。
参考
http://blogwatawata.blog.fc2.com/blog-date-20091118.html
http://blogwatawata.blog.fc2.com/blog-date-20091118.html
http://blogwatawata.blog.fc2.com/blog-date-20111012.html
http://blogwatawata.blog.fc2.com/blog-date-20110528.html
まとめ
「農作物が、どういう人と、どういう付き合いをしてきたのかというところから、醗酵食品が生み出されたり、それをどのようにして安定的に保存するかの知恵が生まれたり、建築も、衣食住すべて、私たちがどのようにすれば生きていけるか、というところから生まれてきたものだと思います。」
「植物は、生殖様式も集団の持つ意味も人間とは異なるので、人間に例えることが適切だとは思えません。生物種ごとに、生殖方法、花粉や種子、そして1個体の重みは全て異なり、雄性不稔個体が果たしている役割も異なり、その生物種にとって不稔個体が一定割合で存在することが必要な(=正常である)こともあると考えられる。不稔株を異常と判断して良いかどうかは、その作物種ごとに事情は異なるのです。」
「植物側に選択権がない遺伝子組み換えは品種改良とはいえない。」
これらの石綿さんの言葉からは、植物も生物の一つであり、その中の農作物、その品種にもそれぞれに個性があり、人がそれらとどう付き合うのか、よく考えないといけない、ということが伝わってくる。
関連記事
https://corezoprize.com/seed-14-gmo
https://corezoprize.com/seed-13-cell-fusion
https://corezoprize.com/seed-12-radiation
https://corezoprize.com/seed-11-radiation
COREZO (コレゾ)賞 事務局
初稿;2015.06.12.
編集更新;2015.06.12.
文責;平野龍平
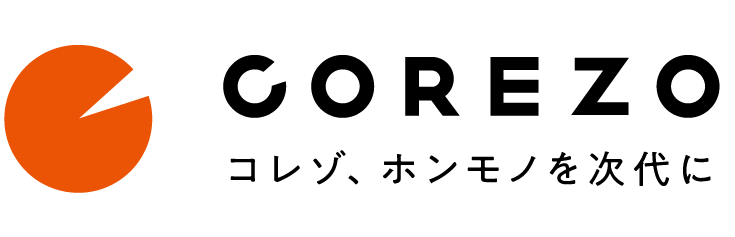
コメント