
目次
COREZOコレゾ「ひとつとして同じ自然環境はない 自然を敬い、あらゆる角度から観察して、身体で感じ、見極めて そのエネルギーを最大限に利用させていただく気持ちで 働く水車づくりを続ける 水車大工棟梁親子」賞

野瀬 秀拓(のせ ひでひろ)さん・翔平(しょうへい)さん/野瀬建設・水車大工
プロフィール
福岡県久留米市
野瀬建設・水車大工
水車建設・精米製粉設備工事
ジャンル
伝統文化・建築
水車大工
経歴・実績
2008年 馬場水車場の水車を、お父さまのの秀拓(ひでひろ)さんとともに再建
水車大工
野瀬 翔平(のせ しょうへい)さんは、福岡県久留米市で水車建設、修理改修を営む、野瀬建設・水車大工の二代目。
福岡県八女市の馬場 猛(ばば たけし)さんの水車場の現役バリバリで働く水車を拝見して、一気に興味を魅かれた。
水車と言うと、なんとなくそば屋を連想してしまうが、かつては我が国の豊富な水資源を利用して、精米や製粉に積極的に活用されていたが、明治中期以降、動力源が蒸気や電力に取って代わられ、実用に供される水車も水車大工も激減したそうだ。
確か2012年だったと思うが、馬場さんにご紹介頂き、その水車を再建された日本でも数少なくなった水車大工のおひとりである野瀬 秀拓(のせ ひでひろ)さんを訪ねた。
約束の時間に伺った住所に到着すると、恰幅のいい野瀬さんがにこやかに出迎えて下さった。
「どうぞこちらへ」とご案内頂き、向かった先は、「家庭料理さつき」という看板がかかっていて、玄関に小さな水車(ご子息の翔平さんが水車大工になって初めて作られた作品とのこと)があった。「私の事務所はこの二階で、一階は家内が家庭料理の店をしています。」とのことだった。


これが野瀬 翔平(のせ しょうへい)さんのお父さま、野瀬 秀拓(のせ ひでひろ)さんとの出会いだった。
その後、何度かCOREZO賞表彰式にもご出席いただいていたのだが、2025年度第15回の表彰式に水車大工を継がれているご子息の翔平(しょうへい)さんもお連れいただいたので、是非、取材させていただきたい、と云うことで、2025年3月に十数年ぶりに再訪させていただいた。
水車大工さんになったきっかけ
翔平(しょうへい)さんは子供の頃から、身近に水車があって、全く珍しいものでもなく、中、高の友人からは、その頃から水車大工になると聞いていたよ、と云われる程、ごく当たり前のように水車大工になり、以来、学生の頃のアルバイト時代を含めると20数年水車づくりに携わっておられる。
自分たちがつくったり、修復した水車で時間をかけて精米したお米が美味しいのはもちろん、米糠でさえ香りがよく、また、挽き立ての蕎麦粉で打ってもらった蕎麦は最高で、水車大工としての幸せを感じる瞬間だ、とおっしゃる。
水車づくり
元々あった久留米の作業場を事情があって撤収し、現在は、翔平(しょうへい)さんのご自宅のある大分と新たに借りた久留米の2箇所に作業場がある。
翔平(しょうへい)さんに、現在、請負っておられる和歌山県すさみと四国の現場の部材加工をしておられる久留米の作業場を案内していただいた。
水車に使われる材は、杉や檜の他、日本全国の地域によって異なるが、野瀬さんたちの地域では杉材を使い、水車に適しているのは、脂分が多く、目が詰まって、堅く、水に強い杉材で、中でも竹下製材所さんの杉材は、野瀬さんたちの水車づくりには欠かせない木材で、良い材を使えば20年は働き続ける水車がつくれるとおっしゃる。
実際、野瀬 秀拓(のせ ひでひろ)さん・翔平(しょうへい)さんがつくられた福岡県久留米市一ノ瀬親水公園の直径約6mの水車は、強い依頼があり、檜でつくったが、10年と持たず、傷んだそうだ。
この直径約6mの大型水車を稼働している水路は、ホタルの餌となるニナ貝を放流し、生育するためのホタル水路で、水量は少なく、流れも緩やかななのに、水しぶきを上げ豪快に回っているので、不思議に思って尋ねたところ、水車を稼働する水路の水量、流れの強さ、用途等々、様々な自然条件や作業効率を加味して羽根板や受け板の角度や枚数、大きさなどをあらゆる角度から、検討、計算し、自然エネルギーを最大限利用できるよう、設計、施工しているので、働く水車はどの水車を取っても同じものはなく、馬場水車場の水車は、設置場所を考慮して稼働させる流れを最大限に活かし、理想的な線香の粉挽き用として最適になるよう設計・施工しているとのこと。
今では、水車づくりにおいては、法律を遵守し、公共工事や文化財工事はすべて大学の教授や研究室、有識者の方々にご協力いただき、大型コンピューターでシュミレーションして、出力計算、データ化し、設計に反映しているそうだが、現在、携わっておられる江戸時代末期につくられた水車の修復・再生では、元の水車は、すっかり朽ち果ててしまっていても、先達たちの仕事を忠実に再現できるよう、つくり手が何を想い、どう考え、どうつくったのかを辿るように、解体すると、コンピューターなどなかった時代に規矩法(規矩術とも)を駆使して、設計、施工した先達たちの創意工夫、知恵や技が伝わってくる。水車大工の仕事には、それらをどう吸収してこれからの水車づくりに活かしていくかが大事だ、とおっしゃる。
規矩法とは、指矩(さしがね:曲尺)やコンパスを用いて垂木や隅木などの建築部材の形状を幾何学的に割り出し材木に墨付けする技術で、「規」はコンパス、「矩」は曲尺(かねじゃく=指矩)や定規を意味し、江戸時代に発展した。
これからの野瀬建設と水車づくり
翔平(しょうへい)さんは、親子の師弟関係は大変だが、ご自身のお子さんにも水車に興味を持って継いでくれたら嬉しい、とおっしゃる。
野瀬棟梁の水車づくりへの想いは、翔平(しょうへい)さんにもしっかり受け継がれている。
COREZOコレゾ「ひとつとして同じ自然環境はない 自然を敬い、あらゆる角度から観察して、身体で感じ、見極めて そのエネルギーを最大限に利用させていただく気持ちで 働く水車づくりを続ける 水車大工棟梁親子」である。
COREZO(コレゾ)賞 事務局
初稿;2025.07.
最終取材;2025.07.
編集更新;2025.07.
文責;平野 龍平
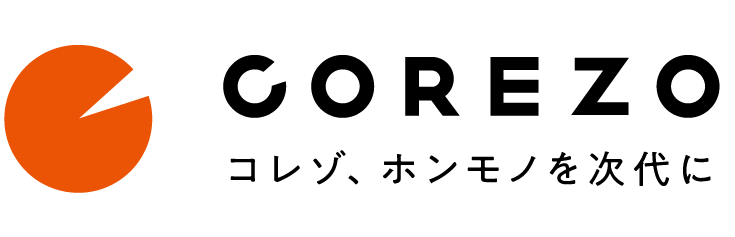
コメント