
目次
COREZOコレゾ 「脂分が多く、目が詰まって、硬く、水に強い水車に適した杉材を提供して、水車の伝統文化と水車大工の仕事を支え続ける林業家・製材所 三代目」 賞

竹下 修平(たけした しゅうへい)さん/竹下製材所 三代目

プロフィール
福岡県久留米市北野町
竹下製材所 三代目
竹下製材所
竹下 修平(たけした しゅうへい)さんは、福岡県久留米市北野町の竹下製材所 三代目である。
野瀬建設・水車大工の野瀬 秀拓(のせ ひでひろ)さん・翔平(しょうへい)さんのご紹介で訪問し、お話を伺った。
竹下製材所は、お祖父さまの代から杉の造林から製材まで一貫して営んでおられる。
製材所の敷地に置かれた木材は大きな材ばかりで、100年生を超えている材も多いと云う。
自然乾燥
山中で伐採した後、そのまま2〜3か月葉枯らし乾燥を行う。葉枯らし乾燥とは、伐採した木の枝葉をつけたまま一定期間山に放置し、葉から水分を蒸散させて乾燥させる方法で、木材の含水率が下がって山から運ぶ際に軽くなり、反りや割れが少なくなるなどのメリットがあり、カビや腐朽菌に対する抵抗力も高まると云われている。
その後、製材所に運び、さらに自然乾燥をした上で、製材し、桟積み乾燥を行う。木材と木材の間に桟木を挟んで積み重ね、風通しを良くすることで、天然乾燥を促進し、木材を均一に乾燥させ、反りやひび割れを防ぎ、製品としての品質も向上すると云われる。
今では乾燥機等を使って短時間で効率的に水分を抜く人工乾燥が主流だが、竹下製材所では、商品になるまで約半年から1年以上と時間はかかるが、木材への負担が少なく、自然な風合いを保てる昔ながらの自然乾燥を続けておられる。
水車に適した杉材
野瀬棟梁と竹下製材所さんとはお祖父さまの代から50年以上の付き合いで、山を観て木を選べ、と教えられたそうだ。
実際、土地が痩せて陽の当たりの悪い斜面で育った杉は、脂分が多く、目が詰まっていて堅く、水に強いため、水車に適しているそうだ。さらに建築に適した真っ直ぐな材より、水車の形状からも曲がり材の方が適しているので、山に生えている段階から目を付けて、購入することもあるが、製材すると思惑が外れることもあると云う。
そんなリスクを負っても水車に適した材にこだわるのは、水車は、良い材でつくれば20年は持つが、材によっては10年も持たないため、10年で作り替えれば水車大工の仕事は増えるが、手間賃が同じなら、20年仕事をする水車の方がお施主さんにはメリットがあるので、全ては、少しでも喜んでいただける仕事をしたいと云う思いからだとおっしゃる。
日本の林業・製材所のこれから
竹下さんは、物心がついた頃から、家業は継ぐものと思っておられて、ごく自然に継がれたそうだが、最も大変な作業は、夏の草刈りだとのこと。植樹して7〜8年、夏の間続くそうで、最近草刈りしたのは、2ha(20,000㎡)だったそうだ。
コロナ禍等の影響で2021年頃から始まった木材価格の高騰・国産材不足の現象はウッドショックと呼ばれ、2025年現在、徐々に沈静化しつつも価格は高止まり傾向が続いており、輸入材に押された国産材の価格の低迷はある程度改善されたが、将来に亘って利益が出る事業にしていかないとこの家業を次の世代に継げない、と竹下さん。
水車大工として水車に適した材を見極めてこられた野瀬棟梁は、山の手入れと自然乾燥を続けてこられた竹下製材所さんでしか手に入らないとおっしゃる。
水車大工さんと林業家・製材所さんがしっかり手を組んで、水車の伝統文化と水車づくりの技術を後世に残していただきたい。
COREZOコレゾ 「脂分が多く、目が詰まって、硬く、水に強い水車に適した杉材を提供して、水車の伝統文化と水車大工の仕事を支え続ける林業家・製材所 三代目」である。
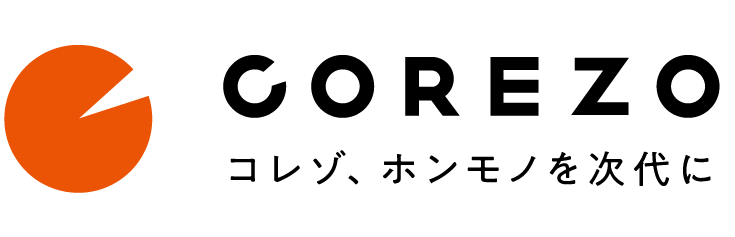
コメント