
目次
COREZOコレゾ「経営者として、幻の紀州棕櫚たわし復活を応援し、棕櫚たわし職人としても、お客様の声に耳を傾けて、使いやすいと喜んでいただけるよう工夫を重ね、他で真似できない高品質な商品をつくり続ける 二代目」賞

高田 英生(たかだ ひでお)さん/高田耕造商店/株式会社コーゾー 代表取締役/紀州棕櫚たわし

プロフィール
和歌山県海南市
株式会社コーゾー、高田耕造商店 二代目
沿革
1930年頃 高田要が自宅において棕櫚製品の加工を開始
1935年 本社工場建設
1948年 高田耕造が髙田耕造商店を設立、棕櫚たわしの製造を開始
1965年 靴洗い用たわし「チェリー」を発明、販売を開始
1968年 本社工場西棟を増築
1972年 県内で3工場稼働
1975年 3工場を集約し御坊工場建設
1977年 高田耕造商店代表に高田英生が就任
1990年 刺繍機を導入、マット類への刺繍事業開始
2004年 たわしストラップの販売を開始
2008年 株式会社コーゾー設立
2010年 紀州棕櫚山再生プロジェクト開始
2012年2月 国立新美術館ミュージアムショップ催事にて紀州野上谷産棕櫚束子が展示
2012年11月 にっぽんのたわし展開催
2012年12月 紀州野上谷産棕櫚束子 小が平成24年度日本民藝館展準入選を受賞
2013年2月 東京営業所を神田神保町に開設(現在は退室)
受賞歴
2017年 平成28年度プレミア和歌山推奨品 審査委員特別賞を受賞
2017年 2017年度ふるさと名品オブ・ザ・イヤー「自治体が勧めるまちの逸品」部門 最優秀賞を受賞(推薦者:和歌山県)
2017年 2017年度ふるさと名品オブ・ザ・イヤー「モノ部門」地方創生大賞を受賞(後援:内閣府、農水省、経産省)
動画 COREZOコレゾチャンネル
髙田 大輔(たかだ だいすけ)さん/紀州棕櫚たわし「髙田耕造商店」(その1)「今や、貴重となった国産棕櫚たわし」
髙田 大輔(たかだ だいすけ)さん/紀州棕櫚たわし「髙田耕造商店」(その2)「調理師を辞め、家業のたわしづくりの道へ」
髙田 大輔(たかだ だいすけ)さん/紀州棕櫚たわし「髙田耕造商店」(その3)「国産(紀州産)棕櫚(しゅろ)たわし復活への長い、長い道のり」
髙田 大輔(たかだ だいすけ)さん/紀州棕櫚たわし「髙田耕造商店」(その4)「雑誌に取り上げられたことが大きな転機に」
髙田 大輔(たかだ だいすけ)さん/紀州棕櫚たわし「髙田耕造商店」(その5)「紀州産棕櫚(しゅろ)の最高級たわしは価値がわかるお客様からだけの受注分しかつくれない理由」
高田耕造商店/紀州棕櫚たわし

髙田 英生(たかだ ひでお)さんは、高田耕造商店の二代目、ご長男の大輔さんの取材や棕櫚たわしづくりの動画撮影で、何度かお目に掛かっていて、筆者と同年代で、大浴場の濡れたバスマットがダメ、と云う共通点があり、その話で盛り上がったことがあるが、今回、改めてお話を伺った。
英生さんは、東京の金物問屋で2年間、商売の勉強をした後、和歌山に戻り、食器や食品を洗う道具を扱うご商売ということもあって、親戚の寿司店で1年間、それらの道具が飲食店でどのように使われているか、実際に働いて体験し、家業の高田耕造商店に入られた。
家業に入られた頃には、安価なスリランカ産のパームやしや化繊を使った「たわし」を近隣で150〜160軒ぐらいがつくっていたが、既に、原材料としての棕櫚は高価になっていたので、棕櫚たわしはつくられておらず、棕櫚自体、幼い頃に見た記憶が微かにある程度だったそうだ。
棕櫚たわしの復活
調理師になり、飲食店をするつもりだった長男の大輔さんが、高田耕造商店に入って、「海南は、棕櫚の産地が近くにあり、棕櫚産業で栄えてきたのに、どうして扱っていないのか、復活させたい」という話があり、「それもそうだ、その意気込みは大事にしたい」ということで、棕櫚を捌いて繊維にする機械がなかったので、つくれる人を探してつくってもらったり、先代の伝手も頼って、準備を始めた。
棕櫚のたわしを復活させようと始めたものの、当時、たわしは、キッチンシンクの中でも見せたくないような日陰モノの存在だったし、化繊のたわしやスポンジが主流になっていたので、たわしに目を向けてもらおうと、誰も真似できないであろう、日本一小さなたわしをつくって携帯ストラップにしたところ、それを「かわいい」と思って買ってくれたおかげで、ヒットして、多少なりともたわしの認知度は上がったと思う。

棕櫚たわしを主力にする方向に舵を切ったものの、すぐに売上げにはつながらず、それまで主力だった百均向けのパームやしや合成樹脂の商品も徐々に原価が上がって採算が合わなくなったので、撤退することなり、並行して営んでいた縫製の事業でなんとか凌いだ、と英生さん。
たわしを巻く技術

英生さんは、高田耕造商店の代表だが、棕櫚たわし職人として生産現場も率いておられ、高田耕造商店の手仕事での商品生産には、なくてはならない存在だ。
たわしを巻く技術は、化繊を巻くのも、パームやしを巻くのも、棕櫚も同じで、化繊は太さが一定なので機械化できるが、元々、高田耕造商店は、大量生産には不向きな小ロットの特殊な「たわし」の受注が多く、化繊たわしも手巻き生産しておられたので、長年、扱っていなかった棕櫚たわしも問題なくつくれたそうだ。
大きさ、形状他を工夫して、お客様が使いやすい、特殊な商品をつくるのが得意でずっとやってきたから、注文が入るし、お客様が喜んでくださるから、仕事をしていても楽しい。定番の同じ商品なら1日3〜400本は巻けるが、特殊な商品は、太さも長さも違い、20種類も30種類もあるし、都度、機械の調整も必要なので、数は巻けない、と英生さん。
棕櫚たわしが売れるきっかけ
たわしをつくっている立場からすると、たわしは洗う道具であって、そんな雑誌に掲載されるとは考えもしなかったが、新幹線のグリーン車の車内誌に「身体を洗うたわし」が掲載された直後から問い合わせや注文が殺到し、潮目が変わった、と英生さん。
棕櫚たわしの価格
棕櫚たわしを復活したものの、売上げに結びつかない状態が続き、採算が取れる価格で売るより、まず、数を売ろうという安易な考えで、価格を下げたため、約10年間、価格を上げられない苦しい時期を味わったが、コロナ禍が終わってから、価格を徐々に上げて、ようやく利益率を改善できる方向になった。
「たわし」は飛ぶように売れる商品ではない、と云うのが根本にあるので、売れるから高くできるものではなく、棕櫚は高価な原材料だと認知されてきたので、適正価格で販売できるようになっただけで、それでも棕櫚自体がないから高価になってしまう、と大輔さん。
紀州産棕櫚(シュロ)
和歌山県海南市は、全国シェアでも高い割合を占める「家庭日用品産業」が地場産業として栄えているが、古くから棕櫚栽培が盛んで、その樹皮を原材料に棕櫚のたわしやほうき、縄などの棕櫚製品づくりがルーツとなって発展してきた。昭和30(1955)年代から、徐々に安価な外国産パームやしや化学繊維に取って代わられるようになり、昭和40(1965)年代には、海南だけでなく、国内の棕櫚産業は、ほとんど途絶えてしまった結果、棕櫚皮を採取する職人の仕事はなくなり、上質な棕櫚の消失も進んだ。
紀州棕櫚山再生プロジェクト

高田耕造商店は、海南市の家庭日用品産業のルーツを守りたい、棕櫚産業をもう一度復活させたいという想いから、2010年、「紀州棕櫚山再生プロジェクト」を開始し、何十年も放置され荒れ果ててしまった棕櫚山をもう一度再生させようと、大輔さんが師匠として仰ぐ、野上谷の棕櫚皮採取職人さんの協力もあって、コツコツと活動を続け、良質な棕櫚を確保できるようになるまで約5年の歳月を要した。
「紀州野上谷」は、和歌山県海南市または隣接する地域(野上・紀美野町あたり)の山あいの地域で、古くより「紀州産棕櫚(しゅろ)」などの伝統的な素材・工芸品の産地として知られる。
紀州産棕櫚の現状
2018〜9年頃から、大輔さんが棕櫚山に入るようになったが、それまで協力してくださっていた棕櫚の師匠をはじめ、職人さんたちはさらに高齢になり、今では、棕櫚の管理と採取作業をするのは、大輔さん一人となった。
この先、大輔さんも歳をとるので、いつまで続けられるかという問題があり、若い職人を育てることができればいいのだが、危険が伴う高所作業なので、それも難しい。さらに、苗を植えても鹿の食害に遭って全滅し、若い木が1本もないので、日に日に採れる量は限られてきている。
申し訳ないが、現状、価格に転嫁する他は無く、やれるところまでやるつもりだが、あとはその時の状況に応じて最善の策を考えるしかない、と大輔さん。
高田耕造商店の今後
英生さん
長男の大輔は、主に卸や大規模店舗の営業担当しているので、販売側の意見や要望を、次男は、手取り足取り教えなくても、見よう見まねで「たわし」が巻けたので、百貨店の催事等で実演販売していて、実際に使われる消費者の皆さんの意見や要望を聞いてくる。それを取り入れて商品にしたり改良するのが、新商品を考えるのが好きな私の仕事で、役割分担ができていて、兄弟喧嘩もなく、上手く行ってると思う。
手仕事なので量産はできないが、他ではつくれない、お客様が使いやすいと喜んでくださる商品なら、少々、値がはっても買ってくださるし、有難いことに高田耕造商店の商品の評判は聞こえてくるので、信頼してくださるお客様を大事にして、この先も小ロット、多品目で続けていきたい。
自分が辞めるとたわしをつくれるのは2〜3人になってしまうので、元気な限り、生涯たわし職人としてやり続けたい、と英生さん。
大輔さん
昔、当たりだったら海外旅行、ハズレだったら「たわし」、と云うようなTV番組があったが、最近、ある番組の担当者から、高田耕造商店の最高級品である「金のたわし(時価)」を景品に使いたいので購入させて欲しい、と云う依頼があって、たまたま、予備に在庫していたものがあったので、販売させてもらったが、紀州産棕櫚たわしを復活したことで、ハズレだった「たわし」が当たりになったのは、嬉しかった。

やりたいことをやりたいようにやってきて、失敗もあったけど、それも糧になっていて、その商品を本当に欲しいお客様にダイレクトにお届けするのが理想なので、その方向で進めている。
今後、拡大できるかと云うと、人材を育てる投資ができるかどうかだが、年々、厳しくなる労基遵守の問題もあり、今の事業を続ける限り、難しいので、いろんなケースを想定している。その時の状況に応じて対処するしかないし、規模を拡大しなくても、成り立つビジネスにしていきたい、大輔さん。
まとめ
高田耕造商店さんにお邪魔すると、大輔さんのお父様の高田 英生さん、お母様の高田 弘実(たかだ ひろみ)さんもいつも笑顔で出迎えてくださり、帰り際には、従業員の皆さんも総出で見送ってくださるので、恐縮するが、小規模な企業といえど、こんなアットホームで温かい企業にはなかなかお目に掛かれない。
英生さんは、東京での修行時代に同じビルに入っていた金融機関にお勤めだった弘実さんと出会われたそうで、弘実さんは、その経験も活かして、高田耕造商店の経理を担当しておられ、1円の誤差も許さず、ピッタリ合うまできっちり仕事をされるそうだ。
家族経営であってもそれぞれの得意なところを活かして役割分担し、役目をしっかり果たしておられるからこそ、棕櫚たわしを復活して、現在、主力の事業に育てることができたのだろう。
今後、紀州産棕櫚皮の採取を続けるのには厳しい現状もあるようだが、 高田耕造商店さんは、一つづつ問題を解決し、その時代、時代に合わせて、進化を続けていかれると思う。
COREZOコレゾ「経営者として、幻の紀州棕櫚たわし復活を応援し、棕櫚たわし職人としても、お客様の声に耳を傾けて、使いやすいと喜んでいただけるよう工夫を重ね、他で真似できない高品質な商品をつくり続ける 二代目」である。
以下は、大輔さんのご紹介記事より
紀州棕櫚たわし
束子(たわし)の原材料が何かご存じだろうか?
かつては、棕櫚(シュロ・ワシュロ)でつくられていたが、現在、私たちが束子と思い込んでいるのは、大半が海外産のパームヤシ製品で、棕櫚であったとしても全て中国産らしい。
堀田雅湖さんから、日本(紀州)産の棕櫚でつくったホンモノの束子を日本で唯一、製造販売している「髙田耕造商店」というメーカーがある、と聞き、天王寺から特急くろしおに乗って約1時間、和歌山県海南市にご一緒した。

和歌山県海南市
白浜や勝浦には何度も訪れているが、途中の和歌山県海南市は、初めてである。
和歌山県海南市は、スポンジやブラシ、マットなど家庭日用品の一大生産地だそうだ。それは原料となる良質の棕櫚が近隣で採れたため、たわし、箒、縄などの棕櫚加工品の製造が盛んになり、その後、時代の流れと共にプラスチックや化学繊維を原料とする製品にシフトしていくが、今でも、炊事、洗濯、トイレ、風呂など水回り品におけるシェアは全国の8割強を占め、中小含め企業数は100近くに上り、中には、大都市圏に販路を持ち、全国の大手流通に商品供給しているメーカーもあるそうだ。
近年、安価な輸入品に押され厳しい状況が続いたが、アイデア商品や高付加価値商品開発で差別化を図り、新たな活路を見出しているとのことだ。
高田
耕造商店の三代目
株式会社コーゾー、髙田耕造商店の三代目、商品開発と営業担当の髙田大輔さんは、「だって、束子づくりの仕事って、カッコええですか?そりゃもう、カッコ悪いでしょ?だから、家業を継ぐ気なんて全くありませんでしたよ。」と、調理師専門学校を卒業後、大阪のイタリアンレストランで調理師として働いておられた。
働いていたレストランを辞め、独立して自身の店舗をオープンするつもりで、実家に戻って来たが、思うような店舗がすぐには見つからず、いつの間にか、家業を手伝っていた、と云う。
棕櫚(シュロ)
棕櫚(シュロ)はヤシ科の常緑高木で、その樹皮は腐りにくく、柔軟性に富み、古くから繊維を取って縄やほうきなどに加工されてきた。冒頭に記したように、国内では、和歌山県が産地で、特に北部の海南市と紀美野町にまたがる「野上谷」一帯の棕櫚は良質とされていたそうだ。
所謂、「亀の子たわし」は、100年ほど前に誕生し、紀州の棕櫚たわしも人気を博したが、やがて安価な輸入のパームヤシや中国産棕櫚の製品に押され、昭和40(1965)年代を境に衰退し、今や、化学繊維の束子やスポンジに取って代わられてしまった。
髙田耕造商店も地元の同業他社と同様、プラスチックや化学繊維を原料とする製品の製造販売が主力になっていたが、その傍らで、細々と輸入した棕櫚を使ったたわしもつくっていた。
10数年前、髙田耕造商店の代表で父親の英生(ひでお)さんが、極小サイズのたわしストラップを思い付き、商品を開発していた。大輔さんはそのたわしを持って高野山の土産物店等に売り込み、好評だったのだが、店主から、「あんたとこの地元の山には、棕櫚がそれこそヤマほどあるのに、なんで中国産なんか使っているの?」と、問われ、大輔さんのスイッチが入った。
「プラスチックや化学繊維製品を廃棄するには、高額な処分費が必要で、地球にも負荷をかけているのでは?、メーカーとして、毎日使うものだからこそ、使う人にも、ものにも、環境にもやさしくありたい、自社の製品の寿命が尽きるまで責任を持たねばならないのではないか」と思うようになっていた時期とも重なった、と云う。
紀州棕櫚山再生プロジェクト
早速、家業のルーツでもある地元の棕櫚のことを調べ始めたが、既に棕櫚山は40年以上放置されて荒れ放題、往時のことを知る人を探し出すのにもひと苦労した。やっと見つけ出した当時の棕櫚採り職人さんも高齢になっておられて、説得するのにももうひと苦労…。最後は、「紀州の棕櫚産業を復活させたい!」と云う、熱意だけで押し切り、職人さんたちと山に入り、手入れすることから始めたそうだ。
棕櫚たわし

「ウチの束子を触ってみて下さい。」

柔らかく、実に心地良い触感で、そこらの百均で売っている束子とは全く別モノである。
「世間では、束子は固いものというイメージがすっかり定着してしまいました。それって、かつて、柔らかく優しい手触りの棕櫚たわしを作ってきた私たちが、大量生産、大量消費に走ってしまい、その価値をしっかりとお客様に伝えてこなかったことが原因です。」
「棕櫚皮の繊維は腐りにくく、伸縮性に富み、1本の棕櫚の木からは1年に10枚ほどの棕櫚皮が採取出来ますが、採取された棕櫚皮はその部位や向きによって繊維の質がまちまちで、たわし製作にちょうど良い太さの皮は全体の僅か3分の1程です。」

「さらに、棕櫚皮の繊維が細いところはブチブチ切れ、逆に太い部分は堅いので、その中間部分の15%程度しか使えません。棕櫚皮10枚でたわし1個できるかどうかなんですが、残りの繊維の太い部分は束ねて『ささら』に、細い部分は縄などに加工するので、全てを使い切り、決して無駄にはしません。」

棕櫚たわしのつくり方
「この厳選された棕櫚皮を毛捌き機に掛けて繊維状に加工します。この工程で棕櫚の繊維はさらに半分ほどに減ってしまいますが、こうして均一な太さの繊維を集めることで手に取った時の柔らかさにつながります。」

「当社で使っている毛捌き機は、たわし職人が少なくなった現在では製造されていないため、当時の機械屋さんを探しだし、在庫部品を寄せ集めて作ってもらったとても貴重な最後の一台です。」

「この棕櫚繊維をひと掴みし、そのままたわし巻き機にセットされた針金に挟み、針金の間に均一になるように広げ、さらに、入念に棕櫚が均一であることを確認した上で、一気に巻き上げます。この辺りの加減はまさに職人の領域で、繊維が繊細な国産の棕櫚たわしを巻ける職人は、父の英生だけだと思います。」

「今や、日本の棕櫚でつくっているのは、ウチだけだと思いますよ。紀州産の棕櫚で束子をつくっているのは髙田耕造商店だけだ、と公言していますが、今まで一度もクレームを頂いたことがないので、ハハハハ。」

この紀州産棕櫚束子(大)が、3,240 円(税込・2017年取材当時)。百均で3個入りが30セット(30×3)買える値段であるが、この品質と手間を高いと感じるか、安いと感じるか、人としての感性や品格を問われているような気がする。

この大輔さんがアイデアマンで、人のボディ用束子や孫の手の他、究極の肌触りを活かした商品を次々に開発しておられる。
紀州産からだ用棕櫚たわし
ちなみに、筆者は、2025年現在、予約商品となっている、13,200円(税1,200円)の紀州産からだ用棕櫚たわし(焼き檜柄)を入手して、入浴時に愛用しているが、お肌がとってもデリケートなワタクシでもすこぶる使い心地が良く、欧州で大人気と云うのが納得できる「たわし」の概念を覆す逸品だ。

以下、2025年7月取材の追加記事
棕櫚たわしで勝負する大きな後押し
高田大輔さんと東京會舘の鈴木前料理長との関係
高田大輔さんが、2018年の「黄綬褒章」に続き、今年(2025年)、「旭日双光章」を受賞された東京會舘日本料理顧問(前料理長)の鈴木 直登(すずき なおと)さんと懇意にされているのは存じていたが、日本料理界の重鎮とたわし屋さんの三代目が親しいご関係になられた経緯を伺う機会を得た。
高田大輔さんが家業に入り、「紀州産棕櫚たわし」を復活した頃、最高の「たわし」だから、和歌山県でも最高のところで販売したい、と考え、県内最高峰の観光施設である「道の駅ごまさんスカイタワー」を指定管理で運営している龍神村の地域おこし団体「龍神は~と」の代表も務めておられる季楽里龍神の小川さださんを訪ねた。
当時、鈴木前料理長が季楽里龍神の料理監修をしておられることを知り、和歌山県海南市藤白にある藤白(ふじしろ)神社は、代々、藤白鈴木氏が代々神職を務め、鈴木姓の発祥の地とされることから、一面識もなかったが、この神社のお守りと「紀州産棕櫚たわし」の中でも最高のものを鈴木前料理長に送ったそうだ。
きっとお忙しかったのだろう、お返事がなかったが、今後、棕櫚たわしに注力するにあたって、視察と社員旅行も兼ね、一大マーケットである東京に行くことになり、食事をするにも右も左もわからなかったので、東京會舘の鈴木前料理長を頼って、地元、和歌山県海南市の飲食相場感覚での予算を伝え、予約した。
鈴木前料理長からは、東京都心の飲食の相場を丁寧に教えてもらったが、当日、東京會舘がどのような施設かも知らないまま、ラフな服装で訪れて、食べたことも見たこともない素晴らしいお料理とお酒もたくさんいただき、その食事中、送った棕櫚たわしに興味を持たれた鈴木前料理長から色々質問をされて、たわしの話題で盛り上がったそうだ。その時のお会計金額はよく覚えておられないとのことで、そう云うことにしておきたいと思う。
鈴木前料理長からの後押し
帰り際、「東京に来ることがあったら連絡してきなさい」とおっしゃったのを鵜呑みにして、行く度に連絡し、都度、お目に掛かるようになり、その当時、棕櫚たわしと並行してプラスチックや化学繊維を原料とする製品の製造も続けていて、「プラスチックや化学繊維製品を廃棄するには、高額な処分費が必要で、地球にも負荷をかけているのでは?、メーカーとして、毎日使うものだからこそ、使う人にも、ものにも、環境にもやさしくありたい、自社の製品の寿命が尽きるまで責任を持たねばならないのではないか」と云う大輔さんが抱える悩み、葛藤も打ち明けるようになっていた。
ある日の別れ際に、鈴木前料理長から「キミの仕事は、土の上か下か?」、「は?」、「上は自然で、下は化石だ」、「どっちもやっています」、「それじゃダメだ」と云われたことが気になって、戻って、聞き直したところ、「土から上のものは生まれる、土から下のものは死んだもの、二度と生き返らないものだから、土から上の仕事をしなさい」と。
当時、自然素材の棕櫚たわしは売上の1割弱、その他を化学繊維製品が占めていたが、大輔さんには、土の上と下の仕事を両立できなかったので、「土から上」の棕櫚たわし仕事に専念する決心をし、東京に出て勝負する大きな後押しになった、と大輔さん。
前料理長がどう思っていただいているかわからないが、大輔さんにとっては、東京の父親のような存在で、頼まれれば出張の交通機関や宿泊施設の手配もするし、和歌山に来られる際には、クルマでの送迎をはじめ、フルアテンドをしておられるそうだ。
棕櫚たわし事業の行方
東京での営業活動
東京での住居が決まって、東京ビックサイトでのギフトショウの日程に合わせて上京し、出店したところ、世間で有名なありとあらゆる大企業の担当者から名刺をいただいた。したこともなかったお礼メールを送ると、次々に打ち合わせのアポイントメントが決まり、数カ月先まで埋まる程で、やっぱり東京ってスゲ〜っと、連日、サンプルを持って駆け巡ったが、現実はそんな甘いものではなく、1件も商談成立しなかった。
棕櫚たわしは珍しく、棕櫚山再生の背景も理解してくださり、興味は持ってくれるが、サンプルだけで商談成立のための武器は何も用意しておらず、アフターフォローもせず、やりっ放しの営業で終わってしまっていた。
それまで主力だった化学繊維製品の仕事は徐々に縮小していたし、取引先も決まらないまま、累損だけが増えていき、金融機関からの融資も厳しくなっていく中、大輔さんの想いに賛同した金融機関の担当者が、上司に掛け合ってくれて、なんとか融資を受けることができ、もう一度勝負を賭ける決意を固めた。
棕櫚たわしが注目される転機
丁度その頃、新幹線グリーン車の車内誌の取材が入り、それまで、TV、ラジオ、新聞、雑誌他、多くのメディア取材を受けてきて、売り上げにつながったことは1度もなかったのに、数ヶ月後、車内に置かれた途端、新幹線グリーン車の客層のニーズと合ったのか、問い合わせと購入希望の電話が鳴り止まなくなる程の反響があった。
売上としては、大きなものではなかったが、これが実績となって、認知度が上がり、問屋や販売店、通販会社にも注目されて、売上が上がる好循環を掴むきっかけとなった。それは、売上も上がらない状況で、今後、東京での展開をやめるか、どうするかでご両親が上京し、和歌山に戻るタイミングでのことだった。
2025年現在の高田耕造商店の取り組み
棕櫚たわしを使う文化を伝えること
2025年現在、高田耕造商店がやるべきことは、たわしを売ることではなく、たわしで磨く行為や文化を伝えることで、Webサイトやカタログ、情報誌である「たわし通信」はもちろん、催事やイベントを通じて、取り組んでいる。


フライパンの数より「たわし」の数が増えることはないし、まな板の数より「たわし」の数が増えることもない。「たわし」を買ったから良いフライパンを買おう、まな板を買おう、土のついた野菜を買おうとはならない。
それまでは、フライパン、まな板、曲げわっぱの弁当箱他と同列に並んで販売していたが、「たわし」は、それらを洗ったり手入れする時の選択肢のひとつに過ぎず、「たわし」だけを先に販売しようとしていたこと自体が間違っていたことに気づいた。
それぞれ相性があって、フライパンに合うたわし、まな板に合うたわしがある。一歩下がって、自社の「たわし」と相性の良い道具を使ってもらうことが先で、まずは、良いフライパンを使いましょう、木のまな板を使ってらっしゃるなら、この「たわし」がベストですよ、という販売方法に変わっていった、と大輔さん。
面倒か手間か
「たわし」は、使ってもらってナンボのものなのだが、 環境に良いと云われて買ったけど、使っていないと云う方もいらっしゃって、それは、必要もないのに買わせてしまったことになり、用途や利点をしっかり理解してもらって、納得して買っていただいて、使っていただけるようにすることが販売する側の務め。
そもそも「たわし」で洗うのが面倒と感じる人には売れないし、無理に買ってもらっても必要がなければ使ってもらえないから、お互いに不幸になるだけだが、道具を使う手間と思って、手入れに一手間かける人には売れるし、そんな人には同じ感覚の人たちのコミュニティがあるので、口コミで良さも拡がる、と大輔さん。
まとめ
営業の鉄則を改めて教えていただいた。販売する側も使い手のお客様の考え方や用途をしっかり理解して、必要な人に必要な場面で使ってもらえるように販売することで双方満足できれば、棕櫚たわしを使う文化は次の世代に続いていくだろう。
COREZOコレゾ「使う人やものにも、環境にもやさしくありたい、幻の紀州棕櫚たわしを復活し、今や最高級品は数年待ち、棕櫚山を守り、職人の手仕事の技を伝承して、棕櫚たわしを使う文化を伝え続ける 三代目」である。
最終取材;2025年7月
初版;2017年11月
最終編集;2025年8月
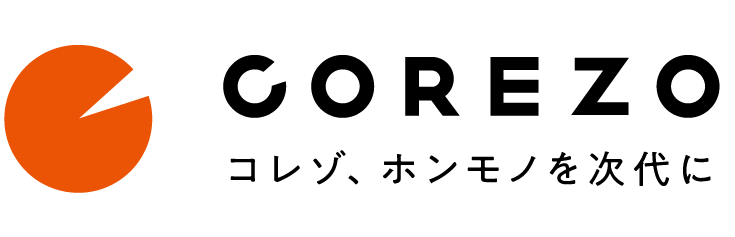
コメント