
目次
- 畦地 履正(あぜち りしょう)さん
- 四万十町にある「道の駅四万十とおわ」
- 昼だけの営業で10回転以上って⁉︎
- 「ここしかないもの」がコンセプト
- 「天然うなぎどんぶり」が、なんと2500円(取材当時)!
- 旧十和村は、限界集落がゼロのワケ
- 「地域住民株式会社」とは?
- デザイナー梅原真さんとの出会い
- とにかく怒られまくった…
- 後に「四万十ドラマ」となる3セクに採用される
- モノを売るには自分らの志や考え方を表明せよ
- 浴用芳香剤「四万十ひのき風呂」の商品化
- 「しまんと新聞ばっぐ」を開発
- 「地栗(じぐり)」というネーミング
- 毎年20%の配当を出す茶生産組合
- 地域の「考え方」に「共感」すると「交流」が起こる
- 四万十ドラマが蓄えたノウハウを惜しみなく伝授するワケ
- 若い世代の人たちが帰って来れる場所、地域に
- まとめ
畦地 履正(あぜち りしょう)さん
https://corezoprize.com/risho-azechi
四万十町にある「道の駅四万十とおわ」
「道の駅四万十とおわ」は、四万十市ではなく四万十町にあり、高知龍馬空港から車で約2時間、首都圏からも関西圏からも時間がかかる不便な場所にある。訪れたのは平日でしかも雨天であったが、かなりの台数の車が停まっていた。その半数ぐらいが他府県と「わ」ナンバーである。道の駅に併設されている「とおわ食堂」は、何と、満席で「待ち」が出ていたのである。
昼だけの営業で10回転以上って⁉︎
待ち客がおられて驚いた旨を伝えると、
「ハハハハ、それ、ウチでは普通でね。この食堂は50席程なんですが、ゴールデンウイークやお盆には、1日、5〜600人のお客様にご利用頂きますよ。」
ー ひぇ〜、夜は営業してないんでしょ?お昼だけで10回転以上ですか?スゴいですね、大儲けですね。実は、以前、四万十の宿泊施設に泊まって、冷えきった養殖の冷凍アユを食べさせられて、四万十のイメージが大きくグレードダウンしたのですが、ここのメニューは、川のものはどれも天然物、食べたくなるメニューばかりで、注文してからゴリがあるのに気づいて、大失敗ですよ。
「ハハハハ、今、ゴリは旬で、美味しいですよ。ウチはね、地元のもんしか出さんのですよ。」
畦地 履正(あぜち りしょう)さんは株式会社四万十ドラマの代表取締役。その一風変わった社名は、四万十川から新しい物語・ドラマをつくっていこう思いから名付けられたという。
同社は高知県西部の四万十川中流域旧3町村(大正町・十和村・西土佐村)が出資する第三セクターとして、1994年に設立され、1999年には独立採算を実現し、2005年には、民営化を果たして、 (株)四万十ドラマとなった。
道の駅「四万十とおわ」は、同社が指定管理者となり、2007年7月に開業した。地元で道の駅の構想が持ち上がり、事前調査をしたところ、店舗が面する国道381号線の通行量は、1日1000台未満で、明らかに経営は成り立たないという結果が出て、9割の人がうまくいかないと予想した。
行政をはじめ、だれも運営に手を挙げない中、畦地さんは、四万十川の「ここにしかないもの」なら売れるという確信が有り、3年間で黒字にするという事業計画を立て、同社の役員会を説得した。
「卸元に納品するだけでは利益は取れないし、地域の情報発信できる場を持つことができ、都会に出て行った若者に『帰って来たい』と思わせる核にもなる。9割がうまくいかないと思っても、1割の賛成者がいるのだから、やってみる価値がある。誰もやらないことをやらなければ、活路も見出せない。我々にとって最後のチャンスかもしれない。」と、反骨精神に火が点いたそうだ。
「ここしかないもの」がコンセプト
コンセプトは「ここしかないもの」である。綿密な戦略を練り、オープンまでの2年をかけてオリジナル商品20数点を開発した。四万十川の景観にもこだわった。計画・設計段階から、立地や建物の配置、設計にもどんどん意見を申し入れ、一切、妥協はしなかったそうだ。
道の駅事業部には、地元だけでなく、Iターンの人材も採用し、外からの視点も取り入れた。そして、オープン初日には、当初予想の5倍の約5000人の来場者があり、周辺は、2〜3キロの渋滞になった。
年間6万人前後という事前調査に対して、初年度12万人、次年度15万人。その後も安全・安心な商品にこだわり、生産者の顔が見えるイベント等を継続して仕掛けることで、順調に入場者数、売上ともに伸ばし、人口3,000人程の寒村の何もなかった田んぼを累計80万人の集客と8億円の売上(2012年3月)を生み出す場所に変えた。
「ここ十和は高知市内からでも2時間も掛かります。せっかく来て頂いたのだから、『ここしかない』景色、買物、食事を楽しんで頂ける滞留型の道の駅を目指してやってきました。」と、畦地さん。
畦地さんから頂いた「ドラマのドラマ」という小冊子の表紙と裏表紙の裏のページには、コレゾ四万十の写真とともに、「はるばるようこそ」、「ここしかないもの」のコピーが踊っている。これに畦地さんと四万十ドラマの思いが凝縮されているように思う。
「天然うなぎどんぶり」が、なんと2500円(取材当時)!
道の駅「四万十とおわ」には、「とおわ市場」、「とおわ食堂」、「ファストフード」店がある。
「とおわ市」は、地元の産品にこだわった直販場で、有機野菜を中心とする農産物、きのこ、鮎や川エビなど、地元でとれたもの、それを加工したものしか扱わないので、とれなかった時は、提供しないそうだ。
周辺地域全体でISO14001取得の取組みをしておられ、農産物には生産者名は勿論、化学合成農薬の使用回数、化学合成肥料の使用の有無まで記載、表示されている。
その他、風呂に置くだけでヒノキの香りが漂う「四万十ひのき風呂」、旧十和村(現四万十町)の特産である栗を使った「四万十栗の渋皮煮」、独特の香りを誇る香り米「十和錦」、地元のショウガを使った「ジンジャーシロップ」、四万十の茶葉を使った「しまんと緑茶」など、「四万十とおわ」にしかないオリジナルのヒット商品が数十品目にものぼる。
「とおわ食堂」では、「とおわ市場」で扱う地元の産品をふんだんに使い、四万十の季節と素材を味わえる。十和で採れたしいたけのタタキや四万十川の青さのりの天ぷらが入った「とおわかご膳」、四万十町産の豚を使った「四万十とおわポーク丼」など、ここで提供する料理は四万十流域の食材を使ったものが中心だ。
テラス席からはコレゾ四万十という風景が広がっていて、階段を降りて、河川敷にも出ることができる。
旧十和村は、限界集落がゼロのワケ
「限界集落って言葉はご存知でしょ?当時、高知大の教授だった大野晃先生が初めて使われたのですけど、既に過疎化が進んでいた同じ高知県の大豊町やここ旧十和村もその先生の実地調査対象になっていました。1950年代に、木材需要が高まり、国が補助金を出して、農地から杉林への転作奨励し、各自治体で数字を競わせて杉を植えさせたんですね。4〜50年は収入が得られないので、若者は集落を出て行き、定年後の収入源にアテにしていた杉は思うようにお金にならず、放置林が増え、土地が痩せて山崩れが頻発するようになったんですよ。」と、畦地さん。
「限界集落」は、1991年に社会学者の大野晃先生が初めて提唱した概念で、林業の衰退と再建をテーマに研究、実地調査を重ねるうちに、山村の人口減と高齢化、それにより、手入れの行き届かなくなった杉・桧等の人工林の荒廃、さらには集落そのものの消滅が進みつつある実態には、「過疎」という言葉ではそぐわないと感じ、集落の自治、集会、生活道路の管理、冠婚葬祭の実地など共同体としての機能維持が「限界」に達している65歳以上が人口比で50%以上の状態を「限界集落」と表現したそうだ。
「高知市にも近くて便利なはずの大豊町は、限界集落が増え続けていますが、ここ旧十和村は、交通の便では、はるかに不便なのに、限界集落はゼロで、全国的にも注目されています。何故かというと、広葉樹対針葉樹の比率が大豊町では3対7に対し、旧十和村では6対4なんですよ。40年も換金できないものを植えても仕方ないだろう、と賢明な判断をした地元の先人達が、『山の複合型経営』という概念で、むしろ広葉樹を植えて、椎茸やお茶、栗の産地としてこの半世紀やってきました。それが今では使える資源になって、地元の特産品となり、Uターンしてくる若者も増えているからだといわれています。」
「地域住民株式会社」とは?
その一番の立役者が、四万十中流域の地域に密着した「地域住民株式会社」、四万十ドラマである。道の駅「四万十とおわ」の運営の他、オリジナル商品の開発や物品販売、観光交流事業といったコミュニティビジネスを手がけておられる。
その成功への道のりを探って行きたい。
「ファストフード」店でも、「ホットなっば(椎茸のたたきのホットドッグ)」、「ひがしやまソフト(干し芋のペーストの上にソフトクリームをのっけたスイーツ)等の気になるメニューが並んでいる。
「なば」=「椎茸」、「ひがしやま」=「干し芋」だそうなのだが、地元の言葉を使っているところから地域のDNA、愛着が感じられ、「えっ、何それ?」「どんな味やろ?」という消費者のコミュニケーションのスイッチが入る仕掛けが仕組まれている。先に、梅原さんにお会いして、お話を伺っていたので、梅原さんのデザインコンセプトに通じるものを感じてしまう。
デザイナー梅原真さんとの出会い
「今があるのは人との出会いが全てです。特に、梅原さんは、師匠であり、恩人であり、足を向けて寝れませんよ。」と、畦地さん。
当時、旧十和村に移り住んでおられたデザイナーの梅原さんに出会い、その考え方、生きざまから大きな影響を受け、折々にアイデアや助言をもらいながら、自ら考え、行動し、思いを実現してこられたという。
畦地さんは、高校球児で、エースピッチャーとして高知県下でその名を轟かせていたが、ご自身のケガによって甲子園出場の夢は叶わなかったそうだ。高校卒業後、高知市内の通信関連企業で働いた後、1987年、23歳の時に、生まれ故郷の十和村に戻り、地元の十川農協に転職された。
一方、梅原さんは、1989年1月、旧十和村役場からの依頼を受けた同村の総合振興計画「十和ものさし」を作成し、「自然が大事、人が大事、やる気が大事」、都会を真似するのではなく、「地域独自のモノサシ」を持とうと、「考え方」、「ビジョン」を示した。
当時も今も、行政の総合振興計画としては、独創的かつ画期的で、もっと評価されるべき内容であったと思うが、その数ヶ月後の村長選挙の結果、現職が落選し、新村長が誕生した。
梅原さんは、「十和ものさし」を通じて、「沈下橋を観光資源として活かそう。」、「土木工事ではなく、特産の栗を活かした産業をおこそう。」と、訴え続けたが、「高知の都会もんに何がわかる?よそ者がつべこべいうな。」と、一蹴され、不便な沈下橋こそが、十和の独自性だと確信していた梅原さんは、すぐさま、旧十和村の中でもより不便な、四万十川沿いに通る国道381号から沈下橋を渡った向こう側に移住することを決意。小さな集落に引っ越し、日々の暮らしで沈下橋を渡ることで、自ら行動に出ておられた。
とにかく怒られまくった…
そして、1990年、畦地さんと梅原さんの運命の糸がつながる。
畦地さんが参加したある地域づくりの会合で、始まる前から終始、えらい剣幕で怒りまくっていたその人こそ、梅原さんだった。あまりの迫力に圧倒された。「この人、一体、何者?なんでそんなに怒ってるの?」と怪訝に思ったが、高知県内の数々のヒット商品の仕掛人であることはウワサに聞いていて、何者かを確かめるためにも、会って話をしてみたくなり、同じ旧十和村に住んでおられるのを突き止めて、梅原さんを訪ねた。
「地域活性化のために、成功しているところを見習って、同じようなものを売りたい・・・。」と、自分の思いを話そうとした途端、「今、ここにあるいいものを見ていない。地元のもんが地元のもんを大切にせんとどうするんじゃ!」と、怒声が飛んできた。
以来、梅原さんの言ってることが気になり、度々、足を運ぶようになったが、とにかく怒られまくった。次第にその怒りの真意が理解できるようになり、地域を見直すきっかけになったという。
旧十和村はお茶の産地でもあったが、ブランド力がなかったため、静岡茶の原料として静岡に出荷されていた。何とか十和村のお茶として売れないかと思っていた。
実は、四国全体が、お茶の産地であるが、ブランド力のないところはどこも同じように静岡や宇治に出荷している。「静岡茶は静岡産ではないの?」、「宇治茶は宇治産ではないの?」という疑問が沸くが、詳しくは、茶生産農家、片木明さんのご紹介ページをご覧頂きたい。
そこで、梅原さんにもアドバイスをもらいながら、消費者を集めて、茶摘み体験を含めた「四万十のほとり新茶を楽しむ会」というイベントを開催したところ、大成功を収めたことができた。それからは、さらに梅原さんとの距離が縮まり、次第に、農協で自分ができることの限界を感じ始め、1994年に農協を退職した。
後に「四万十ドラマ」となる3セクに採用される
その数カ月後に、地元の旧北幡3町村(西土佐村、十和村、大正町)が出資した第三セクター(1年後に「四万十ドラマ」と名付けられた)の職員募集があり、全国公募で40人の応募者の中から、たった1名の職員に採用された。畦地さんに与えられた猶予期間は3年間、3町村から補助金の出る3年のうちに事業を軌道に乗せ、その翌年からは黒字体質にすることが求められていた。
これまでの経緯から、梅原さんを頼りにしようと協力を求めるが、ハッキリ、キッパリ、断られてしまう。しかし、自らが考え、行動するしかないことは既にわかっていたので、「地元に誰がいて何があるのか。それを知らなければ、地域おこしも何もない」と、西土佐村、十和村、大正町にある地域資源の調査を開始した。
モノを売るには自分らの志や考え方を表明せよ
2年目になって、「調査もええけど、いつまでも国と同じことしてたらアカンやろ?モノを売るには自分らの志や考え方を表明せなアカン。」と、梅原さんから、「水」をテーマにした本を作らないかと提案された。
「最後の清流」と賞される地元の「四万十川」も川としての豊かさ、機能を失いつつある中、その恵みを受けて生きてきた四万十川流域から場所を提供して、大切な「水」について語ることで、「真に大切なこと」が見えてくるのではないかと、ほとんど面識もない「みず」知らずの、この人に書いて欲しいと思った40人以上の識者に原稿依頼の手紙を送った。
予算のない四万十ドラマが用意した原稿料は自分たちで獲る四万十の天然アユ3年分だった。
最後の清流四万十川というイメージは、東京のメディアが取材して、編集、発信されてきたことに対するアンチテーゼでもあったが、「四万十川から人の生き方、本質を考えたい」というメッセージを伝えた。
浴用芳香剤「四万十ひのき風呂」の商品化
1997年、「ここらは植林したヒノキが多いけど、材木の需要がないから、山も荒れている。売れへん、売れへんゆうてるだけやったらアカンやんか、ヒノキを木材でなく『香り』ととらえたら、新しい価値が生まれる。」という梅原さんからのアドバイスから、浴用芳香剤、「四万十ひのき風呂」を商品化した。地元の製材所から出るヒノキの端材に焼き印を押し、天然のヒノキオイルを染み込ませ、ユニットバスが香りだけでもヒノキ風呂に変身するという商品だ。これが地元銀行のノベルティ商品として採用され、大ヒットした。
捨てるのはモッタイナイから始まって、捨てられるだけだった木片に焼き印を押して、香りをつけるというローテクの加工作業を地元が請負うことで、雇用と新たな価値をつくり、さらに売れることで、間伐材の需要も高まって、森林保全につながるという環境循環型ビジネスを生み出した。
「しまんと新聞ばっぐ」を開発
「しまんと新聞ばっぐ」も、旧十和村に住んでいた梅原さんが、集落の一斉清掃で、川沿いの木々に絡まって取れないビニールのレジ袋を見て、「川を汚さんように四万十川流域の商品は新聞紙で包もうや。」と言い出したのがきっかけとなって、畦地さんや四万十ドラマの職員さんたちが、カタチにした。
素材は地元の話題が載った地元紙しか使わないというこだわりがあったり、売上の一部は森林保全にも役立てていて、ニューヨークの美術館や高級ブランド店のレイアウトにも使われたことがあるという。同バックは国内だけでなく海外からも注文が舞い込むヒット商品で、顧客の「自分で作りたい」という要望も受け、バッグの作り方と見本セットの販売や、作り方を教えられるインストラクター育成教室も開き、人的交流にも一役かっている。
リサイクル品である古新聞を買い物バッグとして再利用しようというコンセプトは、四万十ドラマのイメージにピッタリで、その名声を高めた。さらには、東日本大震災後、「被災者と社会をつなぐパイプをつくろう」と、被災者と支援者は対等という思いを込めた、「ツクルシゴトツクル」というキャッチフレーズの「しまんと新聞ばっぐ東北プロジェクト」につながっている。
「地栗(じぐり)」というネーミング
旧十和村が限界集落ゼロの理由は先述したが、かつて、四万十川流域は全国有数の栗の産地であった。旧十和町でも最盛期には年間500tも出荷していたが、中国産の安い栗に押されて、採算が合わないため、近年は50tにまで落ち込み、栗林は荒れ放題になっていたという。
栗林の再生を図るため、「大粒で甘みが豊富」な四万十栗を「地栗(じぐり)」というネーミングで「味の良さ」のイメージを前面に打ち出して店頭に並べると、手に取って買ってくれる人が増え、「甘くて、美味しい」と評判になり、関連のスイーツも売れ、売上がどんどん伸び、見捨てられていた地元の宝に再び光が当たった。
毎年20%の配当を出す茶生産組合
地元のお茶を自分たちで売りたいと、2002年に四万十流域の茶葉だけを使った「しまんと緑茶」、「しまんとほうじ茶」を商品化。2008年には、40年前まで、地元で盛んにつくられていた和紅茶も復活させ、ペットボトル飲料や関連商品がヒット商品になり、その提携している「広井茶生産組合」が、毎年20%の配当を出しているというのだ。
当初は、地域の農産物を売るゾと意気込んで東京に乗り込んだものの、さっぱり売れなかったり、イベントでの販売で、確保していた数量が足りなくなって、急遽、他地域から調達したのがバレてしまい、地元の生産者からソッポを向かれたり、散々だったらしいが、着実に実績を積み重ね、地域住民からの絶大な信頼も得るようになり、2005年には、3セクからの完全民営化を実現した。何と、地元住民202名が出資して、株主となり、畦地さんを代表取締役とする「じゅうみん株式会社」に姿を変えたのである
地域の「考え方」に「共感」すると「交流」が起こる
畦地さんのfacebookを拝見すると、オトモダチは2,500人を超える勢いで、全国を駆け巡りながら、各地での取組み等々の情報を発信しておられ、どなたからのコメントにもできる限り返事を返しておられるようだ。「どんだけのエネルギーと行動力や⁉︎」と敬服する。
最近、首都圏での新たな販売チャンネルも開拓されたようで、全て、業者任せにせず、積極的に都市部の商談会にも参加して、自らの力で開発、開拓されている。興味を持ったバイヤーには、是非、四万十に来て欲しいと伝えるそうだ。
四万十ドラマが生み出している商品は、その背景、生産者や加工者や地域の物語・風景まで消費者に買って頂いているので、販売者にも実際に生産現場に足を運び、現場を見て、生産者と話をしてもらえば、商品の売り方も変わる。本気で売りたい人と組まないと商品は売れないし、地域の「考え方」を理解してもらって、「共感」が生まれないと、「交流」も起こらないと考えておられる。
「四万十から発信した商品を購入した人が、ここに来てもらえるような仕組みを構築し、交流を広げていきたい」と、「四万十また旅プロジェクト」という体験観光プログラムも立ち上げられた。ボランティアではないプロのガイドを育成して、他団体と連携して、伝統うなぎ漁、新聞バッグ作り他、四万十の日常生活、生産現場等をありのまま体験してもらい、地域の人々との交流から、繰り返し訪れてもらうことで、四万十の環境につながっていく旅にしたいという。
四万十ドラマが蓄えたノウハウを惜しみなく伝授するワケ
また、インターンシップの受入れや、四万十ドラマが培ったノウハウを講義だけでなく、体験プログラムを通して各地で共有して頂こうと研修制度にも積極的に取り組み、視察の受入れをしておられる観光地域は少なくないが、研修ビジネスにまで発展させておられる。
さらに、2008年度から、経済産業省の「コミュニティビジネス移転支援事業」を引き受け、四万十ドラマのノウハウをほかの地域に伝え始めておられ、他地域のキーパーソンに商品開発の手法や売り出し方など、四万十ドラマが蓄えたノウハウを惜しみなく伝授しておられる。
せっかく培ったノウハウを簡単に教えてしまっていいのかと心配になるが、ノウハウは、「その地域」、「その人」、「その考え方」でできているので、すぐに流用できたり、真似をしたからといって効果が上がるものではなく、自分たちなりに消化して、自分たちの地域に合うようアレンジして、さらに進化させなければ役に立たないという。
「確かに、他の地域に自分たちの経験、ノウハウを伝えていますが、それと同時に、相手の地域の皆さんから教えてもらうことも多いですよ。」と、畦地さん。
ノウハウを出し惜しみせずにオープンにして、既にノウハウのある複数の地域・団体同士が連携すれば、さらに高度なノウハウを生み出せるはずと、地域・団体間の提携、ネットワークづくりも積極的に進めておられる。はるかに次元が高いのである。
四万十方式の考え方、ドラマの全国展開が始まっている。
若い世代の人たちが帰って来れる場所、地域に
梅原真さん流のデザインコンセプト(単なる外観のデザインではない。梅原真さんの紹介記事に詳細)がベースにあると思うが、自ら考え、行動することで、四万十独自の考え方に進化させ、見事に地域全体をデザインしておられる。四万十ドラマを「地域の総合商社」とか「地域プロデュース企業」と呼ぶ人もいるようだが、「地域総合デザインセンター」の方がふさわしいような気がする。
「これからの目標ですか?ここを若い世代の人たちが帰って来れる場所、地域にしたいですね。四万十ドラマも当初、私1人で始めましたが、おかげさまで、今ではパートさんも入れて20名以上になっています。ここに集まってきた人たちと一緒に新たな仕事を創り、産業を創って、雇用を生み出して、四万十の風景を守って行きたいですね。」と、畦地さん。
まとめ
地域振興の最先端が高知の四万十の片田舎にあった。地方の地域から日本全体を元気にするカギはここにある。
関連記事
https://corezoprize.com/risho-azechi
https://corezoprize.com/design-skills
https://corezoprize.com/makoto-umebara
https://corezoprize.com/nobuko-ichohara
COREZO(コレゾ)賞 事務局
初稿;2015.06.24.
最終更新;2015.06.24.
文責;平野 龍平
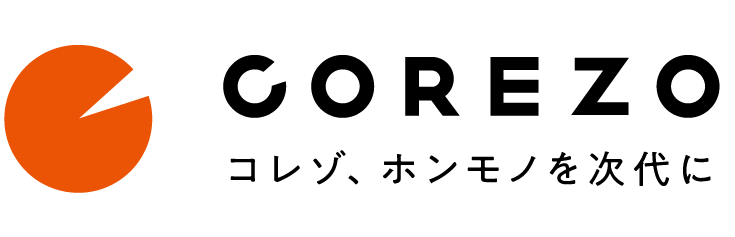
コメント