
目次
COREZOコレゾ 「美しきその色に衝撃を受けて、藍の世界に飛び込み、時代と地域の環境に適合した『藍染めの文化』とは何かを追求し、新たな取組みに挑戦し続ける 藍師・染師」 賞

渡邉 健太(わたなべ けんた)さん/藍師・染師 株式会社WATANABE’S 代表取締役

プロフィール
徳島県板野郡上板町
株式会社WATANABE’S 代表取締役
藍師・染師
1986年、山形県生まれ。阿波藍の産地として知られる徳島県上板町で暮らし、藍の栽培、染料となる蒅(すくも)造り、染色、製作を一貫して行っている。日本の伝統技法 ’’天然灰汁発酵建て’’からなる藍色は、深みのある冴えた色合いが美しく、色移りしにくいという特徴を持つ。その藍を「暮らしに寄り添う色」として、人々の生活に馴染んでいくものづくりを考え、国内外で幅広く活動を行っている。
2021年、NHK大河ドラマ「青天を衝け」にて藍染・蒅造りを指導。
株式会社WATANABE’SWebサイトより
株式会社WATANABE’S
帆前掛け製造・販売の有限会社エニシング 代表取締役社長の西村 和弘(にしむら かずひろ) さんからのご紹介で訪問し、お話を伺った。
美しきその色に衝撃を受けて
渡邉さんは、都内で貿易会社に勤務していた頃に興味のあった藍染め体験をして、その色に言葉にできない震えるような感動をしたことから、13年前、藍染めを志したが、当時、ファストファッション全盛期で藍の伝統産業自体、先が無いと云われていて、学べる先や受け入れ先がなかった。そんな時、総務省の地域おこし協力隊の制度が始まり、丁度運良く、「蒅(すくも)」づくりの後継者育成と藍染めのPRでこの上板町の地域おこし協力隊の募集があり、学びたかった製藍所が研修先だったので、是非!と応募して、見事、採用され、2012年着任した。
株式会社WATANABE’S設立
3年間の任期中、藍栽培から、「蒅(すくも)」づくり、藍染など藍の伝統産業の技術を学び、同じ地域おこし協力隊の仲間と2人で独立して活動していたが、突き詰めていくうちにやりたいことができたので、そこを離れ、2018年、この株式会社WATANABE’Sを立ち上げた。
藍染め
酸化と還元
草木染め等に使われる多くの植物染料は、煮出すことによって色素を抽出し、染料を繊維に定着させる媒染剤で発色して、染色するが、藍の色素は、「インディゴ」と呼ばれる水に溶けない不溶性の物質なので、色素を還元させる環境を整えた溶液で水溶性の物質「ロイコインディゴ」に変化させ、これがアルカリ性の溶液に溶けると黄色のソルブルインディゴ(インディゴホワイト)の溶液=藍染液となり、繊維に染色できるようになる。
「ロイコインディゴ」が染み込んだ繊維を空気中にさらすと、「ロイコインディゴ」が酸化して、「インディゴ」に戻り、繊維に色素が定着する。
藍染めは、このような酸化と還元という化学反応を利用している。
藍染の歴史
インドでは5,400年前の染色槽跡が発見され、エジプトではツタンカーメンのミイラが藍染めされた布と共に埋葬されていた。現時点での最古の藍染めは、6,200年前のペルーの遺跡から見つかった藍染めされた糸を織り込んだ織物だが、ペルーから世界に広まったのではなく、世界中のそれぞれの地域で独自の藍染め技術が生まれ、確立されていったと云われている。
世界各地の藍染めは、同じ酸化と還元という化学反応を利用しているが、それぞれ原料が異なり、様々な染色方法が生まれ、進化、発展してきた。
世界の藍染文化
「藍」と呼ばれる植物は、全く違う種類の植物として、世界各地に100種類以上あり、日本で「藍」と云えば、タデ科の「タデ藍」だが、世界的に有名な「藍」はマメ科で、ヨーロッパではアブラナ科、沖縄ではキツネタマゴ科の「藍」もある。
これらの藍はその地域で生育していたり、栽培しやすい種が使われ、東南アジア、中国南部、インドなどの低緯度の地域では、温暖な気候もあって年中収穫可能な藍が多く、発酵環境にも適していることから、沈殿法と呼ばれる葉から直接色素を抽出する方法で沈殿藍をつくり、染色液の管理も野外で行うところが多く、染色液を各家庭でつくって自家で染色する文化が定着しており、これが世界的には多数派の藍染文化の形となっている。
因みに、石油や石炭を原料に化学合成された「合成藍」の色素であるインディゴは植物から抽出した「天然藍」と全く同じものだそうだ。
日本の藍染文化
日本では四季があり、タデ藍も年に1度、夏の時期にしか収穫できないため、還元のための発酵には温度管理が必要で、管理方法も容易ではなく、日本独自の藍染文化である「スクモ法」と呼ばれる染料の製造方法と「蒅(すくも)」という染料が生まれた。
スクモ法
スクモ法とは、収穫した藍の葉を乾燥し、約120日かけて水と空気のみで発酵させ、堆肥化(有機物を、微生物の力を使って分解させ、成分的に安定化するまで腐熟させること)した染料の保存方法で、その染料を「蒅(すくも)」と呼ぶ。
飛鳥時代に中国からタデ藍が伝わり、始まったとされる日本の藍染めは、室町時代に入ってさらに進化を遂げ、染色液中で還元発酵させる前に、染料をつくる段階で発酵させる二段構えの形を取るようになった。その理由は定かではないが、次のような利点がある。
保存面;「蒅(すくも)」にすることで、染料が半永久的に保存できるようになった。
輸送面;乾燥葉を発酵、堆肥化することで量が減り、輸送が容易になった。
還元発酵面;「蒅(すくも)」の中で発酵菌を選別し、胞子として定着させておくことができるため、染色液の発酵が容易になった。
日本では、このスクモ法によって、年中、どこでも染料を確保できるようになり、さらに、「蒅(すくも)」の中の発酵菌が染色液の発酵を容易にしてくれるため、室内の土中に染色槽を埋めて温度管理を行えば、染色も年中可能になった。
「藍師」と「染師」
「蒅(すくも)」づくりと染色液の管理には、それぞれ異なる技術と経験が必要となり、生産効率を上げるため、「蒅(すくも)」をつくる職人「藍師」と染色する職人「染師」に分業・専門化し、日本の藍染め文化は発展した。
徳島は、藍染の原料となる「蒅(すくも )」の一大生産地
江戸時代、徳島は、藍染の原料となる「蒅(すくも )」の一大生産地として栄えた。その背景には、温暖な気候に加え、日本三大暴れ川として知られる吉野川は、毎年のように台風による大雨で氾濫し、災害をもたらした一方で、上流から運ばれた養分豊富な土砂で肥沃な土地が育まれ、生育に多くの水と肥料を必要とするタデ藍栽培には適していた。さらに阿波藩が藍の栽培を奨励したことから、江戸時代後期には、日本一の「蒅(すくも )」生産地として、生産量、品質共に評価されるようになった。
最盛期(明治時代後期)には、徳島の平地面積の20%近くが近くが藍畑になり、多くの「藍師」が「蒅(すくも )」づくりをしていたが、安価で大量生産、均一品質が求められるようになり、合成藍や化学薬品での藍染めが台頭したことで、蒅の需要は激減し、「藍師」と呼ばれる家業も減少していった。
近年、時流が大きく変化し、環境負荷を考慮した持続可能なものづくりが求められるようになって、天然藍での藍染めは、原材料や規模感でも時代に適しており、その追い風の影響もあって、全国的に染師が増えている反面、藍師はほとんど増えておらず、供給が全く追い付いていないのが現状。
WATANABE’S 渡邉さんの取組み
「蒅(すくも)」づくりからの藍染め
渡邉さんは藍染め体験をして、その色に感動したことから、この道に入られ、その色を良くするにはどうすれば良いかを突き詰めていくと、「蒅(すくも)」の原料の藍を育てる土にまで行き着いたそうだ。WATANABE’Sさんでは、原料の藍を藍色の質は、乾燥葉を発酵させてつくられる「蒅(すくも)」、さらに「蒅(すくも)」をつくる藍の葉の一葉一葉に影響され、藍色の全責任を自分たちで背負いたいと云う想いから、良質な土づくりといきいきと育つ環境を整えることを重視して、より上質な色素をより多く含む藍、その藍が本来生まれもった「らしさ」を存分に有する藍を育てることから取り組んでおられる。
良質な土づくりとサステナブルな循環
原料の藍を育てる土は、かつては毎年のように氾濫する吉野川がもたらしていたが、護岸整備され、氾濫することも無くなったため、毎年、土づくりを行い、土地の肥沃さを維持することが重要になる。
WATANABE’Sさんでは、親交の深い養豚場でつくられる完熟堆肥を藍畑に使用している。形が悪く商品として出荷できない農作物や給食センターで出た残渣を養豚の飼料として活用し、その糞尿を堆肥化した。発酵によってうまれる完熟堆肥は、冬でも湯気が立ち昇るほど有効微生物を含む上質なもので、それを地元の農地に還元するサステナブルな循環が、糞尿廃棄・悪臭問題の解決や農家の化学肥料コストの削減を実現し、WATANABE’Sさんの藍畑の土も豊かになって、結果として生産高も増えている。
「蒅(すくも)」づくり
3月にハウスで種蒔き・育苗、4月に植え付け、梅雨前に定植(苗床から畑への植替)、7〜8月に刈り取り、藍色の色素は葉のみにしかないため、葉と茎を選別(藍粉成し)し、葉の乾燥・保存。
10月から寝床(発酵させる土間作業場)に乾燥葉を広げ、水を打ち、満遍なくかき混ぜていくと、自然に発酵が始まり(寝せ込み)、その後は週に1度、葉の山を切り崩して適宜水を打ち、均一に発酵するよう、中心部と外側を入れ替え、満遍なく空気に触れるようかき混ぜる(切り返し)。「蒅(すくも)」づくりの発酵は熱発酵で、ピーク時、中心部の温度は70℃にもなり、寝床全体には朦々とした湯気、むせ返るほど強い匂いが立ち込め、想像以上の時間と労力を要する。
翌年1月末ごろに発酵が安定し、俵詰めの日を迎えるが、この時点で染色液の仕込みに使用すると還元発酵が不安定になりがちなので、俵詰めの後、さらに約半年間、熟成させる。
このように1年以上掛かる大変な仕事だが、現在の蒅の取引価格では全く採算に合わず、「蒅(すくも)」づくりから染めまで一貫してやることで採算が取れるようになるそうだ。
「藍師」と「染師」の両立
WATANABE’Sさんは、より良い色の追求と現代の社会環境(藍師不足)や工房の立地環境(「蒅(すくも)」の一大産地)に合わせて、分業・専門化した「藍師」と「染師」の両方を社業として営んでおられる。1年間、「蒅(すくも)」づくりのための藍の栽培、農業をベースとして、空いた時間に染色、製品づくりと一貫した生産活動をしておられるところは少なかったが、最近では、同じような取り組みをしておられるところもあるそうだ。
需要が増加しているのに蒅の取引価格が上がらないのは、「蒅(すくも)」をつくる「藍師」と「染師」の分業の歴史が原因の一つで、一次産業としての「蒅(すくも)」づくりを採算が取れるようにしないと藍産業自体が成り立たなくなる、と渡邉さんは危惧する。
渡邉さんは、藍師と染師のどちらもしているから、見えてくることで、江戸時代、「蒅(すくも)」の生産で栄えたが、藍を栽培していた小作人はきっと搾取されていて、今も一次産業の状況は変わっていないので、仕組み自体を考えないと、藍産業はこの先厳しい、とおっしゃる中で、WATANABE’Sさんのように藍師と染師を両立して、「蒅(すくも)」づくりから染め、製品づくりまで一貫して行うのは一つの解法なのだろう。
天然灰汁発酵建て
WATANABE’Sさんの藍建て(染色液=藍染液をつくること)は、木炭から取った高アルカリの「灰汁」、アルカリ分とミネラル豊富な「貝灰」、菌の活動を助ける糖分として使用する「麩(フスマ・小麦の糠)」を用いて行い、それらは、天然の材料であることから「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる伝統的な手法である。
蒅(すくも)藍建てキット
自社で栽培した藍、生産した「蒅(すくも)」は、全量、自社の染めに使ってきたが、余分につくれるようになってきたので、染め屋さんではなく、その向こうの藍染に興味のある方や藍染めのファンの方々を対象に藍染の染色液を発酵させてつくるところから知っていただきたい、体験していただきたい、と云う想いから、染色液を仕込むノウハウを記したマニュアル付きのキットとして開発し、近日中に販売予定だとのこと。
これまで灰汁発酵建は経験と感覚でやってきた職人仕事だったが、WATANABE’Sさんでは、自社で藍建てしたデータを蓄積しておられ、それをベースに藍建てする菌がどのように動いてどう云う作用をしているか、その発酵の仕組みをしっかり理解すれば、どう対処すれば良いかも分かり、論理的にノウハウとして確立することができてきた、とおっしゃる。
実際、小学生の息子さんに説明書の通りやってもらったところ、ちゃんと藍建てできたそうだ。
藍が好きな一般の方でも、いろんな染め屋さんに行くと、それぞれ色の違いを感じると思うが、染色液の匂いや染めた後の匂いの違い、同じレシピで藍建てしても菌が違うと同じ色にならないとか、その工房の色の特徴も藍建てするともっとよく分かるので、選択の幅が広がるし、興味も深まる。
酒造りと同じで、仕込む場所が違えば、同じ蒅を使って、同じレシピでも、温度、湿度、そこに居る菌も環境も違うので、出来上がりの風味が違うように、藍の色にも違いが出るので、発酵のおもしろさも知ってもらえる。
自社のノウハウをオープンにすることでユーザーからのデータが増えることも期待でき、経験値、感覚値を照らし合わせていくことで、より精度も上がるし、ビックデータ化できれば価値も上がる、と渡邉さん。
今後の取り組み
年々、やればやるほど、わからないことがたくさん増えていって、やりたいことが山積みの状態で、調べたり、実験したり、少しづつでも解決し、理解を深めている日々の中、無我夢中でやっているうちに、自然や藍の発酵菌等から色をいただいて生業にさせてもらっていることから、自然の営みやその本質的な部分はとても不思議で、自分の意思と云うよりもその中で生かされているような感覚になり、そんな中から美しい色も生まれていて、一筋縄では行かない発酵のおもしろさを感じている。
「蒅(すくも)藍建てキット」で藍建てや染色の奥の深さを知ってもらった後は、同じく発酵を使った「蒅(すくも)づくり」を体験できるプロジェクトをやりたい。蒅(すくも)藍建てキットもだが、ユーザーと一緒にやることで、裾野が広がり、自社以外の条件、環境ではどんな変化が起きるのか、そんな情報も知りたいし、自分たちだけで実験するより多くの情報、データが集まるだろうから、おもしろいことになりそう、と渡邉さん。
布から染めるより、布を織る前の糸から糸から染める方が糸の芯までしっかり染まり、発色が力強く、深く、色落ちもし難いので、糸から染めて布にする工程は、有限会社エニシングさんに依頼しているそうで、エニシングさんの欧州の販売ルートを活用される日も近そうだ。
渡邉さんが藍の世界に飛び込んだ当時は、衰退産業と云われていたが、エシカル、循環型社会、SDGs…、というな言葉が世の中に出てきて、年々、天然染料での染色が注目される時流になり、藍染めも同様に需要が増えてきた。藍染めは盛り上がっているが、年々、藍染に必要な「蒅(すくも)」づくりの担い手は高齢化し、新規参入も少なく、全国的に生産量が低下していると云う問題もある。
現在、自社での「蒅(すくも)」の生産量は年間20〜25俵(蒅1俵=約56kg)だが、近隣の若手農家さんと手を組みながら栽培を拡大し、100俵ぐらいまで増やしたいそうだ。
渡邉さんは、今の時代と地域の環境に適合した「藍染めの文化」とは何かを追求し続けて、土づくりから取組み、「藍師」と「染師」の両立や「蒅(すくも)藍建てキット」の販売等、従来、藍の世界には無かった取り組みに挑戦されてきた。これまでも同じ業界で色々トライしてきた方もおられたと思うが、時代が合わなくて上手くいかなかった方が多かったのではないか、今は、時代の後押しもあって、ネットやSNSで情報発信ができるし、閉鎖的な産業でも情報がオープンになってくると、異端者が出てきてもできてしまうし、自社で藍師と染師の両方やれば、横槍も入らないので、自分のやりたいことができている、と渡邉さん。
伝統は革新の連続と云われるが、渡邉さんは、伝統技法を継承し、藍の奥深さを追求して、より良い製品づくりに取組みながら、時代の変化に対応し、新たな社会的価値と消費者価値を創り続けておられる。
これからも藍の伝統文化を守り、革新して、産業としてさらに発展させていかれるだろう。
COREZOコレゾ 「美しきその色に衝撃を受けて、藍の世界に飛び込み、時代と地域の環境に適合した『藍染めの文化』とは何かを追求し、新たな取組みに挑戦し続ける藍師・染師」である。
※本文は、渡邉 健太(わたなべ けんた)さんへの取材とご提供いただいた株式会社WATANABW’Sさんのパンフレット資料の内容を元に、編集、構成させていただいた。
取材;2024年10月
初稿;2024年11月
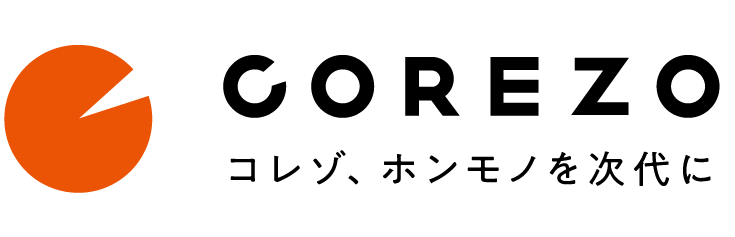
コメント