
目次
COREZOコレゾ 「牛の幸せとみんなの幸せを願い、今や希少となった『山地周年放牧』を続け、豊かな自然環境の中、のびのびと健康な乳牛を育て、『やさしい牛乳』と乳製品を届ける酪農家親子」 賞

上芝 卓司(うえしば たくじ)さん/尚子(なおこ)さん/雄大(ゆうた)さん/農事組合法人 黒沢牧場

プロフィール
和歌山県海南市
上芝 卓司(うえしば たくじ)さん
農事組合法人 黒沢牧場 代表理事
上芝 尚子(うえしば なおこ)さん
農事組合法人 黒沢牧場 外販部
上芝 雄大(うえしば ゆうた)さん
農事組合法人 黒沢牧場 四代目
COREZOコレゾチャンネル
農事組合法人黒沢牧場
季楽里龍神の小川さださんから、和歌山県海南市に全国的にも珍しい、「山地・周年放牧」という、牛を一年中野外で放牧する牧場があり、そちらの牛乳はもちろん、ソフトクリームやアイスクリームがめっちゃ美味しい、と伺い、同じ海南市の高田耕造商店、高田大輔さんにお連れいただいた。
大輔さんによると、近所にあり、とても気持ちの良い高原なので、家族でよく訪れておられると云う。
黒沢牧場の 3代目代表の上芝 卓司(うえしば たくじ)さんは、牛のお世話他で忙しく、手が離せないとのことで、奥様で外販部の上芝 尚子(うえしば なおこ)さんとご子息の上芝 雄大(うえしば ゆうた)さんがご対応くださった。
黒沢牧場の立地

黒沢牧場は、標高約500mの山地(高原)にあり、牧草地面積は約30ha、観光用施設、ハーフゴルフ他のレジャー施設の「黒沢ハイランド」、そして未開墾地も併せると100haの広さがあり、観光牧場として、放牧されている牛たちを見ることができるだけでなく、バーベキューコーナーやドッグランが併設され、ゴルフ、アーチェリーも楽しめる。
黒沢牧場の歴史
林業やその他の事業を営んでいたお祖父様が、ご自身が手掛ける最後の事業として、山林を開墾し、酪農および観光牧場として黒沢牧場を創業された。
1968年、農事組合法人となった。
1980年頃、牧場内で生乳を使ったオリジナルソフトクリームの販売を開始。
1994年、和歌山マリーナシティで開催された「JAPAN EXPO世界リゾート博」に出品したオリジナルソフトクリームが好評で、以降、ソフトクリームミックスの卸販売を開始。
2005年、アイスクリームを開発・販売開始し、商品の多品目化を図る。
2008年、楽天市場への出店開始。ギフト販売や百貨店販売など販路を拡大。
2011年、「6次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の認定を受ける。
2016年、工場新設および直売店「ミルク工房」をオープンして、加工・直販を強化し、愛犬と訪れる方も多かったため、ドッグランも開設。
周年放牧

1年を通して通年で家畜を放牧する飼育方法で、特に牛(乳牛や肉牛)に対して使われることが多く、特徴は、通常の放牧(春〜秋だけ)とは異なり、冬も含めて牛を屋外で飼育し続けるところ。
AIで調べてみると以下のような特徴があるとのこと
① 自然な飼育環境 牛が常に外で自由に動き回れるため、ストレスが少なく、健康的に育つ
② 牛の運動量が多い 常に歩き回るため、筋肉質で脂肪が少ない、あるいは濃厚なミルクになることも
③ 餌は主に牧草 自然の草を中心に食べる(冬は補助飼料を与えることもある)
④ 設備が簡素 牛舎に閉じ込めず、山や原野などの自然環境を活用するため建築コストが抑えられることもある
⑤ 管理が難しい 雪や悪天候の時期でも放牧するため、放牧地の整備・健康管理が重要になる
⑥ アニマルウェルフェアに適合 動物福祉の観点からも評価される飼育法
酪農全体の0.01%未満
黒沢牧場では、牛を一年中放牧しているが、近畿地方で、「山地での周年放牧」を行っている牧場は他にないそうだ。
雄大さんによると、かつて、自然放牧も多く行われていたが、山林を開墾するのが大変で、放牧地にするまでに時間がかかり、放牧地の広さから管理の手間も多く、とにかく、投資効率が悪いので、本来、牛が食べない穀物などの飼料を与え、牛舎で運動をさせず、効率重視で搾乳量を増やす飼育、酪農経営に変化していき、今や、酪農全体の0.01%未満となっている。
AIで検索してみても、全国の乳用牛酪農家約10,000戸弱(2024年)の中で、周年放牧をしているのは、黒沢牧場を含めて数軒という結果だった。
「牛に胃が4つあるのは、草を食べて生きていけるように、進化して、1回胃に入れて、反芻して、噛み砕いて、胃に入れて、反芻して、を繰り返して、草の繊維をアンモニア、窒素、たんぱく質なんかに変えて体内に吸収する構造になっているのに、効率よく搾乳するために、穀物やサプリメントと称して油脂を与えると、胃なんて4つも要らなくて、一気に腸まで届くから、胃は100%働かないし、牛の胃の中に住んで消化を助ける微生物も減るので、胃の中に熱を持って、嫌な臭いの排泄物が出る。牛の胃は大きな発酵槽みたいなもんだから、仔牛の時からできるだけ良質の牧草(繊維質)食べさせて胃の中の微生物も一緒に育てないといけない。それに、搾乳量が多くなるように飼育した乳牛は乳腺炎にかかりやすく、乳房が化膿して膿が牛乳に混じってしまうので、予防のために抗生物質を使うから悪循環だね」、と「いでぼく」の井出 行俊(いで ゆきとし)さんから聞いたことがある。
放牧・酪農の歴史
戦後〜1960年代は、自給飼料中心、自然放牧も多く行われていた。1970〜1990年代には、畜産の近代化政策、効率重視により、運動をさせず、搾乳量が多い舎飼いが主流になり、2000年代以降、TMR(Total Mixed Ration・完全混合飼料=「粗飼料」乾草・サイレージ+「濃厚飼料」トウモロコシ・大豆かす+「添加物」ミネラル・ビタミンなど)が普及して、大規模化・高効率経営に進むことになる。
6次産業化
和歌山は酪農家が少なかったこともあり、良くも悪くも、全国的な大きな流れから取り残されたが、乳業メーカーへの卸が100%だったため、乳価が下がった時には、放牧で運動量が多く、乳量が少ないこともあり、岐路に立たされたこともあったが、動物園では飼育していない乳牛を間近で見れる観光牧場として運営していることもあって、周年放牧を続け、6次産業化を目指した。
以前は、搾りたての牛乳を一升ビンなどに入れて販売していた時期もあったが、中止していた。「牧場なのに牛乳はないの?」、「昔のあの牛乳が飲みたい」と云う来場者からの声が多く、「黒沢牧場だけの味を届けよう」と、自社工場を設立し、現在は、「やさしい牛乳」だけでなく、搾りたての生乳をつかった、ソフトクリームミックスやアイスクリームの他、プリン、ロールケーキなどを製造販売するようになり、牧場の直売店「ミルク工房」でも購入したり、食べることができ、売上の30%を占めるようになった、と尚子さん。

黒沢牧場の飼育方法
飼育頭数と飼料
黒沢牧場では、搾乳期の牛が約30頭、子牛〜育成期、乾乳期の牛が約20頭、計約50頭飼育されている。
放牧地に牧草が生える時期はもちろんそれを食べるが、冬期は、夏場に牧草を刈り、ロール状に巻いてラップで密封し、「ロールサイレージ」と呼ばれる、発酵させた保存飼料をつくておいて与えるそうだ。
搾乳方法
放牧で運動量が多く、乳量は少ないとは云え、1日1頭あたり、10kgは搾乳できるそうで、搾乳の時間になると、リーダー格の牛を呼びに行き、その牛が歩き出すと、全頭、連れ立って搾乳小屋に入る、と尚子さん。
そんな都合よく、放牧地にいた乳牛たちが、一斉に搾乳室に入って、おとなしく搾乳されるのか、と云う疑問が湧くが、搾乳期の牛は、乳が張ってくるので搾乳してもらいたいし、牛は、1日の行動サイクルが決まっていて、リーダーと一緒に団体行動する性質もあるので、自然の流れとして、そうなる、と雄大さん。
自然分娩
酪農のドキュメント等で牛舎で人がお産の介助をしているシーンをよく目にするが、黒沢牧場の牛は、毎日、牧草地を歩き回っているので、足腰が強く、お産も自然分娩で、勝手に産み落とすと云う。出産が近い牛だけは、一つのブロックに入れているが、出産すると、母性本能から子牛のそばにいて、給餌の時間になっても来ないので、産まれたことが分かり、初乳を飲ませた後、子牛は引き離して別に育てる、と尚子さん。
子牛に初乳を与える重要性
初乳は、栄養価が高く、成長に必要なホルモンや酵素が含まれているだけでなく、「免疫グロブリン(IgG)」という抗体が大量に含まれており、子牛は胎内で母体から免疫を受け継がないため、生まれたばかりの時期は病気に非常に弱いが、これを飲むことで病気への耐性がつくそうだ。
乳牛のライフサイクル
歳を取ると、老廃物が乳にも含まれるようになり、乳牛の乳房の健康状態を示す重要な指標である、生乳の体細胞率(乳中に含まれる牛の白血球や上皮細胞)が基準値を超えると、 出荷できなくなる。牛は、9カ月10日が妊娠期、黒沢牧場では、1年1産で、5〜6産で乳牛としての役目は終わることになる、と尚子さん。
一般的な乳牛のライフサイクルを調べてみた。
① 誕生(子牛期) 0~2ヶ月 母牛から生まれる。生まれてすぐ「初乳(免疫を含む母乳)」を飲ませる。通常は1日以内に母牛と離され、人工哺育へ。
② 育成期(離乳~妊娠前) 約2ヶ月~14ヶ月 離乳後、牧草・濃厚飼料を食べながら成長。12~14か月で繁殖年齢に達する。
③ 交配・妊娠 約14~24ヶ月 人工授精(AI)で妊娠。妊娠期間は約280日(9か月半)。
④ 初産(1回目の出産) 約24ヶ月(2歳) 初めて出産し、「乳牛」として搾乳が始まる。出産後すぐから乳が出るようになる。
⑤ 搾乳期(泌乳期) 出産後~10ヶ月程度 毎日搾乳。乳量は産後1〜2ヶ月でピークに達し、その後ゆるやかに減少。
⑥ 乾乳期 約60日間(次の出産前) 次の出産に備えて搾乳をやめ、体を休める期間。搾乳を停止し、栄養管理で健康回復を図る。
⑦ 再び出産→搾乳 毎年1回ペースが理想 出産のたびに乳が出るので、1年に1回の出産を目標に管理。搾乳と繁殖を繰り返す。
⑧ 引退 6~7歳前後が一般的 乳量低下や病気・繁殖障害などで「引退」。乳牛は約2歳で出産・搾乳を始め、その後は1年に1回の出産を目指して搾乳と繁殖を繰り返す。平均で6〜7歳まで活躍し、3〜4産(出産)で引退するのが一般的だが、飼育環境や方針により前後する。
黒沢牧場さんでは、5〜6産ということなので、通常の舎飼いより長く乳牛として働いてくれていることになる。周年放牧で運動量が豊富で、ストレスが少なく、健康状態も良いと云う証だろう。
やさしい牛乳

黒沢牧場の牛乳(やさしい牛乳)は、牧草主体のグラスフェッド牛乳のため、牛乳本来の少し黄味がかった乳白色をしている。季節によって乳脂肪分や味わいが変わり、夏場の牧草は水分が多く繊維が少ないことや、暑さによる採食量の低下、飲水量の増加も影響して、牛乳全体がさっぱりした風味になり、冬は寒さで乳量が減るため、乳脂肪や乳タンパクの割合が高まり、より濃厚でクリーミーな味わいになるが、牛乳に季節ごとの違いがあるのは自然なこと。
これに対し、混合飼料で育てた牛乳は牧草由来のβ-カロテンが少なくなるので、牧草主体よりも白くなる、と雄大さん。
低温殺菌
殺菌作業は通常、120度以上の高温で2~3秒かけて行うが、黒沢牧場では、栄養素と生乳本来の味を残すため65度の低温で30分かけて行う。殺菌しつつ、生乳本来の風味・栄養素をできるだけ残すことができ、タンパク質の変性が少ないので、体質によっては高温殺菌より消化にやさしいと云われることもあるそうだ。
ノンホモ牛乳
ホモジナイズ
生乳をそのまま置いておくと、含まれる脂肪球が大きく浮きやすいため、時間が経つにつれて脂肪分(クリーム)が上に浮いて層になることがあり、消費者が「分離している=古いのでは?・不安」と感じやすいことから、高圧(100〜250気圧)で牛乳を狭い隙間に通し、物理的に非常に細かく(1~2μm)均等にする「ホモジナイズ(均質化)」が一般的な牛乳にはほぼ必ず行われている。
ノンホモ
「ホモジナイズ」をしない、クリーム層ができる昔ながらの自然なままの牛乳で、自然な乳脂肪の風味がしっかり感じられ、脂肪球を細かく均一化していないので、お腹がゴロゴロしたり、緩くなったりしない、と尚子さん。
乳糖不耐性とは?
乳糖(ラクトース)=牛乳などに含まれる天然の糖分は、小腸にある「ラクターゼ」という酵素で分解されるが、この酵素が少ない、もしくは、働きが弱い人は、乳糖を分解できずに消化不良を起こし、お腹がゴロゴロする、下痢・腹痛・ガスがたまるなどの症状が出るが、飲んですぐではなく、30分〜2時間後に症状が出るのが特徴。
ノンホモ牛乳も通常の牛乳と同じように「乳糖」を含んでいるので、乳糖不耐性の人に症状が出るのは同じだが、低温殺菌(パスチャライズ) ノンホモ牛乳は60℃程度の低温で殺菌されており、たんぱく質の変性が少なく、また、自然放牧やグラスフェッドの牛乳などは、生乳の質が良く、乳成分のバランスが整っている場合があり、消化に優しいと感じる人もいる。しかし、これは乳糖が少ないという意味ではなく、科学的には乳糖量は変わらないので、体感的な話で、個人差があるとのこと。
お腹がゴロゴロしたり、緩くなったりする主な原因は、乳糖不耐性によるものらしいが、乳脂肪によって消化が乱れる人もいるそうだ。
実際、筆者は、通常の牛乳を飲むと、お腹がゴロゴロするので、豆乳しか飲まないが、「やさしい牛乳」を飲んでもそんな症状は出なかったので、乳脂肪が原因で、脂肪球を細かく均一化していないことがお腹にやさしかったのかもしれない。
乳糖不耐性にも安心な牛乳?
A2牛乳
牛乳に含まれるたんぱく質「β-カゼイン」には、A1型とA2型の2種類があり、A2牛乳は、「A2型β-カゼインのみを含む牛のミルク」から作られた牛乳で、A2牛乳は、乳糖(ラクトース)を含むため、「乳糖不耐性」の人にとって安心して飲めるとは限らないが、「牛乳でお腹がゴロゴロする」症状の原因が乳糖ではなくA1型たんぱく質であるケースもあり、そのような人にはA2牛乳が合う可能性がある。また、「A2牛乳の方が消化しやすく、膨満感・下痢・不快感が軽減される」と云う報告もあるが、科学的にはまだ明確なコンセンサスは得られていない、とのこと。
長期保存可能な牛乳
種類 主な特徴 保存期間 開封後の保存
LL牛乳(ロングライフ牛乳) 超高温殺菌・無菌充填された牛乳 約90日〜6か月(常温) 開封後は冷蔵で3日程度
ESL牛乳(延長賞味期限牛乳) 低温殺菌+衛生的充填で賞味期限を延ばした 約2〜3週間(要冷蔵) 開封後は要冷蔵で数日
滅菌乳(加圧滅菌) 缶や瓶に密封して高温高圧処理 約6か月〜1年(常温) 開封後は冷蔵保存
粉ミルク(乳製品) 水で溶かして使う粉状の保存乳 1年以上(常温・未開封) 開封後は要密封・冷蔵
「ノンホモ牛乳(均質化していない自然な牛乳)」は加工が少なく、賞味期限も短いため、基本的に長期保存には向かないとのこと。
「プレミア和歌山」審査委員特別賞
平成29(2017)年、黒沢牧場(和歌山県海南市)の「やさしい牛乳」は、県内の優れた産品を和歌山県が認定する「プレミア和歌山」の審査委員特別賞に選ばれていて、低温殺菌で仕上げ、臭みが少なく、さらりとした味わいが特徴で、周年放牧、ストレスのない環境の中で乳牛を飼育していることなども評価されたそうだ。
黒沢牧場の今後

(雄大さんは)完全に放し飼いだったのに牛には興味を持ってくれているので、やりたいようにやって欲しい。近畿には、「山地周年放牧」で牧場経営をしているところがないので、今のうちに、日本全国、世界も含めていろんなところを見てきて欲しい。ただ、県内産の牛乳とそれを使った乳製品は継承して欲しいですね、と尚子さん。
雄大さんは、物心がついた頃から、牛に興味があり、ご両親や周りから何も云われなくても、中学生になった頃には、牧場を継ぎたいなと考えていたそうだ。
やりたいようにやって良いと云われているので、やりたいようにやりたい。6次化では、新製品、今考えているのは、チーズ、バター、ヨーグルトにチャレンジしたい。牛がいてこその酪農家なので、この牧場で牛が産まれて、生涯を終えるまで、どれだけ幸せに過ごしてもらえるかが大事。幸せかどうかは人にはわからないところもあるので、何か気付いたら、すぐに改善するなどの努力は惜しみなく、最善を尽くしたい。
食育にも興味があるが、和歌山では、そもそも酪農家が少ないこともあり、畜産や酪農は一般にあまり知られておらず、興味を持つ人も多くない。無理に押し付けるつもりはないが、「酪農体験などの取り組みをしていて、受け入れもできますよ」というカタチを整えておけば、誰かしら関心を持って来てくれるのではないだろうか。来てくれた方には、教えることはもちろん、最大限のサポートをしたいと考えている。また、学校などの教育機関と連携した課外授業など、できることはたくさんある、とおっしゃる。
まとめ
黒沢牧場では、山の斜面の牧草地で牛たちが草を食んだり、のんびりと寝そべっていたり、30年以上前、旅行会社勤務時代、添乗でよく欧州を訪れていた頃に、アルプスの少女ハイジの物語の舞台となった、スイスのマインフェルトに行ったことがあるのだが、そのアルム(高山牧場)を思い出した。
「産業牛」という言葉を尚子さんから聞いた。愛玩動物や自然の中で自由に生きる存在ではなく、効率を最優先して、人間の経済利益のために飼育される牛を指す言葉のようだが、黒沢牧場の牛たちは、人間の経済利益のために飼育されていることに違いはないが、自然の中で放牧され、ストレスが少なく、自然と共生しながら、動物本来の行動ができる環境で飼育され、身体的にも精神的にも健康で、快適に過ごしているように見える。
「牛がいてこその酪農家なので、この牧場で牛が産まれて、生涯を終えるまで、どれだけ幸せに過ごしてもらえるかが大事。幸せかどうかは人にはわからないところもあるので、何か気付いたら、すぐに改善するなどの努力は惜しみなく、最善を尽くしたい。」とおっしゃっる雄大さんは、なんと当年(2025年)、17歳なのである。
代々、牛たちを大事に育ててこられたことを身近にご覧になっていたからこその発想だろうと推察できるが、中学生になった時点で家業を継ぐことを決め、17歳にして、こちらの質問にも何年もこの仕事をしてこられたベテランのようにお答えくださり、放牧地の牧草のこともよく勉強しておられる。何よりもご自身の職業のことをここまで深く考えておられる姿に、その歳の頃の自分を重ねると、まっことお恥ずかしい限りである。
本来、自分の子供を育てるための乳を人間に提供するのだから、乳牛にとって100%幸せとは言い難いのかもしれないが、少なくとも人間が生きるためにいただく以上は、感謝の気持ちを持って育て、できる限り、快適に過ごせるようにするのは当たり前のようで、経済効率優先の今の世の中では、なかなかできないことだ。自分のやりたいようにやりたいと云いながらも、初代から代々続く、この「牛の幸せ、みんなの幸せ」という志をしっかり引き継いでおられる。
また、取材後、何年かぶりにソフトクリームをいただいたのだが、当日はまだ暑く、食べ慣れないこともあって、最後の方で、溶けたソフトクリームがコーンの外に垂れてきて、ティッシュを尻ポケットから出して拭かなきゃと思っていたら、「コレ、良かったらどうぞ」と、ペーパータオルを持ってきてくださった雄大さんの気配り、尚子さんは、完全放し飼い、とおっしゃっていたが、きっとご両親の背中を見て育たれたのだろう、良い環境で人も育つということだ。
「富裕層というより、心が豊かな人に買ってもらえるようなマーケットを創ればいいだけのこと」と前出の井出さんがおっしゃっていたが、雄大さんは、お客様にも牛さんたちにもしっかり目配り、気配りされ、「独自のマーケット」を創り、黒沢牧場をさらに発展させていかれるだろう。
以前、大松農場の大松さんから、ウィンドレスケージの中で、まるで工場の機械のように、経済効率だけを優先して鶏卵を生産する仕組みを伺ったが、酪農も同じ、食は命であり、私たちは、命をいただいて、生かせてもらっているのである。毎日の生活に追われて深く考えられない人もいらっしゃるだろうけど、消費者も、牛乳や乳製品がどのような環境で何を食べさせて飼育されている乳牛からいただいているのかだけでなく、お米や野菜、お肉や魚、調味料他、日々、いただく食べ物、飲み物がどのようにつくられているのか、しっかり考えてみる必要がある。
自然の中で自由に、快適に過ごし、身体的にも、精神的にも健康な牛さんたちから搾乳した牛乳だから、おいしく、お腹もゴロゴロしなかったのだろう。
COREZOコレゾ 「牛の幸せとみんなの幸せを願い、今や希少となった『山地周年放牧』を続け、豊かな自然環境の中、のびのびと健康な乳牛を育て、『やさしい牛乳』と乳製品を届ける酪農家親子」である。
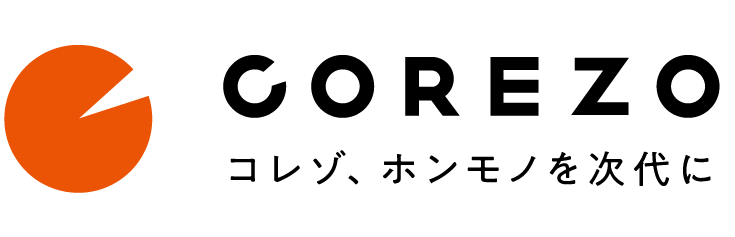
コメント