
目次
COREZOコレゾ 「日本酒の蔵人を経験して家業を継ぎ、初代から110年以上続く伝統的な木桶仕込みの醤油づくりを次の代に引き継ぐ重積を担いながら 、明るい未来に向かって邁進する五代目」 賞

岩本 庄平(いわもと しょうへい)さん/有限会社カネイワ醤油本店 五代目

プロフィール
和歌山県有田郡有田川町小川
有限会社カネイワ醤油本店 五代目
COREZOコレゾチャンネル
有限会社カネイワ醤油本店
有限会社カネイワ醤油本店の歴史

カネイワ醤油本店の初代は、明治時代後半、醤油の生まれ故郷に程近い、湯浅醤油で名高い紀州・湯浅で醤油の製法を学んで醤油醸造技術を身につけた後、紀伊山地、高野山系から湧き出る良質の水を醤油醸造に使うためにこの地を選び、根を下ろして、大正元年(1912年)、醤油醸造を始めた。
創業以来、110年以上、豊かな自然に囲まれ、すぐ隣を美しい有田川の支流が流れるこの地で、カネイワ醤油本店は、伝統的な大きな木桶による昔ながらの製法で春夏秋冬を2回、8つの季節を越えて天然発酵熟成する醤油づくりを続けておられる。
カネイワ醤油本店 四代目 岩本 行弘 さん
現代表取締役である四代目の岩本 行弘(いわもと ゆきひろ)さんが中学生だった頃、日本は高度成長期(1955年頃〜1973年頃)の真っ只中で、TVCMをするような大手の醤油が地方にも進出してきた。当時、有田川町には、5軒ほどの醤油蔵があったのだが、その勢いに席巻されて2軒にまで減り、昭和60(1985)年ごろには、もう1軒も廃業して、カネイワ醤油本店1軒だけが残った。
そんな醤油蔵の商売としては厳しい中、行弘さんは、公務員をしながら、20代の頃から百貨店でのギフト販売や催事への出展等を手伝っておられたが、そうこうする内に地方の隠れた名品や昔ながらの製法でつくった商品がTV番組等で取り上げられるようになり、徐々に消費者の皆さんにもカネイワ醤油の良さが認知されるようになっていた。時代が巡ってきたのではないかと感じていた38歳の時、70歳になった先代から、「継ぐならもう少し頑張って設備も更新しないといかんし、継がないなら自分の代で終わってもええ」と云われ、公務員を辞めて四代目を継ぐ決心をされた。
家業を継いで約30年、厳しい時代をなんとか乗り越えて、より美味しいものや醤油もより良いものが求められる時代となって、食卓が笑顔になると喜んで購入してくださるお客様、ウチの店の味の決め手はカネイワ醤油等々の嬉しい声も聞くようになり、有難く感謝しかないが、息子も帰って来て継いでくれたので、頑張ってきてよかったなと思う、と行弘さん。
カネイワ醤油本店 五代目 岩本 庄平 さん
五代目の庄平さんは、父から云われたことはなかったが、祖父母や親戚、近所の方たちから、長男だから継ぐものだ、と刷り込まれ続けてきて、子供の頃はそれが嫌だと思ったこともなかった。ところが、中高生になると、将来のことも考えるようになって、同級生たちから、お前んとこは醤油屋やから継いだらエエもんな、と云われるのが嫌で、継ぐつもりはあったが、大学卒業して、そのまま家業に入るのは甘えているようだし、一旦は、別の企業に勤めることだけは決めていたそうだ。
大学卒業後、文系だったのに、奈良の日本酒メーカーに蔵人として採用されて、酒づくりでは麹を担当した。米の蒸し方や麹の仕込み方他を考えたり、仕事自体はとても楽しかったが、酒づくりの新たな提案をしてもなかなか受け入れてもらえず、サラリーマンの限界を感じ始め、会社勤めではできなかったことができるんじゃないか、あんなことやこんなこともできるんじゃないか、とイメージするようになって、5年間の勤務後、家業に入った。
5年と云う短い期間ではあったが、醤油より繊細な酒づくりに携わり、お酒は、醤油よりも熟成期間が短く、デリケートで、ちょっとした要因が味や香りに大きく影響するため、失敗要因を限りなく無くすことが基本で、清潔第一が徹底されている製造現場を経験してきた。家業に入って、先ずは、醸造所内の清掃を徹底して清潔にし、失敗要因を無くして作業効率を高めるため、配置換え等に取り組んだ。
これまで通り続けることが当たり前で何かを変えようという発想もなかったので、最初は戸惑ったこともあったが、理に叶っていることも多く、結果として、8割方は上手くいって作業効率も上がっており、息子が帰ってきてからの5年間、新しい風が入ったことで製造現場はかなり改善されたと思う。良いのか良くないのかは、やってみないと分からんし、人間、頑固になったらアカンなぁ、と行弘さん。
また、もろみの櫂入れ、絞り方、火入れの仕方他、どの工程をとってもそれぞれに意味があり、つくり手ができることは限られるが、何をどうすればどうなるかを突き詰めていけば、昔ながらのつくり方をずっとやり続けてきたカネイワ醤油は、もっとおいしくなる、と思うので徐々に取り組んでいきたい、と庄平さん。
販売面では、地元を約10年離れていたこともあり、疎遠になっていた人間関係もあるため、SNSでの発信と並行して、マルシェなどのイベントにも積極的に参加して、兎に角、名前と顔を覚えてもらい、醤油は放っておいても売れるものではないので、お客様としっかり会話して、カネイワ醤油を気に入っておいしいと思ってくださる方に購入していただくにはどうすれば良いかを常に心掛けてきて、徐々にではあるが、リピーターのお客様が増え、SNSで繋がった方がわざわざ購入に来てくださるようになったりと結果につながりつつあるとのこと。
カネイワ醤油本店の代表的な商品
生醤油(なましょうゆ)「穀醢(こくびしお)」

北海道産の丸大豆、近江産の小麦、こだわりの国産原料を原料処理、そして麹(こうじ)をつくり、木桶に入れた塩水に麹をいれて丸2年の間、日々撹拌しながら愛情こめてじっくりと発酵熟成させた諸味(もろみ)をただ搾っただけで、調味はもちろん火入れもせず、何の手も加えていない。火入前の搾りたてそのままの酵母や微生物が生きている「生醤油(なましょうゆ)」。
昔ながらの伝統の技法で醸造した「カネイワ醤油本店」の味が、この「穀醢(こくびしお)」に集約されていて、火入れをしていないので、醤油の香りというより、醤油蔵や諸味(もろみ)そのものの香りがして、味は醤油で、2年熟成しているので、まろやかでやや濃厚。
搾ったままの生揚醤油は微生物の活動により醸造されたものなので、微生物が生き続けていて、このままの状態でビン詰めすると、発酵が進み品質が変化してしまうため、熱を加え、火入れ殺菌をして微生物たちの活動を止めることで醤油としての品質を保持し、安全に流通できるようにする。
火入れには、微生物たちの活動を止めるだけでなく、以下の効果もある。①醤油に熱が加わってアミノカルボニル反応が促進され、冴えた赤みの強い色になり、色沢が整う、②同じくアミノカルボニル反応によって、香ばしい醤油香が出る(付く)、③分解されなかったたんぱく質や乳酸菌、酵母菌がオリとして固まるのでビン詰め前にろ過の工程で取り除くことができる。
酵母や微生物が活きている醤油を美味しくいただくには、やはり醤油自体に火を入れないのが一番、まずは、「つけ」「かけ」醤油で、お刺身に付けると本物の味と香りが口の中いっぱいに広がり、素材の味を一段も二段も引き上げてくれるので、この「生醤油(なましょうゆ)」にハマった方は、他の醤油には浮気されないそう。
また、前述の火入れの効果②の通り、諸味(もろみ)を搾ったままの生揚醤油(きあげしょうゆ)の火入れ時に漂う香ばしい醤油香が一番良い香りだそうで、煮炊きなど加熱するお料理に使うと、熱が加わった際に、醤油蔵の火入れ担当しか知らない、食欲がかきたてられるその香ばしい醤油香を家庭でも楽しる。
この「生醤油」は酵母が生きており、品温10度以上になると発酵が進むので、未開栓、開栓に関わらず要冷蔵で早めに使い切って欲しい、とのこと。
古式しょうゆ

北海道産の丸大豆、近江産の小麦、厳選した国内原材料にこだわり、天日塩を使用して二年間じっくり木桶で発酵、熟成させた「もろみ」を搾った醤油で、生醤油(なましょうゆ)「穀醢(こくびしお)」との違いは、火入れをして酵母の活動を止めているところのみ。
「こく」があって「まろやか」、香り豊かで上品な味わいで、「つけ」「かけ」用としては赤身のお刺身に、また、焼肉他の脂身にも負けない旨味が特徴。 また煮炊き用としても少量でしっかりと味も香りもつけることができる。
開栓後は、要冷蔵で早めに使い切って欲しい、とのこと。
有限会社カネイワ醤油本店の今後

「穀醢(こくびしお)」をはじめ、昔ながらの伝統製法で醸造した「カネイワ醤油本店」の味を大きく支えているのが、創業以来使い続けている仕込み蔵と木桶である。現在、木桶は22本あり、どれも年季の入ったものばかりで、液漏れしている桶もあって、どんなに大事に修理して使ったとしても、その内、順次、寿命を迎えるだろう。自分の代は、この創業110年以上のカネイワ醤油本店で木桶を使い続けるかどうかの瀬戸際で、それを決断する役目も担っていて、木桶職人復活プロジェクトにも参加しつつ、今後、醤油の販売高をどう増やしていくか、増やしていけるかも見極めながら、できるだけ良いカタチで次の代、次の未来に引き継げるよう取り組んでいきたい、と庄平さん。
伝統製法の醤油を続けるのは大変なことで、100年を超えて木桶仕込みをしておられる醤油蔵さんはどこも木桶の維持管理に苦労しておられる中、小豆島のヤマロク醤油の山本 康夫(やまもと やすお)さんが中心となって活動されている「木桶職人復活プロジェクト」の取り組みからは、毎年、新桶がつくられ、仕込みのできる大桶の製作や補修のできる職人が育っている。
現在、木桶仕込みをしておられる醤油蔵さんの多くが「木桶職人復活プロジェクト」に参加されており、五代目の庄平さんは、同じ悩みを抱える醤油蔵さんと情報共有、連携し、山積みの課題をひとつづつ解決して家業をさらに盛り立て、より良いカタチにして次の代に引き継げるよう、明るい未来に向かって邁進されることだろう。
COREZOコレゾ 「日本酒の蔵人を経験して家業を継ぎ、初代から110年以上続く伝統的な木桶仕込みの醤油づくりを次の代に引き継ぐ重積を担いながら 、明るい未来に向かって邁進する五代目」である。
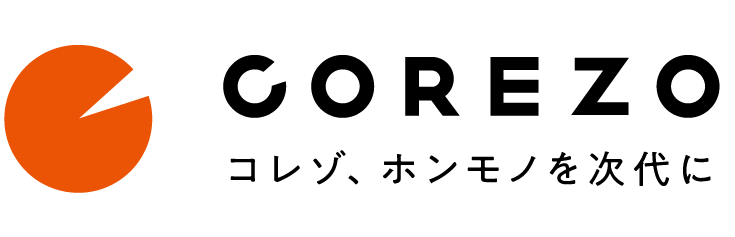
コメント