
目次
COREZOコレゾ 「歴史と伝統を守り続ける企業や産業と積極的に関わって、『つくり手』の想い、価値観、背景他を分かり易く、魅力的に言語化し、『つかい手』の共感を呼んで、相互信頼の関係性を結び、育む『つたえ手』」 賞

岩田 舞海(いわた まゆみ)さん/コピーライター/クリエイティブ・ディレクター/プランナー

プロフィール
愛知県県名古屋市
日本プロモーショナルマーケター協会JPM認定プロモーショナル・マーケター
【経歴】
グラフィックデザインを学んだ後、広告制作プロダクションに勤務。’89年よりフリーランスのコピーライター/広告ディレクター/プランナーとして活動。
’92 スズケングループCI計画ツール制作
’96-‘09年契約コピーライターとして松坂屋本店・豊田店広告全般、2010年大丸松坂屋統合広告制作
’03-‘08年名古屋ブルーノート情報誌編集長
ソフトバンククリエイティブODN WEBマガジン「STELLA」企画・制作
平安会館・中日新聞広告連載コラム(2012-2020)
‘12年より瀬戸焼振興協会発行情報誌『セトリエ』企画・編集・ディレクション・コピーを担当。
各種広告企画・制作、SP企画、CI/VI企画、編集・出版、リクルーティング、ブランディング、 WEBサイト企画制作、商品・店舗・イベント関連のプロデュース等、案件・クライアントご依頼内容に応じて制作チームを編成し、制作管理から制作全般、印刷・WEB制作受注、SPコンサルティングまで行う。
【賞歴】
‘97年 世界ポスタートリエンナーレ・トヤマ入選
‘01年 第9回中日新聞広告賞最優秀賞/株式会社松坂屋
‘03年 第11回中日新聞広告賞ショッピング部門賞/株式会社松坂屋
‘05年 第14回中日新聞広告賞地域メディア賞/株式会社松坂屋 他
COREZOコレゾチャンネル
受賞者のご紹介
岩田 舞海(いわた まゆみ)さんとの出会いは、ヤマサちくわ株式会社 代表取締役の佐藤 元英(さとう もとひで)さんにCOREZO賞を受賞いただいたことがきっかけだった。岩田さんは、佐藤社長が主宰される「豊・食・人 GEN‐B(げんび〜)」のWebサイトの制作を受託しておられ、COREZO賞の表彰式や「豊・食・人 GEN‐B(げんび〜)」のイベントで何度もお目に掛かっていた。
名古屋城にほど近い、名古屋市西区でお祖父さまが創業された名古屋発祥の楽器「大正琴」とギター製造会社がご実家で、現在は、弟さんが「ナルダン楽器」の三代目として、大正琴の製造販売、修理、メンテナンスをはじめ、「大正琴教室 澄音会(すみねかい)」も主宰されている。
今回、「ナルダン楽器」さんのサロンをお借りして、お話を伺った。
コピーライター・クリエイティブディレクターの仕事
岩田さんは、ご実家のものづくりの現場を遊び場にして育ち、関心のあったグラフィックデザインを専門学校で学ばれた。グラフィックデザイン科の卒業制作・広告部門最優秀賞を受賞し、コピーライティングも評価されたことで、コピーライターの仕事にも興味を持つようになり、広告制作プロダクションに就職された。
仕事の中で、クライアント企業さんや勤務先が岩田さんに任せてくださったこともあって、能装束の人間国宝・山口安次郎氏や法隆寺昭和大修理を手がけた宮大工棟梁・西岡常一氏、画家・岡本太郎氏など、ものづくりやアートを牽引する著名人の方々にインタビューをする機会があり、創作にかける思いやものづくりの哲学に触れて、「伝える」ことの大切さに使命感を抱くようになった、とおっしゃる。
広告の仕事は多岐に亘るが、愛知は、ものづくりが盛んな地域で、数多くのものづくりの現場取材を通じて、コピーライターおよびプランナー、そしてコーディネーターとしても研鑽を積んでこられた。
お祖父さん子だったこともあり、祖父は、製材所で原材料を選び、職人さんたちに指示をして、大正琴の製造・販売をしていたし、さらに父も貿易の仕事から大正琴の製造・販売の道に入って、演奏を教えるところまで、一貫してものづくりをする祖父と父の姿を見て育ったので、ものづくりの現場取材には役立ったかもしれない、と岩田さん。
フリーランスとして独立後は、大手百貨店を主軸とした広告宣伝部の専任ディレクター/コピーライターとして、MD=Merchandising(マーチャンダイジング・売るための仕組みづくり)・SP=Sales Promotion(セールスプロモーション・売るための具体的施策)企画、ブランディング、流通の活性化と魅力発信に力を注いでこられた。
岩田さんの転機
2011年の東日本大震災で、ものづくりの根幹が一気に壊されてしまい、食の安全や子供たちの健康も危惧されるようになって、被災地支援プロジェクト「MINAMOTO源CALLING!」を始動し、復興ボランティア団体の後方支援と併せ、福島・北関東からの親子保養キャンプの運営スタッフとして、主に「安全・安心な食の提供」に関するサポートを担当した。
食の現場や生産者さんともっと深く関わりたい、その土地、土地で食べられてきたもの、営んできたものを生活に取り入れて、繋いでいけるような社会をつくるお手伝いをしたい、と強く願うようになった、と岩田さん。
地元・円頓寺商店街の活性化

円頓寺(えんどうじ)商店街は、名古屋駅から名古屋城へ向かう間にある、名古屋で一番古いアーケード商店街。寺院(圓頓寺)の門前町として発展し、周辺には昔の蔵群など、名古屋の古い町並みが残り、人気のレストランがたくさん集まる四間道(しけみち)などが近接していて、レトロで個性的な商店街として注目されている。
岩田さんが生まれ育った生家の近隣にある商店街だったので、商店主たちが発行するフリーペーパーを20数年前からお手伝いし、連載コラムも書いてきた。円頓寺商店街の中には、何故か、フランス好き、パリ好きの方が多く、2013年から、パリをテーマに、商店街をフランス風マルシェに見立て、雑貨・カフェ屋台・音楽などで賑わいを創出しようと云う「円頓寺秋のパリ祭」がスタートし、2年目(2014年)からそのイベントの実行委員として、企画から広報まで関わることになった。
コロナ禍の時期には、飲食を控える状況があったので、フランスのMOF受賞職人さんと名古屋の円頓寺商店街をつなぐ企画をつくり、フランスの職人さんには、日本の伝統工芸や食文化を知ってもらい、日本の職人さんには、フランスでMOF受賞した日本人もいらっしゃって、フランスで活動できる道もあることを伝え、日仏の職人さんたちが交流する橋渡しができれば、という想いで続けている。
現在(2025年)、開催されている大阪関西万博でのフランス館のMOF関連のイベントでは、縁ingの西村社長をご紹介したところ、MOFオリジナルの前掛けをつくってくださり、MOFの職人さんたちがそれを着けてPRをされていた、と岩田さん。
「MOF(エム・オー・エフ)」とは、フランスの国家認定資格である、Meilleur Ouvrier de France(ムイユール・ウヴリエ・ド・フランス=「フランス国家最優秀職人章」)の略称。1924年に創設、約3~4年ごとに開催されるコンクール形式で授与され、料理人、パティシエ、靴職人、ガラス職人など 100以上の職種が対象だが、合格率は非常に低く、一生かけても受からない人が大半と云われるほどの難関。近年、日本人受章者も誕生しているそうだ。
フリーペーパー「セトリエ」

岩田さんは、工芸の分野の仕事も数多くしてこられて、2012年、「せともの(瀬戸物)」の語源ともなっている「瀬戸焼振興協会(愛知県瀬戸市)」から、瀬戸焼を焼き物好きの方たちだけでなく、もっと広く、多くの方々に知ってもらいたい、と云う依頼があり、「瀬戸焼のあるくらしが好きになる。」をコンセプトに、その歴史から、瀬戸焼を身近に楽しむライフスタイルやつくり手の紹介、器の使い方、瀬戸のまちの魅力、カフェやショップなどの情報を発信する、瀬戸焼情報「セトリエ」の企画・編集・ライターとして、通算16冊を制作された。
「瀬戸焼」は、「常滑焼」、「越前焼」、「信楽焼」、「丹波焼(立杭焼)」と並んで、「日本六古窯」として知られ、1,000年以上の歴史を持つ日本の代表的な焼き物の産地である瀬戸市は、ものづくりのまちで、特有の息吹き、雰囲気があり、取材を重ね、地元の方々と親しくなることで、地域外の目から見た瀬戸のまちの良さ、楽しさ、おもしろさを伝えられたら、という想いで制作していた、と岩田さん。
豊かに食べ、愛で味わう人々の交流会「豊・食・人 GEN-B」

「ヤマサちくわ」さんは、創業以来、箱根を越えず、比叡を越えず、で事業を続けてこられたが、2028年に創業200年を迎えるにあたって、関東圏にも商圏を広げようと云う方向性になり、佐藤社長の発案で、関東圏にも「ヤマサちくわ」の熱心なファンを増やして、会員の皆様と美味しく食べ、楽しく語らうことを目的に「豊・食・人 GEN-B」(「げんび〜」=三河弁で食いしん坊の意)と名付けた交流会を発足し、活動を開始した。
この交流会をしっかりブランディングをして、情報発信もして行こうということから岩田さんにお声が掛かり、「豊・食・人 GEN‐B(げんび〜)」のWebサイトの制作に関わることになった。
創業200年に向けて、「豊・食・人 GEN-B」を発足し、活動を開始した佐藤社長の想いを伝え、アーカイブスとしてその活動をいつでも誰でも見れるようにすることで、今後、新たに「ヤマサちくわ」さんに入社されたり、若手の社員さんたちも勤務先企業が取り組んできた歩みを知ることができる、と岩田さん。
「アーカイブス(archives)」とは、歴史的・文化的・社会的に重要な記録や資料を収集・保存・整理し、後世に伝える仕組みや場所、またはその資料群を指す。
四谷の千枚田(愛知県新城市)での「豊・食・人 GEN-B 田植えツアー2025」、第5回 あいち/名古屋『豊・食・人 GEN-B』交流会「198年三河で続く、昔も今も変わらぬ”うまさ”の秘密」、第9回『豊・食・人 GEN-B』交流会「~江戸から続く手仕事と魚旬暦を楽しむ~その九」、第8回『豊・食・人 GEN-B』交流会「~江戸から続く手仕事と魚旬暦を楽しむ~その八」他の活動レポート作成も手掛けておられる。
「豊・食・人 GEN‐B(げんび〜)」旬のひと・もの・こと特集はこちら
「豊・食・人 GEN‐B(げんび〜)」豊・食・人GEN-B活動レポート一覧はこちら
仕事を進める上で大事にしていること
コピーライターという仕事だけでも、商品開発から関わったり、ネーミング、コンセプトワーク他、多岐に亘る。西岡棟梁の「木を組むなら人を組め」という名言に、若い頃、感銘を受けた。制作全体を統括してみる仕事もしてきたが、カメラマンさん、スタイリストさん、デザイナーさん、印刷会社さん…、皆さん、それぞれの立場での想いがあるので、まず、想いをよく聞いて、どう組むかを考え、チームとしてまとめていくことを大事にしてきた、と岩田さん。
「木を組むなら人を組め」とは、法隆寺や薬師寺の修復を手がけ、「最後の宮大工棟梁」とも称された西岡常一棟梁は、現場を指揮・統括する最高責任者として、人を育て、導き、まとめてきた経験から、建築やものづくりだけでなく、どんなことでも、理解しあって信頼関係を築き、適材適所で、それぞれの長所を引き出し合えるチームワークが最も大切である、という教え。
つたえ手としての想い
この仕事に就いて、約40年(2025年現在)、いろんな方々に支えられてきたが、最近は、地元の愛知に軸足を置いていて、時代の流れとともに、文化や経済、企業のあり方も変わっていく中、愛知には長く継続している企業が多く、そんな企業の哲学やものづくりの魂は、今も息づいていて、50年、100年、200年続いた企業が、この先、次の時代に何を残し、伝えていくか、次の未来を考える仕事に関わらせていただけたら嬉しい。
ただ、現場をつくって来られた方々の想いとその積み重ねが礎となっている企業としての哲学や理念が継承され難い時代となっていて、継承されるにはどうすれば良いかは、常に意識している。現場の生の声を上手く伝える手法を考えたり、ただ残すだけでなく、誰でもSNS他で発信できる時代なので、事業者自ら能動的に活発に情報発信できるネットワークをつくっていきたい、と岩田さん。
岩田さんの今後
これまで、ものづくりや工芸、食の現場、愛知の地域ローカルの文化等々を取材し、伝えることに取り組んできたが、今後は、伝えていく種子を植えていきたい、と願い、IT企業さんやプロダクトデザイナーさんたちと連携し、日本列島の腰帯のような東海3県(愛知県、岐阜県、三重県)をひとつの軸として、企業とつかい手である消費者、食の生産者とアーティスト他、いろんな関係性を繋ぐメディアづくりの準備中。
コピーライターという仕事だけでも、商品開発から関わったり、ネーミング、コンセプトワーク他、多岐に亘るが、「もの」にも「まち」にも「つくり手」がいらっしゃって、それをつかったり、楽しんだりする「つかい手」がいらっしゃるから、経済活動が成り立つわけで、コピーライターは翻訳家であり、どちらの言語も柔軟に翻訳して、より分かりやすく伝えられるよう、今後も取り組んでいきたい、と岩田さん。
まとめ
円頓寺商店街のWebサイトで、岩田さんがインタビューを受けている記事を見つけた。
■店主インタビューでは、どんなことを意識しましたか
公式サイトの固定記事として、遠方や円頓寺商店街界隈をあまり知らない方にも、ある程度ロケーションや雰囲気をイメージしてもらえるよう配慮しました。他の媒体やSNSのリンク等、各店主の記事を発信、活用してもらえるツールになるよう、単独でも読み切れるし、まとめて読むと各店のつながりが見えてくるような構成にしています。
なにより、店主への直撃インタビューを通じて、単なるお店の宣伝記事ではなく、「顔の見える商店街」として、そこにいる「人」が見えるようなものにしたかったんです。個々のお店が商店街とどんなふうに関わりを持っているか、代々受け継いできたお店も多いので、子どもの頃や若いころの話、お父さんやおじいさんの思い出など。また、新たなお店も含め、まちの歴史や活気を継いでいく個々の想いなどをおたずねしました。
店主個人の目線や姿勢からまちの風景が見えてくるように、点と点ではなく、面として見えるように。
商店街やお店は過去にもメディアで取り上げられてはきましたが、これだけ一気に紹介されるのは初の機会でしたので、商店街の「いま」を感じてもらいつつ、先にも残せるアーカイブスをめざしました。
■円頓寺オンライン商店街はどんな役割を担うでしょうか
取材歩きをしてあらためて気づいたのは、意外と一見さんには入りにくい面もあるかなということ。私自身もインタビューの際には「よし、行くぞ」と気合いを入れて扉を押していました(笑)。この記事を読んでもらうことで、お店に近づく一歩になれば。はじめて訪れる方にとっても、円頓寺オンライン商店街の記事や情報がお店に入りやすくなるきっかけになるといいですね。
お店と商店街がどうつながっていけるか、お店も常に考えていると思いますが、実はお客さんがまちを歩き、いろいろなお店に入ることで、商店街を、まちを、自然につないでくれているんだと思います。
「単なるお店の宣伝記事ではなく、『顔の見える商店街』として、そこにいる『人』が見えるようなものにしたかった」、「お店と商店街がどうつながっていけるか、お店も常に考えていると思いますが、実はお客さんがまちを歩き、いろいろなお店に入ることで、商店街を、まちを、自然につないでくれている」と云う考え、想いこそが、岩田さんのコピーライター・クリエイティブディレクターとしての仕事の真髄ではないかと思う。
今後も、「つくり手」と「つかい手」の良好な関係性を結び、育む「つたえ手」としての活動を続け、そして、伝えていく種子も植えていかれることだろう。
COREZOコレゾ 「歴史と伝統を守り続ける企業や産業と積極的に関わって、『つくり手』の想い、価値観、背景他を分かり易く、魅力的に言語化し、『つかい手』の共感を呼んで、相互信頼の関係性を結び、育む『つたえ手』」である。
取材;2025年9月
初稿;2025年9月
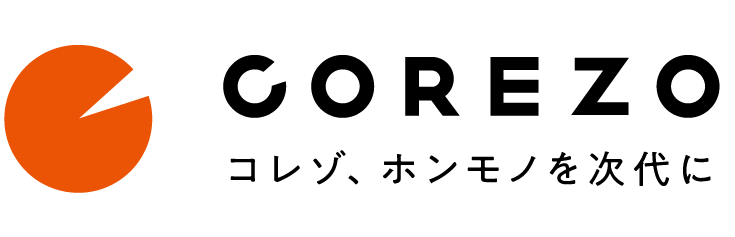
コメント