
目次
COREZOコレゾ 「『受け継ぎ守るもの』と『進化し変えるもの』の両輪で 次の代に向け、楽しく仕事をする姿を見せ、木桶仕込み醤油への挑戦を決断した 全くの素人だった醤油づくりを引き継いだ六代目」 賞

吉川 修(よしかわ おさむ)さん/イゲタ醤油醸造元 株式会社井上本店 代表取締役社長

プロフィール
奈良県奈良市北京終町
イゲタ醤油醸造元 株式会社井上本店 代表取締役社長
COREZOコレゾチャンネル
イゲタ醤油醸造元 株式会社井上本店
株式会社井上本店の歴史

イゲタ醤油醸造元 株式会社井上本店は、幕末の元治元年(1864年)、奈良公園、興福寺南側の猿沢池近くで醤油蔵として創業した。その後、JR奈良駅から桜井線で一駅、往事は、奈良北東部、中南部、大阪などを結ぶ物流の拠点として栄えていた奈良市の京終(きょうばて)の地に移転した。
1941年(昭和16年)頃に先々代が買い取ったレンガ造りの建物は、氷会社の氷室(貯氷庫)として大正時代末期に建てられ、堅強な造りで保温性が高く、温まりにくく冷めにくい特性を持ち、今も醤油蔵や保管庫として使用されている。
戦後の大きな混乱の中、一部事業からの撤退や物不足などによって思うように原料を手に入れることができず、醤油がつくれない困窮の時代を経て、先代の五代目は、お酒の小売販売、濃縮ジュースや米糀の製造販売などでなんとか事業を継続させながら、社長業だけではなく、自身の考える“本物の醤油”づくりを目指す醸造職人として、「醤油とは」、「醸造とは」、「微生物と人間とは」と問い続け、日々研究を繰り返して、現在の井上本店の基礎を築いた。
現在の社長の吉川修さんは、醤油屋五代目の娘(現専務 惠美子さん)さんと結婚したが、事業を継ぐ予定ではなかったのに、或る日、先代との会話の中で「そろそろ会社たたもうかな…」という言葉から、気づいたら六代目を継ぐための慣れない醸造生活が始まっていたそうだ。
醤油づくりは全くの素人だったのに、先代からの職人の体調不良による引退もあり、一緒に醤油づくりに取り組めたのはほんの数年で、手取り足取り教わることはなく、自分なりやってみて何かを見つけてゆく日々となった。
醤油は単なる旨味調味料ではない。
元来、醸造は微生物が自らの生命をまっとうするために作り出す貴重な生命物質を利用させていただくという先祖の遺産である。
先代が残したこの考え方こそ、自分たちが守ってゆくものだと考え、「自分たちが食べて美味しいと感じるものを造ること」に対して、「受け継ぎ守るもの」と「進化し変えるもの」の両輪で、現代の科学的なアプローチや技術的な改善改良にも積極的に取り組んでおられる。
七代目となる吉川 遼(よしかわ りょう)さんは、大学の醸造科への進学時にはまだ迷っておられたそうだが、在学中、醸造の勉強をするうちに、家業でやっている昔ながらの醤油づくりのおもしろさに気づき、継ぐことを決めた。いざ家業に入ってみると、思っていたより仕事は大変だが、一からの醸造をはじめ、できる限り昔ながらのつくり方にこだわっているところも多く、また、いろんなことをやっていることを知り、やればやるほど発見があって、改善点を思いついたり、実際に試してみたりと、奥が深く、おもしろい、とおっしゃる。
六代目のお父様の修さんは、醸造の勉強もしておられず、醤油づくりは全くの素人で、手探り状態で家業を引き継がれたこともあり、ご子息たちには、継ぐ、継がないは別として、ひとつの選択肢として、醸造の勉強はしておいたら、と折に触れ伝えておられたそうで、結果として、ご子息はお二人共、醸造科に進学し、家業に入られた。
井上本店の醤油づくり
蔵に住み着く微生物たちの邪魔をしないよう人がサポートして、長期間熟成、天然醸造にこだわって丁寧な醤油づくりを心がけ、醤油の原料は、大豆、小麦、塩。井上本店では、穀物原料は国産のものを使用し、原料の処理から製麹、仕込み、発酵、熟成、圧搾までの醸造の全工程を自社で行っておられる。
1960年代に施行された中小企業近代化促進法に基づき、全国のほとんどの地域では、圧搾までの工程を地域の醤油メーカーの共同工場で行うようになったが、奈良県の醤油生産者は、この方針に賛同せず、昔ながらの醸造を続け、酵母菌を守り継ぎ続けてきたため、それぞれの醤油蔵の独自性が失われておらず、今でも蔵によって違った醤油が生産され続けているそうだ。
昔ながらの製法による醤油づくりを続ける中で、「微生物の邪魔をしない」範囲で様々な専用設備を導入し、中でも、こちらも自社で一から仕込んでいるストレートつゆの製造にも対応した充填設備と原料や醤油の検査が行える分析室は、小規模生産者としては珍しく、「自分たちが食べて美味しいと感じるものを造る」ために必要なものとして、完備しておられる。
環境保全の取り組みとして、圧搾時の「醤油粕」は畜産用飼料や堆肥に加工して使われ、通常は、産業廃棄物として捨てられる生揚醤油から分離した「油」も小麦を炒る機械の燃料として再利用している。
木桶仕込み醤油への挑戦
五代目が導入したコンクリート製の醸造タンクは、 木桶のあと、昭和初期から中期にかけて、醤油の醸造容器として普及したそうで、木桶と同じく、コンクリートタンクは解放状態のため、蔵に住み着く微生物の影響を受けやすい特性があるそうで、それが地元消費者の皆さんから愛される各種イゲタ醤油の個性でもあり、特徴にもなっていて、原料には国産丸大豆・小麦、オーストラリア産天日原塩を使用し、開放型コンクリート槽での発酵・熟成を経て、製造して来られた。
しかし、使い始めてから40年を経過し、経年劣化により、使用できないコンクリート槽も増え、新たな発酵槽について考えなければならない時期を迎えている。後継者であるご子息たちが家業に入ったこともあって、単に天然醸造を続けてゆくという事だけでなく、手入れや入れ替えなどの管理面の有用性、環境負荷の軽減など、様々な条件を検討した結果、自然素材である伝統的な木桶に戻ることが良いという考えに至った。
現在では、ガラス繊維などの繊維を入れた強化プラスチック(FRP=Fiber Reinforced Plastics)や金属製の醸造タンクが用いられることが多くなり、木桶の需要がなくなって、醸造用の大型木桶を製造する桶屋さんもほとんどが廃業され、木桶は絶滅の危機に瀕している状態だ。
このままでは木桶による醸造という日本の文化までもがなくなってしまうという現状を憂い、小豆島のヤマロク醤油の山本さんが中心となり、醤油蔵、酒蔵、味噌蔵、流通・飲食関係者によって立ち上げられた「木桶職人復活プロジェクト」を通じて、木桶を手に入れることができたとのこと。
醸造の世界では何百年も使い続けてこられた実績のある昔ながらの木桶だが、井上本店さんにとっては、子ども世代、孫世代、これから先も醤油をつくり続けるための新しい挑戦であり、「自分たちが食べて美味しいと感じるものをつくる」そんな当たり前のことにコツコツと真面目に取り組んできた想いを込めて木桶仕込み醤油「木まじめ」という名前をつけられた。
「木まじめ」は、いわゆる濃口醤油というものに分類され、色は透き通った赤橙色で、華やかな香り、軽やかな味わいで、素材の味を引き立てる名脇役のような醤油に仕上がった。木桶づくりの醤油は、長年使ってきた開放型コンクリート槽での発酵・熟成とは、熟成期間が異なり、また、仕込み始めてまだ間も無く、棲みついている微生物も異なるだろうということもあって、フレッシュな風味があるそうだ。
50年前は約6,000社あった醤油蔵は、現在では1,000社ほどとなり、個性的な醤油はどんどん姿を消していて、醤油に限らず、自分の好みに合った商品を選ぶことが生活を豊かにし、色々な個性のある商品があるから選ぶ楽しみも生まれるので、一軒でも多く、個性的な醤油をつくる小さな蔵が残る必要性があるのではないか、「木桶」自体は昔ながらの技術だが、醤油づくりを続けるために新たに導入するということは、原料から商品化までのすべてのプロセスを一つの醤油蔵で行うという全国的に見ても少なくなった製造方法をこれからも続けてゆくという意思表明でもある、と六代目の修さん。
井上本店の今後

七代目の遼さんは、社業を大きく拡大するというような野望はないが、今後、使用できないコンクリート槽が増えるから、桶も増やさないといけないだろうし、現在、木桶仕込みの醤油は、「木まじめ」1種類しかないが、種類を増やすことになるだろうし、また、ストレートつゆなどの加工品、関連商品も開発することにもなるだろう。昔ながらのつくり方というのは、良い面も悪い面もあって、衛生面はさらに改善できるところがあるので、より良い商品を作り続けられるよう、日々、アップデートをしていきたい、とおっしゃる。
次の代に向け、より良い商品をつくる挑戦を続け、楽しく仕事をしている姿を見せることが家業の継承には大事なことだ、と六代目の修さん。七代目の遼さんご兄弟もそのお考えを継承して、この先、何代も続く醤油づくりをしていかれるだろう。
COREZOコレゾ 「『受け継ぎ守るもの』と『進化し変えるもの』の両輪で 次の代に向け、楽しく仕事をする姿を見せ、木桶仕込み醤油への挑戦を決断した 全くの素人だった醤油づくりを引き継いだ六代目」である。
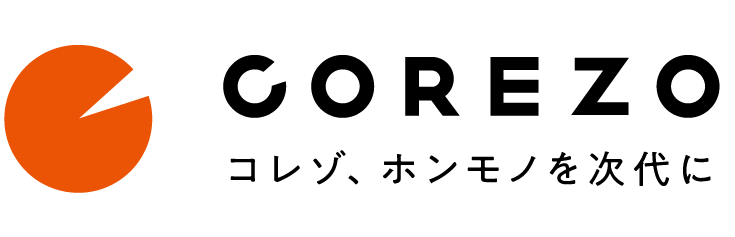
コメント