
目次
COREZOコレゾ 「唐揚好きが高じて『日本唐揚協会』を設立、大成功に導き、そのノウハウで社会問題の解決にも取組んで、おもしろいこと、楽しいことを盛り揚げ、日本を元気にする、協会ビジネスのプロフェッショナル」 賞

やすひさ てっぺい さん/ 一般社団法人日本唐揚協会 会長 兼 理事長/ケーアールジー株式会社 代表取締役

プロフィール
< 代表 >
一般社団法人日本唐揚協会 会長兼理事長
一般社団法人日本カレーパン協会 理事長
ケーアールジー株式会社 代表取締役
日本協会協会 会長
協会大學校 学長
< 役員 >
一般社団法人リフォーム管理士協会 理事
一般社団法人日本ビルインスペクション 理事
一般社団法人忍者サスケ協会 副理事長
< 応援 >
キッチンカー相談センター センター長
COREZOコレゾチャンネル
一般社団法人 日本唐揚協会
2016年、当財団の顧問を務めてくださっている岩村 敬(いわむら さとし)さんに同行して、スイスを訪れた際、在スイス日本大使館のイベントで唐揚げを揚げて提供された「日本唐揚協会」会長のやすひさてっぺいさんとご一緒したことがあった。
岩村さんから、今は、「日本唐揚協会」だけでなく、リホーム詐欺に遭って困っている人を無くそうと「一般社団法人 リフォーム監理士協会」や大規模修繕の初期調査から施工完了後のチェックまで一貫してサポートして、工事の透明性を高め、ビルオーナーのコスト最適化や品質確保を実現する「一般社団法人 日本ビルインスペクション協会」も運営しておられると伺い、久しぶりにお目に掛かってお話をお聞きした。
日本唐揚協会とは
やすひささんは、ふとしたときに無性に食べたくなり、挫けたり、苦しい時、悲しい時でも食べると自然に笑顔になって、元気を取り戻すと云うほどの無類の唐揚好き。
ビジネス上の付き合いがあった、日本唐揚協会現専務理事の八木宏一郎さんが事業で唐揚を始めたと云う話をされるので、当時、やすひささんが唐揚好きが高じて、ブログで唐揚の批評をしているのがバレたのかと思いヒヤヒヤして、噛み合わない話になったのだが、お互い、唐揚が大好きなことが分かった途端、一気に距離が縮まり、長年の親友のような関係になった。
唐揚げが人と人をつなぐパワーは半端ない、唐揚のファンクラブのようなものがあったら一緒に入りましょう、となって、どちらもIT業界だったのですぐに調べたが、当時、そのような団体は存在していなかったので、ならばつくりましょう、と云うことで、2008年、八木さんと二人で日本唐揚げ協会を設立した。
2010年に一般社団法人化し、現在、会員(=カラアゲニスト)数は25万人を超える規模になり、カラアゲニスト認定、からあげグランプリ、全国イベント、企業や地域とのタイアップなど、活動は多岐に渡るが、やすひささんは、主にシステムと会員管理、八木さんが企業との折衝、他にイベント関係1名、会員の問い合わせ窓口、フォローアップ等事務局業務に1名、計4名体制で運営していると云う。
日本唐揚協会の目指すところ
唐揚げを通じて世界平和を担う団体
私ども日本唐揚協会は、唐揚げを愛する人々の団体であるとともに、唐揚げを通じて世界平和を担う団体でもあると自負しております。
それは、やはり唐揚げを食べている人は、自然と笑顔になり怒ったり争ったりすることはありません。
これが、もし世界で同時に人類が唐揚げを食べたとしたらどんなことが起こるでしょうか?
そうです。 世界中が笑顔に包まれ、一瞬だけかもしれませんが、争いの無い、戦争の無い、平和な世界が訪れるのではないでしょうか?
私ども協会はそんな世界をいつも想像しています。
この平和な世界を実現する為には、まず唐揚げ文化を有する日本で、きちんと唐揚げを認識し、意識し、美味しさ、すばらしさを伝えられるようになること。 これができた時、まず日本から平和が訪れます。
そして、それがアジアから世界へ広がることで間違いなく世界平和を実現できるのです。
世界へ誇れる日本の「唐揚げ」が、世界へ飛び立ち世界の「KARAAGE」になること。
これができた暁には、唐揚げが世界を変える。
そんな可能性を秘めた食べ物。
それが唐揚げです。
カラアゲニスト
「カラアゲニスト」に認定されるメリット
唐揚げに対する愛が証明され、飲み会の席で唐揚げについてちょっと語れる。協会認定の証として、有料の「カラアゲニスト協会章」「カラアゲニスト免許証」「カラアゲニスト免許証」がつくれ、さりげなく「唐揚げ好き」をアピールできる。
唐揚げ好きの方が、「オレが、ワタシがカラアゲニストにならなくて誰がなるんだ」と云うモチベーションで認定試験を受けてくださる。そんな同じ想い、志の仲間が集まれる環境をつくった、とやすひささん。
「カラアゲニスト」認定試験
唐揚げに関する知識(「歴史」、「文化」、「地域的違い」、「正しいマナー」他)が一定水準以上(10問中7問以上正解)ある「唐揚検定」合格者を、日本唐揚協会が「認定カラアゲニスト」として認める仕組みで、日本唐揚協会公式サイトの「唐揚検定」ページからWeb上の筆記試験(選択式と記述式)でいつでもどこでも誰でも受験することができ、すぐに採点され、合否の判定と正解が届く。不合格であっても、何度でも受験でき、問題は同じなので再受験すれば全員合格するはずだが、実力で合格したいのか、3度、4度と受験する方もいらっしゃると云う。
「カラアゲニスト」認定試験問題
唐揚げの「正しいマナー」問題の一例として、「皿に添えられたレモンの使い方」等がある。
実際、 唐揚検定ページから受験してみたが、なんとか一発合格できた。
ファン協会とガチ協会
世の中にはファン協会とガチ協会とも呼ばれる資格系・業界団体系協会やNHKや日本大相撲協会のように公共性が高い公的協会がある。
ファン協会の目的は「共通の趣味・好き」を軸にした楽しみや文化の共有であり、親しみやすい組織。日本唐揚協会は、「唐揚げが好き」という共通の想いから始まったファン協会の代表例で、現在(2025年)、会員数が25万人を超え、日本最大級の「協会」として認識されていると云う。
ファン協会でも、同じジャンル内に団体がいくつもあると、まとまりにくいが、日本唐揚協会は他に団体ができても、皆んな唐揚げ好きなら、一緒にやっていこうと云う方針なので、排除や分断がない、とやすひささん。
からあげグランプリ
からあげグランプリの部門
「素揚げ・半身揚げ部門」「しょうゆダレ部門(東日本・中日本・西日本の地域別)」「塩ダレ部門」「手羽先部門」「味バラエティ部門(東・中・西日本)」「素材バラエティ部門」「チキン南蛮部門」「弁当部門」「スーパー総菜部門(東日本・中日本・西日本)」、各部門で審査を実施し、毎年4月に「金賞」「最高金賞」が表彰される。
「素材バラエティ部門」は、通常の鶏肉や衣の選択肢とは異なる素材(例:他の肉、魚介類、野菜)を用いた唐揚げを評価する部門。
審査方法の変更
2024年度までは、試食審査会を実施していたが、年々、参加店舗・業者が増えてきて、唐揚げファンが決めるグランプリの趣旨から足切りや絞り込むのもどうかと云うことで、2025年度(第17回大会)からは、認定カラアゲニスト全員による投票制審査を導入し、ファンが主体的に審査に関わり、より公平でリアルな意見を反映するシステムにリニューアルされた。
日本カレーパン協会
2013年、日本カレーパン協会は、任意団体として協会設立。2017年に社団法人化、カレーパンに関するWEB筆記試験に合格すると「カレーパンタジスタ」として認定され、現在(2025年)、会員数は5万人を超え、やすひささんが理事長で運営責任者だが、唐揚げ程好きではないので、会長職は、選挙で選び、協会活動を盛り上げるのが会長の役割だそうだ。
日本唐揚協会のビジネスモデル
ビジネスとしての日本唐揚協会は、従来からある広告収益型のビジネスモデルだが、経済の専門家からは、会員の集め方や広がり方が今までのファン団体とは違うと評価していただいていて、この仕組みをカレーパンに応用したところ、そのまま上手くいったので、再現性があることが実証できた、とやすひささん。
主にスポンサー収入により、協会運営されていて、日本唐揚協会は、粉、油、飲料他のメーカー、日本カレーパン協会は、チーズ、粉、カレーフィリング、油他のメーカーがメインの協賛企業とのこと。
興味があったので「日本唐揚協会のビジネスモデルとしての評価」をAIに尋ねてみた。
日本唐揚協会のビジネスモデルを評価すると、 ファン協会の枠を超えた「文化発信型ビジネスモデル」として非常に優れていることがわかります。主な特徴を整理しました。
強みと評価ポイント
1. 会費・検定料を取らない運営スタイル
一般社団法人でありながら、会費や検定料を徴収せずに運営されているのが大きな特長で、広いファン層の参入障壁が低く、信頼感とブランド力を高める基盤になっている。
2. 爆発的なファン獲得とメディア戦略
わずか数年で認定カラアゲニストは10万人→25万人と急成長し、会員数は世界最大級の規模で、「からあげグランプリ®」「テレビ出演」「大手企業との商品開発」など、多彩な露出でブランド認知を拡大。
3. イベント連動型のファン体験
年間イベント「からあげグランプリ®」により、ファンが審査員として参加できる透明性の高い仕組みを構築し、さらに「リアルファンによる審査制度」に改革して、ファン参加型イベントとしての価値を高めている。
4.スポンサーモデルによる安定的資金基盤
一般的な会費制ではなく、B2B型のスポンサーモデルを採用。大手企業(例:ローソンのからあげクンなど)との協業で資金調達を行い、会員への返礼義務を回避しながら持続可能な運営を実現。
5. FC展開による店舗および地域経済の支援
金賞受賞店舗の味を他地域へ広げるための からあげシェアードFC を導入し、受賞店・協会・飲食店・ファン(四方よし)の関係性を築き、新たな市場価値を創出。
6. 地域振興および観光貢献への取り組み
「中津市」を“唐揚げの聖地”として観光振興に活用して、自治体とも連携したまちおこしを実施。映画「カラアゲ★USA」でも協力するなど、地域文化との接続を促進。
評価まとめ
項目;評価内容
無料モデル;会員・認定制度に費用をかけず、多くのファンを取り込む
ブランド戦略;メディア・商品開発・イベントでブランド力を強化
ファンエンゲージメント;審査参加・免許証・コミュニティづくりで愛着を醸成スポンサーシップモデル;自主運営しやすいB2B型資金調達戦略
実業展開;FC事業・IOT店舗とファンをつなぐ実用的展開
地域連携;観光・映画・地方創生と連動した文化の社会実装総括
日本唐揚協会のモデルは、「好き」という感情を起点にした文化的な取り組みが、実利的なビジネスモデルへと昇華しており、非常に高い評価に値する。ファンを巻き込み、社会・経済・文化の多面で成果を上げている点が、他のファン協会と一線を画する強み。
日本唐揚協会成功の要因
先ず、日本には唐揚げ好きが多いと云う、唐揚自体が持つパワー。また、やすひささんがシステム開発やWebマーケティングの仕事をしていることもあり、ネットの隆盛と共に後押しされたこと。
そして、唐揚協会の設立は2008年だが、盛り上がったのは2011年以降のことで、東日本大震災後に日本人の意識のパラダイムシフト(これまで当然とされてきた考え方や価値観、枠組みが劇的に変化し、新たな常識や方法が定着する現象)が起きたこと。
それまでは、お金こそが一番の価値基準で、勝ち組、負け組の世界だったけど、震災以降は、自粛、自粛の後、繋がりとか絆とか、人との関係性が重視されるようになり、他人が好きなものや共感性を否定しなくなった。実際、唐揚協会を立ち上げた当時は、唐揚が好きと云うと、「子供か」と笑われたのが、「私も好きなんです」とおっしゃる方が増え、世の中の意識、環境が変わった。
臆することなく、自分の好きなものを好きだと云えるようになり、共感が共感を呼んで、日本唐揚協会も世の中に認められるようになったのではないか、とやすひささん。
資格系・業界団体協会
日本唐揚協会の成功により、資格系・業界団体協会の設立、運営の問い合わせや依頼が入るようになった。
一般社団法人 日本ビルインスペクション協会
建物が老朽化しているのに十分なメンテナンスができていないため、外壁タイル他の落下で、傷害事件が発生する等が社会問題になっているが、なんとかできないか、と個人の方から相談があり、やすひささんは、一から勉強をして「一般社団法人 日本ビルインスペクション協会」を設立したそうである。
最新技術を駆使して信頼性高い建物調査を提供する第三者機関として、コストと安全性のバランスを重視し、技術と透明性に裏付けられたサービス提供して、快適で安全な建築物の環境維持に貢献し、広く社会に資することを目的に設立された。
具体的な調査技術の特徴として、建物外壁や屋上の状況を非接触で広範囲にスクリーニング診断する「ドローン+赤外線調査」は、足場不要、高所や隠れた劣化の発見が可能で、安全性とコスト効率に優れ、ドローンで検出された異常個所に対して、専門作業者がロープを使い直接詳細を調査する「ロープアクセス打診調査」も、足場なしで精密な劣化確認が可能で、無駄な工事コストを削減することができるとのこと。
一般社団法人 リフォーム監理士協会
リフォームの請負金額が500万円(税込)未満の工事であれば、「軽微な工事」に該当し、建築業法の建設業許可制度において認められているため、建設業の許可は法律上は不要なので、誰でも請け負うことができるそうだ。
「無料診断します」と屋根に上がって、故意に瓦を割って、屋根修理、床下に入って、シロアリは発生していないのに虚偽の調査報告を受けて被害に遭った、と云うのはよく聞く話だが、「リフォームの不正を無くす」ことからスタートした。
宅地建物取引業者(宅建業者)は、不動産の売買や賃貸契約成立前に、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士(宅建士)の資格を持つ者が、書面(重要事項説明書)を交付して取引に関する重要な事項を説明する義務があるが、リフォーム工事契約時にはこのような義務がないことが問題ではないか、民間が主導してでも説明できる資格制度は必要だと考え、資格制度と認定する団体「一般社団法人 リフォーム監理士協会」をつくった。
国交省は、一定の基準を満たす民間資格を「国土交通省登録資格」として制度的に登録・評価する仕組みを整えていて、これらの資格保有者は、公共工事の入札において企業評価の際に加点されることがあるなど、実務的なメリットもある。
2014年度制度導入以来、現在では、BIM/CIM管理技士(建設情報技術分野)、地籍調査関連技術者資格(地籍調査分野)、舗装診断士(調査・設計分野)、ドローン測量管理士(UAV測量分野)他、約389件にのぼる民間資格が登録されているので、一般社団法人 リフォーム監理士協会の資格も世間の認知度が上がり、必要な資格と認められれば、登録される可能もあると云うことだ。
やすひささんは、協会運営のプロとして世の中の問題解決に関われるのは嬉しい限り、とおっしゃる。
協会を設立・運営する醍醐味、メリット
ルールを決めることができる
例えば、チキンナゲットは唐揚げか否かについては、どちらでもいいことだが、2009年に定めた日本唐揚げ協会の唐揚げの定義は、粉をつけて油で揚げたものなので、日本唐揚げ協会の見解としては、唐揚げになる。
日本唐揚協会の規模がどんどん大きくなって、唐揚げのことならなんでも知っていると思われて、いろいろ尋ねられるので、仕方なく決めていたのだが、世の中のルールって、こんな風に決まるのかと云うことが理解できた。
また、唐揚げ協会では、唐揚げが盛られている皿は公共の場であるという立場で、それは、やすひささん個人の見解でもあるのだが、10年も経過すると、それが世間でも主流の考え方になる。「協会」という組織団体はそんな力を持っている。振り返ってみると、「株式会社」だとこうはいかなかっただろう。これから協会を設立・運営される方には、その分野でのルールを決めることができるようになることも頭に置いてもらえたら、とやすひささん。
「株式会社」は、営利を目的とし、利益を株主に配当することが前提の法人に対し、「一般社団法人」は、特定の目的のために集まった「人々の集団」に法人格を与えた法人形態を指し、原則、非営利で、利益(剰余金)を構成員に配当できないが、定款や社員総会の決議により、役員報酬や従業員給与は支払えると云う違いがある。「社団法人」、「協会」と云う名称には、「営利より社会貢献や公益性を重視する」と云う世間一般のイメージもあると思う。
実際に「チキンナゲットは唐揚げなのか?」AIに尋ねてみると、しっかり「日本唐揚協会」の見解も反映されている。
「チキンナゲットは唐揚げなのか?」という問いについて、以下に日本唐揚協会および一般的な定義に基づいてお答えします。
日本唐揚協会の見解
一般社団法人 日本唐揚協会では、「唐揚げ」を次のように定義しています。
食材に片栗粉や小麦粉などをまぶして揚げた料理すべてを「唐揚げ」とみなす。パン粉使用のフライはカツに、 水溶き小麦粉は天ぷらとして分類する。
チキンナゲットについては、一般的に小麦粉や薄力粉で衣をつけるため、「唐揚げと定義しています」つまり、日本唐揚協会としては、チキンナゲットも唐揚げとして扱ってよいというスタンスです。
調理法に基づく一般的な比較
唐揚げ:食材(例:鶏肉)をそのまま小麦粉や片栗粉で揚げる料理。味の付け方や衣の種類によって多様な派生があります
チキンナゲット:肉(鶏むね肉・もも肉など)を細かく刻んだりミンチにし、一口大に成形したものに衣をつけて揚げたもの
この違いは調理プロセスに由来し、形状や味わいの印象の差にもつながります。
まとめ
観点 結論
日本唐揚協会の定義 チキンナゲットも唐揚げに含む(小麦粉等使用の揚げ料理として)
一般的な違い 唐揚げ:原形の食材を揚げる / ナゲット:挽肉を成形して揚げる
ニュアンス 技術的には唐揚げの派生形とも言えるが、家庭では別カテゴリとして認識されることが多い
つまり、 協会的にはチキンナゲットも「唐揚げ」の範疇ですが、一般にはその調理方法の違いから、別ジャンルとして認識される場合が多いというのが本音の結論です。
今後のやすひささん
やすひささんご自身の感性や感覚に共感してくださる方がいらっしゃれば、協会設立・運営のお手伝いをしたい。
実は、協会自体、世の中に沢山あるが、一人協会とも呼ばれる、個人が勝手に立ち上げた協会は、勝手に萎んでいくし、一生懸命やってみたけど、上手く行かない協会も多いが、少しテコ入れするだけでもっと伸びる可能性がある。おもしろいことをやりたいと云う方には、ファン協会のノウハウを提供するので盛り上げていただきたい。
ファン協会を盛り上げるには、先ず、1,000人の壁というのがあり、それを超えるといろんなことができるようになる。それまでは、協会としては半人前以下なので、やれるだけでいいや、と云う独りよがりの協会が多い。
世の中に広めたいなら、世の中に受け入れられるように、仲間を1,000人以上集めて、組織体として見せる必要がある。1,000人なら、気合と根性で集められるので、そこを突破すれば、次のステージに上がれる、とやすひささん。
「ファン協会」や「ファンコミュニティ」においてよく語られる「1,000人の壁」とは、ファン1000人という規模が個人や小規模団体にとって持続可能なビジネスやコミュニティ構築の一つの目安になるという理論のこと。
1. ケヴィン・ケリーの「1,000人の真のファン理論」
テクノロジー哲学者ケヴィン・ケリーが提唱した理論で、「たった1000人の“真のファン”がいれば、クリエイターは独立して生計を立てられる」とされる。
真のファンとは、遠方でもイベントに来てくれる、全ての作品を購入してくれる、継続的に支援してくれる熱心なファンを指し、例えば、1人あたり年間1万円の支援があれば、総額1,000万円に。月額1,000円課金なら、毎月100万円、年間1,200万円となる。
2. 現代のコミュニティ運営では「30〜50人」が最小限の盛り上がる規模
特にオンライン上でのコミュニティ運営においては、最初に30〜50人のファンが集まると自走的な盛り上がりが期待できるという実運用からの経験的な指針も出されている。
つまり、「1,000人の壁」は、ファン協会が組織として持続可能になるための目指すべき規模の一つとされる理論的指標。
ゼロの状態からスタートする場合、まずは数十人のコアメンバーが集まることがコミュニティを動かす“最小限の出発点”で、その後、真のファンを1000人規模まで育てることで、収益性や継続性が見えてくる。
日本唐揚協会のビジネスモデルは、上記で引用された会費制モデルとは異なり、会費ゼロで「唐揚げ好き」が気軽に参加できる設計と、印象的な名称によって会員登録のハードルを下げ、無料の会員制度によるコミュニティを拡大したが、B2B型のスポンサーモデルを採用して、大手企業との協業で資金調達を行い、会員への返礼義務を回避しながら持続可能な運営を実現しておられる。
「からあげグランプリ」他、ファン参加型イベントで、
資格系、業界団体運営協会に関しては、その良さを伝え、世の中に広める手法、マーケティングが上手くないケースが大半で、良いものを持っていることが大前提だが、世の中に知ってさえもらえれば、盛り上がるので、そこを重点的にテコ入れすること。協会の理念と云うか、運営の考え方が根本にあって、それが問題になっていることも多いが、協会運営のやり方を変えることで考え方も同時に変えることができる。
協会運営で困ってる方々、協会を設立しようとしている方々にこれまで蓄積してきたノウハウを誰にでも実践可能なカタチにして提供し、盛り上げることが使命と考えていて、唐揚も世界にも少しづ広がっているが、自分たちが好きな世界や困っていることを改善する仕組みを世の中に広げ、さらに日本の良さを海外にも知ってもらう足掛かりになるようなお手伝いをしていきたい。
一つでも多くの世の中の問題を解決し、おもしろいこと、楽しいことで盛り上がれば、日本を元気にする原動力になる、とやすひさん。
まとめ
唐揚は、最期に食べたい料理ではないが、好きな料理の一つだ。唐揚が嫌いな人は少ないだろうけど、唐揚好き、唐揚愛から日本唐揚協会を立ち上げ、巧みな運営戦略によって、現在(2025年)、会員数が25万人を超える、日本最大級の「協会」に育て上げられた。
さらに、「からあげグランプリ」他のファン参加型イベントでは、店舗側はファンを増やしたい、ファンは贔屓の店舗を応援したいというニーズが一致して、盛り上がることで、サプライヤーである粉や食用油メーカーも潤って、スポンサー協賛やコラボ商品の開発協力依頼などで、協会運営資金が確保でき、業界全体が盛り上がり、潤う仕組みが構築されている。
今回、やすひささんから直接お話を伺って、「日本唐揚協会」という名称自体が非常にインパクトが強く、「唐揚げの専門的な知見を持つ団体感」が自然に醸成されるネーミングとブランド戦略、無料で「唐揚げ好きなら誰でも参加OK」の開放されたコミュニティ戦略、参加型のイベント展開や検定・投票などで関与を促進しての会員拡大、店舗とコミュニティ双方で「満足度を上げ続ける」取り組み、そして、東日本大震災以降、人々の価値観は「お金」や「モノ」から「感動」や「つながり」へと変化したことから、時代の空気にマッチングした「体験の提供」や「感動の共有」を重視したマーケティング戦略など、とてもよく考えられたすごい団体であることを再認識させてもらった。
やすひささんが日本唐揚協会の会長兼、理事長であることは存じ上げていたし、度々、TV番組等でも拝見し、日本唐揚協会は、何だか、ユルくて、おもしろそうな団体の印象だったが、個人的には、何よりも、思わず参加したくなる、この楽しそうな雰囲気と唐揚が好き、唐揚で盛り上がりたい、と云うシンプルなメッセージこそが成功の要因だったのではないかと拝察する。
そのノウハウを応用して、社会問題の解決にも取り組んでおられることに敬意を表すとともに、一つでも多くの世の中の問題を解決して、おもしろいこと、楽しいことで盛り上げ、日本を元気するだけでなく、さらに世界平和の実現にも貢献していただきたい。
COREZOコレゾ 「唐揚好きが高じて『日本唐揚協会』を設立、大成功に導き、そのノウハウで社会問題の解決にも取組んで、おもしろいこと、楽しいことを盛り揚げ、日本を元気にする、協会ビジネスのプロフェッショナル」である。
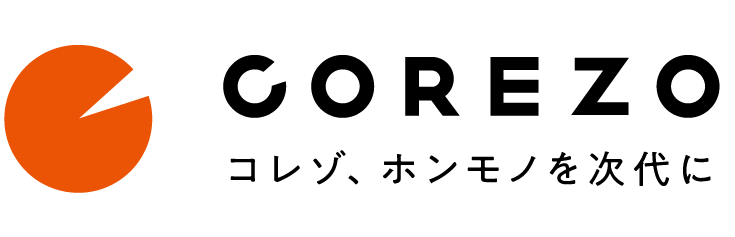
コメント