
目次
COREZOコレゾ 「『全国木橋サミット』他を通じて、木橋・吊り橋の魅力と活用方法を広く伝え、維持管理の意識と質の向上を図り、今や希少となった木橋・吊り橋を守り育て、後世に継承する、木橋研究の第一人者」 賞

渡辺 浩(わたなべ ひろし)さん/福岡大学 工学部 教授/全国木橋サミット世話人代表

プロフィール
福岡市城南区
専門分野;橋梁, 木橋, 木材利用, 市民防災
長年耐震構造物を研究し、構造物を強くするだけでは震災を抑えることはできないことを痛感した経験から、市民が積極的に関わる防災まちづくりについての研究に取り組んでいる。東日本大震災等の被災地に通い、復興とそれに関わる人々との繋がりを通じてその答えを見つけ出そうとしている。
国内に豊富に蓄積している資源でありながらも積極的に活用されていない木材を外構構造物に活用するための研究を進めている。全国の木橋の耐久設計・施工から健全度診断・補修に関わっている、この分野では国内で稀少な研究者である。
COREZOコレゾチャンネル
全国木橋サミット

令和7年1月に開催された「第6回全国木橋サミット in岩国」に参加された季楽里龍神の小川さださんから「全国木橋サミット」と云う、おもしろい活動があると紹介され、タイミングよく、大阪で、渡辺 浩(わたなべ ひろし)先生と山脇 裕(やまわき ひろし)さんのお二人にお目に掛かることができた。
福岡大学 工学部 教授の渡辺 浩(わたなべ ひろし)先生は、鉄の橋、コンクリートの橋から木の橋と橋全般を研究されてきたが、木の橋の研究者はほとんどいないので、珍しい部類だとおっしゃる。
株式会社特殊高所技術 建機事業部 部長他の肩書をお持ちの山脇 裕(やまわき ひろし)さんは、主に橋の点検調査、保守設計の仕事をしておられ、吊り橋の点検調査等で和歌山県田辺市龍神村には頻繁に訪れておられることから、「第6回全国木橋サミット in岩国」のパネルディスカッション「木橋の魅力を後世に継承」に、龍神村にある「佐久間橋」のパネラーとして登壇された。
山脇さんが業務として和歌山県田辺市龍神村の木の橋に関わった際に、橋業界では木の橋の第一人者として有名な渡辺先生に連絡して指導を受け、それ以来、木の橋に関する業務で不明なことがあれば相談されている。
道路橋点検士の資格があれば、大抵の橋の点検ができ、自治体が管理する木橋の点検、補修では、木橋自体が少ないため、自治体の担当者の認識不足と「木橋診断士」の資格者不在だったり、木橋の知識や経験の乏しい業者が競争入札で受注し、実施してしまうケースも多く、木橋が他の橋とは異なることを十分理解できていないことに起因する問題が生じているそうだ。橋に関する資格を持ち、吊り橋をはじめさまざまな橋の点検を行なってきたプロなのに、木を使った橋のことはよく分からないので教えて欲しい、と連絡してきた山脇さんを真面目そうな人だな、と感じた渡辺先生は、それ以降、懇意にされているとのこと。
全国木橋サミット2017 inつるた
2017年、「全国木橋サミット2017 inつるた」が第1回目として開催された。青森県北津軽郡鶴田町から、町内にある木造橋「鶴の舞橋」を老朽化により大改修をすることになり、そのキックオフとして、大規模改修に至る経緯と必要性、その効果他の広報も兼ね、シンポジウムを開催したいと渡辺先生に依頼があったので、「全国木橋サミット」というタイトルにして、声掛けをしたところ、木橋を管理する全国の自治体からの参加があり、木橋の魅力や維持管理他を話し合う場となった。
鶴の舞橋
「鶴の舞橋」は、青森県津軽平野のほぼ中央に位置する鶴田町にあり、1994年7月8日、岩木山の山影を湖面に映す津軽富士見湖(廻堰大溜池)に架けられた。総ひば造りで、橋脚には樹齢150年以上の青森ひば700本を使用し、全長300m、木造三連太鼓橋としては日本最長。2023年9月に改修工事が始まり、2026年3月、完成予定。

「全国木橋サミット」がシリーズ化
その時、参加くださった会津若松市さんが来年はウチでやろうと手を挙げ、その次は岩国市さんと、そのつもりもなかったのにシリーズ化することになり、「全国木橋サミット」と木橋に関する情報発信をするWebサイトを立ち上げた。渡辺先生は、「全国木橋サミット」世話人代表として、現地実行委員会のお手伝いと木橋の発展に関する活動をしておられる。
全国的に希少となった木橋を管理する自治体による意見交換の場として、毎回、講演会またはパネルディスカッション、意見交換会と見学会を開催し、木橋の専門家が集うことで維持管理のレベルアップを図ってこられた。
こうして、「全国木橋サミット2018 in会津」、「全国木橋サミット2019 in岩国」、「全国木橋サミット2022 in加賀」、「全国木橋サミット2023 in三好」と順調に続いたが、三好市さんの後、積極的に引き受けてくれる自治体がなくなり、サミット継続が危ぶまれたため、無理を承知の上でお願いして、岩国市さんに2回目の開催を引き受けていただいた。
それまでのサミットでは、サミットそのもの意義や価値が変わるような心配があったので、観光を前面に出さないようにしていたが、「第6回全国木橋サミット2024 in岩国」では、これがラストチャンスかもしれない、との思いもあって、参加自治体がポスターで自身の木橋を紹介するコーナーを作ったことと観光PRもOKにしたところ、ずいぶん参加者が増え、登壇者のプレゼンが盛り上がって楽しい場になったそうだ。
岩国市さんでの盛況を受けて、「全国木橋サミット2025 in函館」、「全国木橋サミット2026in京丹後」と開催が決まり、その先も開催に興味を示してくださる自治体さんが現れ、しばらくは存続の危機から遠ざかれそうでうれしい、と渡辺先生。
木橋技術協会
木橋技術協会は、木橋づくりに携わるメーカー13社により設立され、現在は、木橋に関する技術の向上に取り組む企業、個人が参加する団体になっている。
木橋は、メンテナンスが主流の時代となり、木橋技術に関する情報の発信、「木橋点検マニュアル」や「木橋定期点検要領(案)」の発刊、「木橋診断士」の資格の認定制度等、木橋の点検やメンテナンスができる人材育成がメインの活動で、渡辺先生は木橋アドバイザーを務めておられる。
木橋の定義
法的な定義も業界での定義もなく、木橋(もっきょう)は、構造から全てが木でできているものであり、吊り橋は鉄製のワイヤーロープを張っているので、木橋でないと云う方もおられるが、渡る際に足場となる踏板等に木を使っていて、それがないと渡れない吊り橋は木橋で良いのではないか、と云う渡辺先生のお考えから、木橋サミットでもそんな吊り橋も木橋として捉えられている。
実際、「全国木橋サミット2023 in三好」は、「祖谷のかずら橋」が有名な徳島県三好市で開催されている。「祖谷のかずら橋」は、橋全体が「しらくちかずら」で覆われ、踏板にも木材が使用されているが、安全のために床板や手すりなどの主要な部分に鋼線ワイヤーが使用されていて、橋の支えには地中の岩盤に固定されたグラウンドアンカー工法(高強度の引張材を地盤に定着させ、緊張力を与えることで、法面や斜面の安定を図る工法)が導入され、敷綱は太いワイヤロープに交換されており、3年ごとの架け替え時には専門家によるワイヤーロープの定着確認や点検が行われているそうだ。


京都嵐山の渡月橋は、欄干や桁隠しを木製にすることで、一見、木造橋のように見えるが、鉄筋コンクリートを主体とする構造の橋で、このような木で化粧をしたり、木材のように塗装している鉄や鉄筋コンクリート製の橋が増えていて、これは渡辺先生のお考えでは木橋ではなく、一部に木を使った木橋よりも数は多いだろう、とのこと。

木橋の特徴
木材は、身近にあることから、古くから建設材料として利用され、木橋もたくさん架けられてきた。木橋は、木材の性質から長い橋や強い橋には不向きであり、耐用年数も長くないので、今では、木の橋は、お金が掛かる、手間が掛かると云うことで、鉄やコンクリート製の橋が主流となり、新しく架けた吊り橋も、踏板には木を使わず、鋼板を使っているものが多くなっている。
木橋も設計次第では長い橋や強い橋をつくることができ、しっかり手入れすれば耐用年数も長くなるが、何よりも、木橋はその存在そのものが絵になるので、実際、観光スポットやランドマークになっている木橋も多く、風雪に耐え、経年変化で色が変わって風格が増すのも木橋ならではの特徴、と渡辺先生。
木橋の数
さて、一体、日本全国には、木橋はどれぐらいあるのだろう。道路法上、道路橋として指定されていたら公表されているのでカウントできるが、電力会社が管理する送電線の設置調査や点検用、林業組合等が架けた林業用等、自治体が管理していない吊り橋や道路に指定されていない橋もあり、それらはカウントできない。
渡辺先生が運営しておられる「木橋資料館」と云うWebサイトには、ご自身が実際に訪れて撮影された国内外の多数の木橋の画像が掲載されていて、山脇さんも全国を仕事で巡りながら撮影された木橋の画像を山のようにお持ちでご自身のインスタグラムで公開されている。
渡辺先生は、全てが木でできた木橋は、ご自身が確認されただけで数百あるので、千ぐらいはあるのではないか、山脇さんは、人道用吊り橋全体で約800、その内、一部が木でできた木橋は、5〜600はあるだろう、と推計されている。
観光資源としての木橋
木橋・吊り橋を残していくには、管理する自治体が木の橋を前向きに捉えているかどうかが一番大きな問題。サミットの第一義は、全国的に希少となった木橋を管理する自治体による意見交換の場であり、維持管理のレベルアップを図ることであるが、観光PRを解禁した「第6回全国木橋サミット in岩国」での盛況で、木橋を観光資源として捉えている自治体も多く、一般参加者の関心も高いことが分かった、と渡辺先生。
龍神村にある「佐久間橋」のパネラーとして登壇された山脇さんは、観光資源としての魅力のプレゼンしかされなかったそうで、木橋・吊り橋の維持管理と存続には、観光資源として活用することが一つの選択肢となる可能性が大いにあるし、木橋を守り育て、後世に継承するには、維持管理のレベルアップと同時に多くの一般生活者にその存在意義や価値に関心を持っていただくことも必要ではないかと思う。
サミットでよく話題に上がるのが、木橋の保守点検、維持管理の費用をどう捻出するかで、徳島県三好市の祖谷のかずら橋や岩国市の錦帯橋は観光施設として料金を徴収しているが、募金箱を置いたら盗難が…云々、自治体の皆さんの心配は絶えない。
募金箱を置いている木橋もあるが、鶴田町の「鶴の舞橋」は誰も気付かないようなところに設置されていて、以前はそんなに集まってなかっただろうと思うが、北海道新幹線開通時のキャンペーンで有名女優さんがその橋の袂に佇んでいる写真がポスターになると、その女優さんのファン世代の皆さんが大挙して訪れるようになり、「こんな良い橋、どうしてお金を取らないの」と云う声もあがって、募金箱が溢れるほど募金が集まるようになった事例もある、と渡辺先生。
何かのきっかけがあれば、木橋も注目され、その立ち位置も変わると云うことだろう。
錦帯橋は道路法上の道路ではない
岩国市の錦帯橋は市道であったが、自治体が隣に別の橋を架けたことで道路法上の道路の指定を解除して、観光施設として維持管理されており、維持管理費用を賄うため、入橋料が徴収されている。徳島県三好市の祖谷のかずら橋も3年に1回架け替える費用は、入橋料で賄われている。橋を有料にするには、道路であれば、有料道路にする方法があるが、道路の指定を解除して、観光施設として維持管理した方がハードルが低い、と渡辺先生。

吊り橋の特徴
「祖谷のかずら橋」は、諸説あるが、地域の平家落人伝説の伝承にも残っているほど古くからあったものと推測され、吊り橋が面白いのは、元々、吊り橋は、川の向こうの対岸にどうやって渡ろうかと考えて思い思いに架けたものだから、全部カタチが違うところで、人々の生活に根ざしているのが魅力。
使っている人にとっては日常生活になくてはならない生活道路だから、何かあったら困ると云うのが管理する自治体の立場。観光利用には、観光客が利用時に悪ふざけをしたりしてケガをすることが心配で、使い方が悪いのに、管理者に責任が及ぶこともあり、どうしても管理者である自治体は消極的になるので、その対策をどうするかと云う課題もある、と渡辺先生。
観光資源としての吊り橋の魅力
徳島県三好市の「祖谷のかずら橋」の年間集客数は、年間約35万人(2023年)、奈良県十津川村の「谷瀬の吊り橋」には、推定、年間約16万人が訪れる十津川村の主要な観光スポットとなっている。こちらは道路橋なので、通行料は無料だが、路線バスの便は僅かしかなく、クルマか貸切バス利用となるため、駐車場を整備して、駐車料を徴収している。

吊り橋は、観光客がわざわざ渡りに来てくれる程、観光資源としての魅力がある、と云える。
和歌山県田辺市龍神村の吊り橋
前述したように吊り橋は全国に約800あると推定され、その内、日本一面積の広い村として知られる奈良県十津川村には、6〜70、和歌山県古座川町に20弱、和歌山県田辺市全体で70〜75、龍神村だけでも約35あるそうだ。
山脇さんは、それらの吊り橋の点検調査のため、和歌山の龍神、田辺、川湯辺りで一年のうち数ヶ月は滞在しておられ、2005年の市町村合併後、龍神村の急激な人口減少と過疎化を間近にご覧になられてきて、地域活性化のため、観光客を増やし、交流人口を増やすには、吊り橋を観光資源として利用するのも一つの手ではないか、龍神村のように一つの地域にこれだけの吊り橋があるのは全国でも珍しく、観光資源として捉えるとビジネスとしていろんなことが考えられる。吊り橋群として、土木学会「選奨土木遺産」の公募に応募してはどうか、認定されると、「ダムマニア」ではないが、一定数の「土木遺産マニア」が存在するので、注目度が上がることは間違いない、とおっしゃる。
土木学会「選奨土木遺産」
「選奨土木遺産」とは、2000年、土木遺産の顕彰を通じて、歴史的土木構造物の保存に資することを目的として、社団法人土木学会が創設して認定制度で、社会へのアピール、土木技術者へのアピール、まちづくりへの活用、失われるおそれのある土木遺産の救済等の促進が期待されるとのこと。
認定されるとWebサイトに掲載され、過去には、冊子も刊行されたと云う。
佐久間橋
中でも、龍神温泉の上流、国道371号線沿いの日高川に架かる「佐久間橋」は、珍しい、2径間(橋の構造において、支点と支点の間が2つある)の 吊床版橋(ワイヤロープを床版に沿って両サイドの橋台に張り渡しで橋を支える構造で、塔柱や吊索がない)で、 構造的によく揺れる橋なので、地域では最恐の橋とも呼ばれているそうだ。


しかし、地元の観光に携わる人に話しても、あの吊り橋のどこがおもしろいの?何が魅力なの?と云う反応で、昔から当たり前にあるものなので、地域の人々が観光資源として認識できていない現状もある、と渡辺先生。
木橋を守り育てていくために
木橋を増やす
元々、地元で簡単に手に入る木材でつくられてきたのが木橋で、吊り橋を架けるのに必要な費用は、両岸の地盤の強度によっては支柱を立てなくて済む場合(例;前出の「佐久間橋」)もあり、長さによっても異なるが、100万円/mが目安なので、人が渡るだけなら、鉄筋コンクリートで架けることを考えると圧倒的に安いそうだ。
渡辺先生の研究室では学生の皆さんと設計して木橋のリニューアルをされた。踏板を簡単に交換できるよう工夫し、木橋の維持管理コストも抑えることができるそうで、木橋、木を使った吊り橋を残すには、木橋を増やすことが一番と、木橋を増やすことも含めて、研究、活動を続けておられる。

既存の木橋の維持管理
コンクリートや鉄だとすぐに取り換えられないが、木ならそれが手軽にできて、木は地元でも手に入り易く、部材を生産できるし、草木が生い茂ると木部が腐り易くなるので、橋の両端部の草刈りも地元の業者に任せば、地域経済の活性化にも寄与できる等々のメリットがある。また、木材はプラスチックより優れたところも多く、両端部の5mだけでも脂分が多くて腐りにくい木材の赤身(心材)を使うとか、少し目線を変えて工夫することで、維持費を抑えることができる、と山脇さん。
木橋・吊り橋を観光資源として利用するには
廃止したくてもできないジレンマ
主に吊り橋があるのは、山間部であり、過疎化が進む地域で、道路行政は、住民中心なので、人口が少ないところには、お金を掛けたくない、廃止したい、となるが、人口減少が続いても、何かの理由で1人が月に1回使うだけでも、無くなったら困る住民が1人でもいる限り、廃止したくてもできないので、維持管理費がかかる。ならば、その費用を賄える方法を考えなければいけない、その吊り橋の要不要、必要ならどうするか、を地域住民に委ねるのも一つの方法だが、地域住民も一枚岩ではない。
ただ、吊り橋が架かっているのは山間部だから、道路として捉えると、住民がいなくなっても、山仕事はあるし、治山点検用に必要かもしれない、登山者や渓流釣りの釣り人が利用しているかもしれないし、実際、電力の送電線の点検に利用されている実例もあり、そのような用途でも使われている限り、無くすことはできない。
維持管理費捻出方法の検討
渡るためだけなら鉄やコンクリート製の橋に任せておけば良いことなので、まずは、木の橋を木の橋だと認識してもらい、渡ることにワクワクできる橋、先に何も無くても渡ってみたい橋、渡ること自体が楽しい橋、そんな木の橋がせっかくあるのだったら、見にきてもらい、渡ってもらう工夫してみてはどうか。
木橋、吊り橋が有名になって、観光客が吊り橋を棄損したり、利用時に悪ふざけをしてケガをしたり、使い方が悪いのに、管理者に責任が及ぶこともあるので、管理者である自治体は消極的になるのは理解できるが、橋自体が稼げるようになると維持管理費も捻出できるようになる、と渡辺先生。
せっかくある木橋・吊り橋の活用
「1人以上で渡るな」(えっ、誰も渡ったらダメってこと?)と渡り口に掲示されている吊り橋もあるそうで、観光用として利用する場合は、最低2人は渡れるようにすることが必要だが、行政は、万一、事故が起こった時の責任は回避したいということだろう、橋の専門家である渡辺先生、日々、点検調査業務をしておられる山脇さんは、「1人しか渡れない吊り橋はまずない」、耐荷重は構造と地盤調査をすれば確認できるとおっしゃる。
勿論、地域外から訪れた方々が無茶をしてケガをするような行動をとらないようにする対策は必要だが、行政や観光協会とは関係のない吊り橋マニアのような個人や団体が情報発信することは抑止できないし、人道橋は住民だけでなく、観光客でも誰でも渡れるので、その吊り橋を渡りたいと訪れる人々を規制することもできない。ならば、地域と行政、民間の観光事業者他が一体となって、せっかくある木橋・吊り橋の今後のあり方、観光資源として利用する他の活用方法を検討するのが一つの方法、と渡辺先生と山脇さん。
吊り橋効果
揺れる吊り橋を渡るような状況下で感じるドキドキ感を恋愛感情の高まりによるドキドキ感と錯覚して、一緒に渡っている相手のこと魅力的に感じやすくなることがあると云う心理現象を指す「吊り橋効果」なる現象があるそうだ。そういえば、老いも若きもキャッキャと歓声を上げ、楽しそうに吊り橋を渡るカップルをよく目にするので、そう云う人もいるのかもしれないし、観光目的なら一人より二人以上で渡るものなのだろう。
まとめ
今回、渡辺先生と山脇さんのお話を伺い、以前、観光庁さんから委託を受けた調査事業で、徳島県三好市に滞在して、「祖谷のかずら橋」だけでなく、大歩危・祖谷地区に数多く存在する吊り橋も観光資源として調査したが、吊り橋を渡ること自体は勿論、「渡った先に何があるのだろう」と云う、ワクワク感を思い出した。吊り橋は、マニアでなくても、見るだけでもワクワク感が、渡る時にはドキドキ感が湧いてくるし、山間にあることがほとんどなので、風光明媚な場所にあることが多く、写真撮影スポットでもある。

渡辺先生には、これからも「全国木橋サミット」他を通じて、木橋・吊り橋の魅力と活用方法を管理する自治体、関係業者だけでなく、広く一般の方々にも伝え、維持管理の意識と質の向上を図り、木橋を増やして、木橋・吊り橋を守り育て、後世に継承していただきたい。
COREZOコレゾ 「『全国木橋サミット』他を通じて、木橋・吊り橋の魅力と活用方法を広く伝え、維持管理の意識と質の向上を図り、木橋を増やして、木橋・吊り橋を守り育て、後世に継承する、木橋研究の第一人者」である。
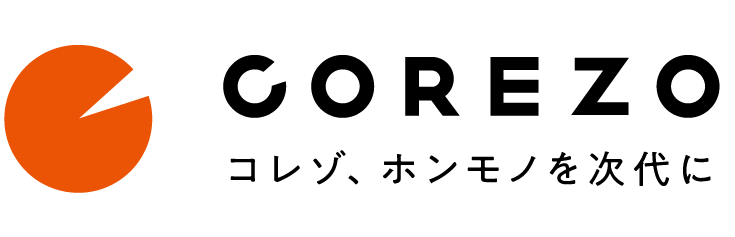
コメント