
目次
COREZOコレゾ 「『濱納豆』LOVE! 脇役に回って、それぞれの食材の良さを引き出し、全体をまとめる『濱納豆』に生き方まで教わり その伝統を守って未来の可能性を創造する母娘」 賞
國松 勝子さん(くにまつ まさこ)さん/國松本店 代表取締役/「濱納豆」製造販売元
プロフィール
國松本店 代表取締役
國松 千純(くにまつ ちずみ)さん/國松本店 広報・営業/「濱納豆」製造販売元
プロフィール
國松本店 広報・営業
國松本店
國松本店さんは、愛知県豊橋市で、創業から140年の間ずっと地元の皆様に愛される、郷土の伝統食である「濱納豆」の製造販売元。
濱納豆
1300年前、仏教とともに「濱納豆」のルーツである「豆豉(とうち)」は、調味料として中国から伝わった。「豆豉」の原料は黒豆だが、奈良のお寺では、日本の大豆を使ってアレンジし、保存食として作られるようになった。お寺の台所である「納所(なっしょ)」でつくられたことから、糸引き納豆ではないが「納豆」と呼ばれるようになり、寺から寺へと製法が伝えられたため、「寺納豆」とも呼ばれ、保存食、栄養食として広まった。
戦国時代にはお寺を本陣にした武将たちに好まれ、とくに徳川家康は常食するほど愛したそうで、「國松本店の濱納豆」は、三河・吉田城のほとりにある悟真寺(愛知県豊橋市)から伝わり、旅人や行商人、庶民だけでなく、吉田藩7代藩主・松平信古にも珍重された。
元和年間(1615年~1624年)に、後水尾天皇に國松本店の濱納豆を献上した際、 「ひく汐に わたりかかれば 三河なる 浜名は落ちて ここは八橋」との御製を賜ったことが「八橋納豆」の起源となり、 長らく品名を「八橋納豆」としていたが、諸事情により、現在は、「國松本店の濱納豆」となっている。
「國松本店の濱納豆」は、「大豆を粒のまま味噌にして半生乾きにした」発酵調味料であり、保存食であり、栄養食でもある。地産地消にこだわり、手間暇かけて、すべては自然の力に任せてつくられている。


濱納豆の製造工程
大豆は、「愛知県産フクユタカ」を使用し、①一昼夜、水に浸漬した大豆を蒸す、②麹菌を混ぜた香煎(こうせん/大麦を炒って挽いた粉=はったい粉、麦こがし)を蒸した大豆にまぶし、杉箱の『ろじ』に入れ、「麹室」で3~4日間培養する、③塩水に漬け、上に重し蓋をして、半年かけて熟成発酵させることで、独特の旨味が凝縮される、④最後に天日干しを行うことで旨味を増すとともに、まろやかさを引き出す、⑤煮込んだ生姜を混ぜて完成。
高温多湿の7〜8月は、製造はお休みとなる。
濱納豆の美味しい召し上がり方
そのまま召し上っていただくのが基本で、あったかいご飯やお酒のお供に、そのままでも美味しいが、油を引かずフライパンを熱し、食べる量だけ3~4分表面を焦がした「焼き濱納豆」も香ばしくなって、さらに美味しくなる。
地元豊橋では、お茶漬けに始まり、お茶漬けに終わる、と云われ、ご飯に濱納豆を10粒ほど載せ、濃い煎茶をかけて、少し時間を置くと、独特の旨味が出て“絶品”のお茶漬けになる。
塩キャラメルの感覚で、アイスクリームに濱納豆を少し加えると、ぐんと風味のグレードが上がるそうだ。
調味料としても和・洋・中華・スイーツなどの隠し味に、アレンジは無限大、醤油やお塩を控えめにして、濱納豆を何粒か加えるだけで、風味がグレードアップするので、是非、試して欲しい、とのこと。
実際、生姜も加えられているので、中華との相性もよく、野菜炒めに濱納豆を少量加えてみると、プロの味にかなり近付くので、この濱納豆と世界の森部農園の「にんにくこしょう」があれば、中華の合わせ調味料は不要になる。
濱納豆は、醸造の過程で抗酸化物質が生成され、原料となる麹と比べて6.6倍の抗酸化力が備わっているという研究結果もあり、免疫力もアップする“魔法の調味料”といわれているそうだ。
今後の濱納豆と國松本店
濱納豆は、子供の頃から食卓にあったそうだが、國松社長は、國松本店に嫁ぎ、濱納豆の製造販売に携わったことで、脇役に回って、それぞれの食材の良さや個性を引き出し、全体をまとめる「濱納豆」の素晴らしさに気づき、「濱納豆」に生き方まで教わったので、50年間、社長業を続けてこられた、とおっしゃる。
お母様の背中を見て育ってこられた千純さんと妹さんは、濱納豆の伝統を守って続けるのはもちろんのこと、地域貢献も含めて、濱納豆ができること、濱納豆でできることを考えながら、その未来を創っていきたい、とのこと。
COREZOコレゾ 「『濱納豆』LOVE! 脇役に回って、それぞれの食材の良さを引き出し、全体をまとめる『濱納豆』に生き方まで教わり その伝統を守って未来の可能性を創造する母娘」である。
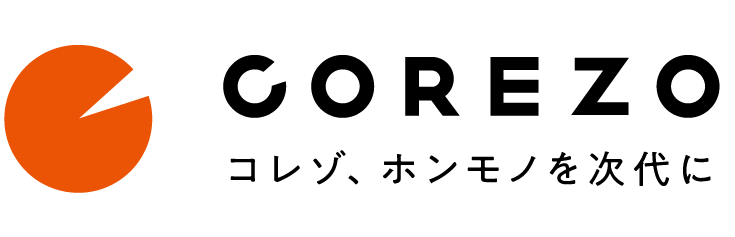
コメント