
目次
COREZOコレゾ 「『小さな木の実』に出会って、『童謡』の魅力に惹き込まれ、世界に誇れる日本特有の音楽文化『童謡』を次の世代に継承する活動に人生を捧げ、自身の生き様を込めて歌い続ける歌手」 賞

大庭 照子(おおば てるこ)さん/ 歌手/NPO法人日本国際童謡館 館長

プロフィール
熊本県出身
熊本県出身
フェリス女学院短期大学音楽科卒業。三宅春惠氏に師事。二期会研究科を経てポピュラー音楽に転向。
昭和42年(1967)日本シャンソンコンクール入賞
昭和45年(1970)よりNHK“みんなのうた”で「詩人が死んだとき」 「小さな木の実」「こわれそうな微笑」を歌い、「小さな木の実」がヒット。
昭和46年(1971)この年より「大庭照子コンサート」を全国の小・中・高・養護学校・聾学校・盲学校で開催し、延べ3,000校以上を回る。
昭和48年(1975)この年より、日本青年会議所主催の「青年の船」に音楽講師として10年間乗船する。
昭和50年(1975)大庭音楽事務所発足。世界各地よりクラシック及びポピュラーアーティストの招聘、国内イベントの企画制作も多数行う。
昭和53年(1978)より、大庭音楽事務所代表として、20年間シャンソンの祭典「パリ祭」を主催・制作。
平成元年(1989)より南阿蘇アスペクタにて、「童謡ピクニック」を開催する。
平成2年(1990)パリのパラディーラタンでシャンソングループ「サンクオム」のコンサートツアーを主催。
平成4年(1992)民間団体としてはじめて「全国童謡・唱歌サミット」を熊本で開催、平成18年度より阿蘇発童謡ワールドを開催。
平成6年(1994)阿蘇郡久木野村に「日本国際童謡館」を設立。館長を務める。また、ハワイに事務所を開設し童謡運動として「ハワイ童謡ツアー」を継続している。
平成6年(1994)ニューヨークのリンカーンセンターで「童謡コンサート」
平成15年(2003)「NPO法人日本国際童謡館かながわ」設立。
平成19年(2007)山都町清和高原の旧朝日小学校に童謡学校を開校。
平成20年(2008)横浜に歌手活動専念のための事務所を開設。
2022 年 NHK ラジオ深夜便「私終いの極意」に出演。
2023 年月刊誌「致知」特集「わが人生の詩」にノーベル生理学・医学賞受賞の大村智博士との対談が掲載される。
現在、NPO法人日本国際童謡館館長としての活動のかたわら、大庭照子が贈る年齢は宝ものコンサート、キングラン童謡コンサート(老人施設)、大庭照子シャンソンをうたう等で全国展開中。
<受賞歴>
昭和62年(1987)第17回日本童謡賞特別賞受賞
昭和63年(1988)第1回下總皖一賞(演奏部門)受賞
平成7年(1995)第35回久留島武彦賞(個人賞)受賞
平成13年(2001)くまもと県民文化賞受賞
COREZOコレゾチャンネル
歌手 大庭 照子(おおば てるこ)さん

突然、大庭 照子(おおば てるこ)さんとおっしゃる方から、お電話をいただいた。以前、たまご農家の大松 秀雄(おおまつひでお)さんから電話でお名前だけは伺っていたのだが、どのような方なのか全く存じ上げなかったので、礼を失してしまった。
大松さんに確認すると、大庭さんの活動に感銘を受け、地元でのコンサートを開催したことがあるそうだ。
NPO法人日本国際童謡館 理事長の高田 真理(たかだ まり)さんから、大庭さんのプロフィールと同館の活動資料を送っていただき、後日、大松さんも交えてお目に掛かることになった。
小さな木の実
大庭 照子(おおば てるこ)さんは、1968年にシャンソン歌手としてデビューしたが、所属事務所の方針とご自身の思う歌手の道とは違っていると感じ、「みんなのうた」(「こどもたちに明るい健康な歌をとどけたい」というコンセプトで、1961年に放送スタートしたNHKテレビ・ラジオの5分間の音楽番組)出演を目指して、NHKの番組ディレクターのもとに何度も足を運んだそうだ。
大庭さんは、「みんなのうた」出演が叶い、1971年、「小さな木の実」という曲に出会って歌唱したところ、放送直後から大きな反響があり、それがきっかけとなって、全国の小中高校、養護・聾・盲学校などを巡る「スクールコンサート」の依頼が次々に入り、延べ3000校以上を訪問された。そして、この歌は、度々、音楽の教科書にも掲載されるようになった。大庭さんは、童謡・唱歌のことをもっとよく知りたいと、その歴史をはじめ、赤い鳥運動など、調べれば調べる程、素晴らしく、ますますその魅力に惹き込まれ、歌手として、童謡を通じた地域文化交流の社会活動を始めることになった。
童謡と唱歌
大庭さんによると、唱歌は学校教育で、童謡は大正7年に創刊された「赤い鳥」がきっかけとなり、もっと子供たちの生活に密着した歌をと、世界に類を見ない、子供たちのための芸術運動から生まれ、子供たちが遊ぶ時に歌う「夕焼け小焼け(ゆうやけこやけ)」は童謡で、学校で教える「旅愁」や「仰げば尊し」は唱歌。外国にも子供の歌はたくさんあるが、芸術家、作家が一丸となって子供たちのためにつくったのは日本の「童謡」だけとのこと。
「夕焼け小焼け(ゆうやけこやけ)」
夕焼け小焼けで 日が暮れて
山のお寺の 鐘が鳴る
お手々つないで みな帰ろ
烏と一緒に 帰りましょ
「旅愁(りょしゅう)」
更け行く秋の夜
旅の空の
わびしき想いに
ひとり悩む
恋しや故郷
なつかし父母
夢路にたどるは
里の家路
もう少し調べてみると、唱歌(しょうか)は明治時代以降、文部省が学校教育の教材として作成した歌曲で、道徳教育や国民意識の醸成を目的とし、現在の「音楽」という科目名がその当時は「唱歌」だった。一方、童謡(どうよう)は、大正期に雑誌「赤い鳥」などを中心に開花した、より芸術性を高め、子どもたちの感性に響くように作られた歌を指すそうだ。
1907年(明治40年)「中等教育唱歌集」に収録された「旅愁」の歌詞は、秋の秋深まる静かな夜空の下、旅先で感じる故郷への強い思い、父母への恋しさ、孤独や挫折、葛藤を静かに歌い上げていて、作詞者の犬童 球渓(いんどう きゅうけい)は、熊本県人吉市出身の詩人・作詞家・教育者で、東京音楽学校(現・東京芸大)卒業後、兵庫・柏原中学校へ赴任しましたが、生徒たちからの西洋音楽排斥運動に遭い、失意のうちに女学校へ転任し、そこで故郷を想い、「旅愁」の詞を書いたとされる。
1923年(大正12年)発表の「夕焼け小焼け(ゆうやけこやけ)」は、夕暮れ時の情景と郷愁を美しく歌い上げた、日本を代表する童謡のひとつで、東京府南多摩郡恩方村(現・東京都八王子市)出身の詩人・教師の中村 雨紅(なかむら うこう)が教え子たちと見た夕焼けの情景を詩にしたとされる。
唱歌
学校教育における音楽教材として、道徳の教科書のような歌詞で国民意識を醸成することを目的に明治時代の初等教育で歌われる歌曲として作成された。日本の自然風景や風習、訓話を背景にした文語体が多く、子供には少々難解な場合があり、1911年(明治44年)に発表された「もみじ」や、1914年(大正3年)に発表された「故郷(ふるさと)」などが代表的な曲とのことで、1957年生まれの筆者もいつどこで覚えたのかは思い出せないが、どちらも1番だけなら誦じて歌える。
「もみじ」
秋の夕日に 照る山紅葉もみじ
濃いも薄いも 数ある中に
松をいろどる 楓や蔦は
山のふもとの 裾模様
「故郷(ふるさと)」
うさぎ追おいし彼かの山やま
小鮒こぶな釣つりし彼かの川かは
夢ゆめは今いまも巡めぐりて
忘わすれ難がたき故郷
童謡
1918年(大正7年)、児童雑誌「赤い鳥」の創刊を契機として童謡が生まれたそうだ。
児童雑誌「赤い鳥」は、夏目漱石門下の鈴木三重吉という児童文学者が創刊し、「芸術味の豊かな、即ち子供等の美しい空想や純な情緒を傷つけないでこれを優しく育むような児童文学」を子供たちに与えたいとして、これを「童謡」と定義づけた。
当初、この雑誌に掲載された童謡には、曲(旋律)は付いていなかったが、西條八十の童謡詩「かなりや」に成田為三作曲による楽譜を付けて掲載され、これが曲のついた童謡として初めて発表された作品で、この曲の発表以降、童謡詩に曲を付けて歌われることが一般化し、真に子供のための歌、子供の心を歌った歌、子供に押し付けるのではなく、子供に自然に口ずさんでもらえる歌を作ろう、という鈴木三重吉の考えは北原白秋(きたはら はくしゅう)、野口雨情(のぐち うじょう)、 西條八十(さいじょう やそ)他、多くの賛同者を集め、童謡普及運動あるいはこれを含んだ児童文学運動は一大潮流となった。
この曲もなんとなく覚えていて、曲調も然り、子供心にも物悲しい印象の曲だったが、歌を忘れた「かなりや」も自分の居場所を見つけることができれば、再び美しい声で歌いだすという、傷つきやすい子供の心を「かなりや」に準え、希望を与えようと作詞されたそうだ。
「かなりや」
歌を忘れたカナリヤは後ろの山に捨てましょうか
いえいえそれはかわいそう
歌を忘れたカナリヤは背戸の小藪に埋けましょうか
いえいえそれはなりませぬ
歌を忘れたカナリヤは柳の鞭でぶちましょうか
いえいえそれはかわいそう
歌を忘れたカナリヤは象牙の船に銀のかい
月夜の海に浮かべれば忘れた歌を思い出す
子供の歌のジャンル
子供の歌は、「唱歌」、「童謡」、「現代子供の歌」、「アニメソング」と時代の流れと共に変遷してきて、「里の秋」、「からすの赤ちゃん」、「お猿のかごや」他を作曲され、「童謡の神様」とも称された、海沼 実(かいぬま みのる)さんが活躍されていた頃までの子供の歌が「童謡」で、昭和30年ぐらいから「現代子供の歌」が始まったので、それ以降は、「現代子供の歌」と捉え、この4つのジャンルに分けると分かりやすい。
「里の秋」
静かな 静かな 里の秋
お背戸(せど)に木の実の 落ちる夜は
ああ 母さんと ただ二人
栗の実 煮てます いろりばた
童謡は、作家の先生方が、ご自身の人生観を基につくっていて、子供たちに媚びていない。例えば、「赤とんぼ」は、三木露風(みき ろふう)が故郷の心象風景、幼い頃の郷愁、ご自身の人生を基に作詞したので、歌って、教え、諭すことができる。
「赤とんぼ」
夕やけ小やけの 赤とんぼ
負われて見たのは いつの日か山の畑の 桑の実を
小籠(こかご)に摘んだは まぼろしか十五で姉やは 嫁に行き
お里のたよりも 絶えはてた夕やけ小やけの 赤とんぼ
とまっているよ 竿の先
日本の自然風景や風習、訓話を背景にしていた唱歌は、戦時中、それ以前の穏やかで情緒的な内容から大きく変化し、軍国主義や愛国心の高揚を目的とした内容となる残念な時期があったが、童謡・唱歌を子供たちの教育の中に入れると、道徳的にも、精神的にも、国際交流の他、いろんなことを学べる素材がある、と大庭さん。
現代子供の歌
「現代子供の歌」は、従来の「童謡」や「唱歌」などへのある意味ではアンチテーゼもあって、和音や響きを大事にしたり、現代の子どもたちの生活や価値観、社会環境に即して、現代的な感性でつくられ、現代を生きる子どもたちに喜ばれるように寄り添った内容・表現・メッセージを持つ歌が多く、作者の創作への想いや意向の違いもあるので、現代子供の歌の作家さんには、童謡と呼ばれたくない方もいらっしゃる、と高田さん。
NPO法人日本国際童謡館
童謡・唱歌不遇の時代
1971年に「みんなのうた」で歌って以来、大庭さんが歌い続けたことにより、「小さな木の実」は生き残り、童謡も広がっていったのに、どうして童謡は歌われなくなったのだろう、という言葉を残して、NHK担当ディレクターは亡くなられた。
一時期、アンチ海沼 実(かいぬま みのる)の風潮が蔓延り、「童謡の神様」とも称されただけに、「童謡」にとっても不遇の時代があって、スクールコンサートで全国の学校を巡っても、「故郷(ふるさと)」は歌われなくなっていたし、自衛隊で歌った時には、3番の「志を果たして」と云う歌詞が書かれていないのにはびっくりしたが、今振り返ると、それもひとつの時代だったのかもしれない、と大庭さん。
「故郷(ふるさと)」3番
志を 果たして
いつの日にか 帰らん
山は青き ふるさと
水は清き ふるさと
童謡が教科書から消えた
大庭さんから、童謡が教科書から消えた時期があると伺い、調べてみると、1977年(昭和52年)の指導要領改訂で、小学校音楽科のどの教科書にも必ず載っていた唱歌・童謡から削除指定される曲が出てきたことに始まり、その他の多くの唱歌・童謡(「われは海の子」「春の小川」「村の鍛冶屋」「雪」など)も徐々に掲載が減って、1986年にはすべての教科書から除外された状態になり、その理由として、「歌詞が難しい」「農村の情景が伝わりにくい」といった教育的配慮や、時代背景との乖離が挙げられたとのこと。
世界に誇れる日本特有の音楽文化「童謡」を次の世代に
日本国際童謡館の設立構想
大正時代に「子どもたちに良い歌を」という理念の下に多くの作詞家や作曲家が作った「童謡」は、日本が世界に誇ることのできる特有の音楽文化であると云われ、その後も引き継がれて多くの歌が生まれ、多くの子どもたちの心を育んで来たが、この素晴らしい文化が時代の変化とともに次第に忘れ去られようとしている危機感から、童謡・唱歌が歌い継がれ、広めていくためには、童謡の理念を理解し、正しく歌える歌い手が必要と、1989(平成元)年10月10日、阿蘇で開催した「アスペクタ童謡ピクニック」の会場で、大庭さんは、阿蘇発の童謡運動の発信地として、日本国際童謡館の設立構想を発表し、長年のスクールコンサート等の活動を通して行ってきた童謡運動の集大成としての活動をスタートされた。
「日本国際童謡館」設立にあたっての3つのビジョン
1 過去:先人が遺された名曲を歌い継いでいく
2 現在:「今生きている歌を、今生きている子どもたちに」をモットーに新曲に取り組む。
3 未来:童謡の理念を理解し、正しく歌える若い人材を育成する。
NPO法人 日本国際童謡館
こうして、阿蘇に「日本国際童謡館」を設立したものの、紆余曲折があった。そして、多くのご苦労を経て、この3つのビジョンを柱とする「阿蘇からの風」の童謡運動を継承し、多くの人々がかかわりを持って参加できる組織をつくりたいとの思いから、2003年、大庭さんが館長、高田さんが理事長を務める、NPO(特定非営利活動法人)日本国際童謡館を日本(神奈川県横浜市)と米国ハワイ州に設立して、日本が世界に誇れる音楽文化「童謡」を次の世代に継承する活動を続けておられる。
唱歌・童謡が教科書に復活、再掲載
一旦、小学校の教科書から姿を消した童謡・唱歌だったが、童謡・唱歌の「良さ」が再認識され、「次世代に歌い継ぐべきだ」と云う動きを背景に、2005年度(2005年4月以降)の小学校音楽の教科書には、「月」「雪」「夕日」(2年生)、「あの町この町」「七つの子」「村祭り」(3年生)、「みどりのそよ風」「月の沙漠」「夏は来ぬ」「背くらべ」(4年生)など、なつかしい唱歌・童謡が約13曲復活、再掲載され、現在、2025年度も教科書に掲載されているようだ。
大庭さんとNPO法人日本国際童謡館が続けてこられた童謡運動が寄与したところも大きいと思う。
おんぷマン

資料としていただいた日本国際童謡館のチラシに入っているイラストのキャラクターが気になって尋ねたところ、阿蘇の日本国際童謡館開館祝いに、2025年上期のNHK朝ドラで盛り上がっている、やなせたかし先生からプレゼントされたと云う。
手のひらを太陽に
大庭さんは、小学校の「スクールコンサート」での最後の曲は、みんな立ち上がって「手のひらを太陽に」(やなせたかし作詞、いずみたく作曲)を一緒に歌っておられたそうだ。
この歌は、1963(昭和38)年につくられ、翌年、NHKの「みんなのうた」で放送されて、ヒットした名曲で、♪ぼくらはみんないきている♪と歌いだし、「みみず」「おけら」「あめんぼ」「とんぼ」「かえる」「みつばち」が皆んな「ともだち」になる。
歌詞がわかりやすく子供たちは喜んで歌うし.子供の声によく合う歌で、単に力強いだけではなく.自然に対する愛情や湧き出るような生命力を感じる、と大庭さん。
作詞した、やなせたかし先生はご存じのように、小さな子供たちに圧倒的な人気を誇る、テレビアニメ香組「それいけ!アンパンマン」の作者で、88年10月の放送開始から現在(2025年)も続いている。
やなせ先生とのご縁
やなせ先生とは、舞台で「えかきうた」を歌うときなどに共演したご縁があったそうだが、そのやなせ先生が、日本国際童謡館のためにと、1994年4月の開館前に「おんぷ(音符)マン」のイラストを描いてくださり、しかも「版権を差し上げあげます」とおっしゃってくださった。
「おんぷマン」は、顔と頭が「八分音符」、指揮者のように「卜音記号」を持っているイラストで、「卜音記号」が指揮棒のようでもあり、指揮棒を「卜音記号」のよう振ったようにも見える。
正義の味方「アンパンマン」のようにやさしい、やなせ先生に感謝して、ご恩を生かそうと、「おんぷマン」を日本国際童謡館のシンボルキャラクターとして、名刺やコンサートのポスター、チラシ、グッズなどに使わせていただいている、と大庭さん。
プレゼントされたのは、もちろん、大庭さんの人徳があってのことだろうが、以前、「佐世保バーガーマン」でも同じような話を聞いたことがあり、やなせ先生は、NHK朝ドラで描かれている通りの人物のようだ。
今後の大庭さんとNPO法人日本国際童謡館
大庭館長と高田理事長の関係
高田さんは、大庭音楽事務所に入社以来、大庭さんの片腕として、大庭さんの活動を支えてこられたが、歌手、大庭照子としてもっと売れて有名になることには興味がなく、歌手の立場から、周りの皆さんをまとめて運動を推進しようとして、大庭照子の歌を聴きにこられているのに、「こんな若い素晴らしい歌い手がいます」と紹介役に廻ったりするので、大庭照子のファンの皆さんにどう対応したらいいのか、スタッフとしてやりづらいこともあったが、大庭照子と出会ったからこそ、NPO(特定非営利活動法人)日本国際童謡館として「童謡」を次の世代に継承するための活動ができている、とおっしゃる。
高田さんには、いつも上から目線で対応されているが、40年以上、苦労をかけてきて、記念碑的なコンサートの時に、高田さんのお母様から、「娘と一点だけ共通しているのは、大庭さんのやっていることは間違っていない、ということだけ」とおっしゃっていただいて、ホッとしたし、日頃の生活を支えてくれている高田さんには言葉に表せないぐらい感謝している、と大庭さん。
童謡レクチャーコンサート
童謡の歴史・背景・歌詞の意味などを「解説(レクチャー)」しながら、歌や演奏を組み合わせて行う音楽イベントである「童謡レクチャーコンサート」を開催していて、「一般社団法人日本童謡学会理事長」の三代目海沼 実(かいぬま みのる)さんに解説を依頼しているが、今後も協力関係を続けていきたい、と大庭さん。
三代目海沼 実(かいぬま みのる)さんは、童謡作曲家・音育の先駆者である初代・海沼実(かいぬま みのる・1909〜1971年)の孫にあたり、祖父が残した「童謡は単なる音楽ではない」という信念を深く受け継ぎ、「童謡が日本人にとっての心の基盤となり、人生を支える力になってほしい」という思いを込めて、日本語の美しさや情感を伝える童謡文化の価値を現代にも輝かせようと普及活動・教育活動を続けておられるとのこと。
童謡の今と大庭さんの今後
童謡・唱歌の素晴らしさ、無限の可能性を信じて、地道に日本が世界に誇れる音楽文化「童謡」を次の世代に継承するための活動を続けてきた結果、阿蘇を始め、神戸、千葉、山梨、横浜、そして東京と童謡を通じた「地域文化交流」の組織ができつつある。
1971年に「小さな木の実」を歌って以来、54年(2025年現在)が経過して、50年前、30年前とはすっかり世の中が変わり、童謡・唱歌で生活が成り立つ方が増えたが、ビジネスはビジネスとして、社会貢献は忘れないで欲しい。
童謡コンサートやイベント他を通じて、子供たちだけでなく、老若男女、皆んなが心豊かに交流ができるのは、童謡・唱歌が根幹にあって、現代子供の歌、楽しいアニメソングにも良い曲がたくさんあり、脈々と子供の歌が続いてきたからこそで、後進を育てた訳ではないが、それぞれのジャンルで、この歌にはこの歌い手という若手が育っていて、ワクワクしている。
自分で選んだ人生だから、何の不満もなく、自分が選んだ苦しみだから、誰かを恨んで、今に見ていろではなく、これで終わってたまるか、「大バカ照子、これで終わってたまるか」と云う気持ちで続けてきたことがようやく実を結んできて手応えを感じている。
地方にも若い歌い手が育っており、おかげさまで、童謡・唱歌は軌道に乗り始めたが、シャンソンにも強い思い入れがあって、こちらも再チャレンジしようとしているところ。運動や活動は一人ではできないので、託せる人がいるから嬉しいし、自分の人生を振り返って整理できるところに来ることができた。
有難いことに、どんな時にも必ず支えてくれる人が現れてくださって、これからは、そんなご恩をいただいた方々(既に先に旅立たれた方も多いが)の想いもしっかり受け止めて、これまでの自分自身の人生を込めて歌いたいですね、と大庭さん。
まとめ
今でもそれとなく覚えている童謡の世界を改めて知る機会になった。
今年(2025年)、87歳を迎えられるという、大庭さん、日本国際童謡館でマネージメントをしておられる、90歳でソロデビューをされたボニージャックスのオリジナルメンバーである玉田 元康(たまだ もとやす)さんともご一緒にステージに立たれているそうだ。
やりたいことが山ほどあり、日々、突き進んでおられるからだろう、とても若々しく、生き生きとしておられ、見習いたいものだ。
AI検索で見つけた大庭さんのコメントから
「誰にでも分かるやさしい歌詞とシンプルなメロディーで感動を伝えるには、テクニックだけではダメ。一フレーズ、いや一言一言を疎かにせず、心を込めなければ歌い切れない童謡が一番難しい。童謡をしっかりと歌えるようになったら、どんなジャンルでも歌えるようになると云うのが持論。」
「私も童謡を歌い始めたばかりの頃は、『子どもの目線で、明るく、かわいく』と勘違いをして歌っていた。しかし、子どもの真似をするのなら、子どもが歌ったほうがいい。人生の山坂を乗り越え、辿り着いたいまの自分の人生を素直に歌に込めるからこそ、相手の心に響く。それは聴衆が大人でも子どもでも同じこと。そういう意味で、童謡は『人生の歌』だと思う。」
そんな大庭さんの手綱をしっかり引き締める高田さんと二人三脚で、これからも世界に誇れる日本特有の音楽文化「童謡」を次の世代に引き継ぐ活動を続け、艱難辛苦を乗り越え、今に辿り着かれた大庭さんの生き様を込めて歌い続けていただきたい。
COREZOコレゾ 「『小さな木の実』に出会って、『童謡』の魅力に惹き込まれ、世界に誇れる日本特有の音楽文化『童謡』を次の世代に継承する活動に人生を捧げ、自身の生き様を込めて歌い続ける歌手」である。
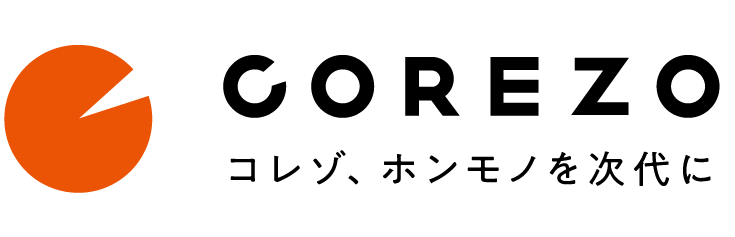
コメント