
目次
塩づくりの原理と技
海塩づくりには気候条件の悪い日本では、さいかんとせんごうを組み合わせてつくられてきた。
伝統的な製塩法でつくった塩がいい塩、おいしい塩というイメージがあるが、流下式が使われたのは、1948〜1971年の間で、それ以前に何百年と使われていた入浜式の塩は、一体、どんな塩だったのだろうか?
昔の塩はおいしかったの?
大昔から(現在も)伊勢神宮には、入浜式の塩田があり、神事用として保存可能な焼塩を作っているそうだ。さて、昔の塩はおいしかったのだろうかという興味が湧く。
http://www.isejingu.or.jp/summary_4.html
江戸時代の塩
純度70~80%程度だったと考えられていて、出荷する前に積み上げて、水分や水に溶けやすいにがり分を落としたり、家庭でもつぼの上に置いたザルに塩をのせ、にがりを切って使い、にがりは豆腐づくりに利用していた。
明治時代の塩
江戸時代の製塩法と大差がなく、塩分80%以上で苦汁分が少ない「真塩」と塩分70~80%未満で苦汁をかけてカサ増しした「差塩」があったそうだ。
昭和初期の塩
入浜塩田でかん水をとり、平釜で結晶にするのが主だったが、真空式多重効用蒸発缶も使われていた。母液注加法というにがりの中で結晶化させる方法でスケール(海水中の湯垢、主成分は石膏)の付着を防止してたので、全体的に石膏と水分が非常に多いのが特徴。特に、平釜の塩は極端にベタベタして水切りが悪く黒っぽい色をしていたと考えられているが、真空式缶には遠心分離機が導入されて、かなり水分は少なくなった。
一時、にがり健康法がブームになったのを知っている方はご存知と思うが、にがりそのものは苦くて不味くて飲めた代物ではないし、健康に良いのか悪いのかもよくわからない。
昔の人がにがり分を含んだ水分を切って使っていたことからも、にがり分の多い塩を好んで使っていたとは考え難く、水分とにがり分を如何に少なくするかに苦心してきたようだ。だから、日本の製塩は、岩塩や湖塩の資源がなく、気候条件が悪い中、如何に海水からにがり分を含む水分を少なく塩を効率的につくるか、に苦心してきた歴史でもあったと云える。
参考
http://www.siojoho.com/s07/03.html
塩職人の熟練の技と勘がものをいう世界
にがりが少ない塩は、さっぱりした塩になるが、高純度になり過ぎると塩辛さが尖ってきて、にがりが多すぎると苦味が強く雑味のある塩になる、と云われている。
釜焚き塩の場合、濃い塩水を平釜に入れて加熱していくと、最初に泡やゴミ、続いて石灰の結晶が液表に浮きでてくる。それを丹念に取り除いていくうちに、やがて液表に「塩の種」が誕生し、液中で次第に大きくなって塩の結晶が生育する。この結晶の具合を見守りながらにがりと塩の結晶が混じった状態の液(母液)を攪拌しながら焚いていき、頃合いを見計らって釜から引き上げ、水分を抜いて塩に仕上げる。
塩はその濃度と温度で、自在に変化する生き物だとも云われていて、おいしい塩に仕上げるのには、いかに程よいにがりを残して塩の結晶を釜から採りだすか、その絶妙なタイミングこそが塩づくりの決め手で、塩職人の熟練の技と勘がものをいう世界だそうだ。
では、どのようににがり分の分量を調整しているのだろうか?
海水中の代表的な成分
海水の組成、水 96.6%、塩分 3.4%、塩分の内訳は、塩化ナトリウム 77.9%、塩化マグネシウム 9.6%、硫酸マグネシウム 6.1%、硫酸カルシウム 4%、塩化カリウム 2.1%、その他
ナトリウム分
塩化ナトリウム77.9%、塩辛味
マグネシウム分
塩化マグネシウム9.6%、硫酸マグネシウム6.1%、強い苦味
カルシウム分
硫酸カルシウム4%、淡いエグ味
カリウム分
塩化カリウム 2.1%、酸味
塩づくりの原理
中学で習った溶解度とイオン化傾向は、覚えておられるだろうか?
水に溶けやすさ
マグネシウム分>カリウム分>ナトリウム分>カルシウム分
海水を蒸発さて濃縮していくと、一番溶け難い成分(カルシウム分)から析出を始め、一番溶けやすい成分(マグネシウム分)が最後に析出する。
塩分濃度約13〜25%
一番固まりやすい(溶けにくい)カルシウム分(淡いエグ味)だけが最初に析出を始め、カルシウム分だけが塩(固体)になり、ナトリウム分をはじめ他の成分はまだ母液の中に溶け込んだままの状態。
塩分濃度約25%
ナトリウム分が析出を始める。
塩分濃度約27~28%
カリウム分・マグネシウム分がナトリウム分と並行して析出を始め、塩(固体)になっていく。
塩づくりの技
塩分濃度約30%
塩分濃度約27~28%を超えて、そのまま海水を濃縮を続けると、ナトリウム分にカリウム分とマグネシウム分がどんどん塩に含まれていく。
強い苦味のマグネシウム分があまり多く含まれてしまうと苦過ぎる塩になるため、30%あたりで塩を引き上げる場合が多いが、ナトリウム分以外の成分をどれぐらい残すか、残さないかは製塩業者の考えで決まり、腕の見せどころでもあるそうだ。
ナトリウム分だけを採る方法
カルシウム分が析出を終えた25%から塩を採り始め、27~28%で濃縮を止めるか(海水を足してその濃度を保つ)、それ以降も濃縮する場合は、ナトリウム分とともに析出するカリウム分・マグネシウム分は、ナトリウム分よりも溶けやすい性質を使って、「塩を洗う」ことで落とす。
塩を洗うとは?
カリウム分・マグネシウム分は最も溶け易く、ナトリウム分はそれらより溶け難いという性質を使って、まずナトリウム分(NaCl)の飽和水溶液(それ以上NaClが溶けない程濃いNaClの塩水)を用意し、それで塩をザブザブ洗うと、ナトリウム分(NaCl)は溶けずにそれより溶け易いカリウム分とマグネシウム分が溶け落ちるという仕組み。
また「洗う」ことである程度の夾雑物(異物)も洗い流せる。天日塩は洗われるのが一般的だとのこと。
天日塩を再度、水に溶かして釜で炊き直すワケ
高温の釜焚き製法では、短い時間に結晶の粒が一気に出来上がるため、結晶の粒は小さくなるが、天日製法では、低温で時間がかかっているため、その分、結晶の粒が育って大きくなるので、天日塩を釜(平釜)の中でいったん溶かし、焚き直して、釜焚き製法のような小さい粒に再結晶させることで、細かくするのだそうだ。
その釜にはほとんど飽和状態の塩水が入っているため、溶けた後すぐに細かな粒ができるので、「一度に大量の粒を細かくする」という点では、粉砕するより断然効率的だが、一度溶かすと、溶けやすいニガリ成分(マグネシウムなど)が落ち(さらに塩化ナトリウムの純度が高くなる)、成分・味も変わるとのこと。
釜焚結晶と天日結晶の違い
物質の溶解度は、温度によっても変化するので、海水を濃縮する温度と時間の違いにより、塩の成分が析出する濃度もスピードも異なり、違った性格の塩になる。また、高温の釜焚き製法では、短い時間に結晶の粒が一気に出来上がるため、結晶の粒は小さくなり、天日では時間が掛かるため、大きな結晶ができる。
シロートにもよくわかる、塩に関する情報満載の素晴らしいサイト
http://www.shio-ya.com/general_salt/index.html
塩は、和食の基本調味料の醤油や味噌の原料にも使われている調味料の基本中の基本なのに、調べ始めると、奥が深過ぎるのと、塩に関しては感覚的、心情的に訴えかける漠然とした情報やこと製塩に関して専門的な知識を要する情報ばかりで、知りたいことになかなかたどり着けなかったが、素晴らしいサイトに出会うことができた。
シロートにもとても分かりやすい平易な文章、かつポイントが明確で、塩づくりの原理や岩塩に他のミネラルが含まれない理由が一気に理解できた。大感謝である。それに、他の批判は一切なく、我田引水の文章もないが、塩づくりに対する思いが伝わってくる。こんな方がつくっている塩なら食べてみたい。
塩に興味がある方は、是非、アクセスして頂きたい。これを読むだけで、塩についてかなりの部分が理解できると思う。
まとめ
昔の人がにがり分を含んだ水分を切って使っていたことからも、にがり分の多い塩を好んで使っていたとは考え難く、水分とにがり分を如何に少なくするかに苦心してきた歴史があるが、いざ、イオン交換膜法が開発されて、純度の高い塩が生産できるようになり、ましてや、それまでの塩田が禁止されてしまうと、従来の塩を食べたくなるのが人の常である。
もちろん、イオン交換膜法以外の製塩法を禁じ、選択肢をなくしたことは許し難いが、そういう製塩にとって専売の暗黒時代があって、水分とにがり分を如何に少なくするかに苦心してきた歴史から、如何に程よくにがりを残しておいしい塩をつくるかの歴史に転じたとも考えられる。
塩は海からの授かりものであるが、塩づくりの原理が理解できると、塩は、海水そのものを濃縮、乾燥したものではなく、海水の主な成分である塩化ナトリウムと塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム、塩化カリウム等の水溶液の濃縮と析出の過程での配合の妙であることがわかる。それこそが、製塩職人さんや製塩業者さんの腕の見せ所であり、その塩の値打ちなのであろう。
今では、「土佐の山塩小僧」のように小規模でも自由に製塩ができるようになったのは、消費者にはとても喜ばしいことである。選り取り見取りで、選択肢が増え過ぎて困るぐらいなのだから…。
関連記事
https://corezoprize.com/salt-halobacteria
https://corezoprize.com/salt-human
https://corezoprize.com/solt-mineral
COREZO (コレゾ)賞 事務局
初稿;2015.04.26.
編集更新;2015.04.26.
文責;平野龍平
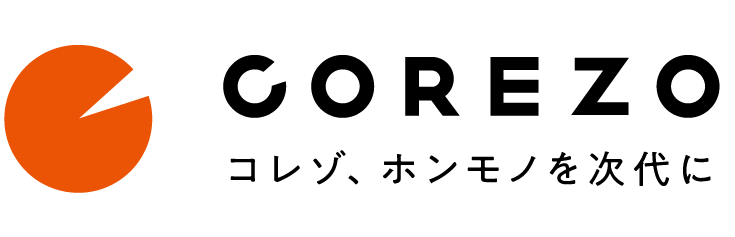
コメント