
目次
COREZOコレゾ 「収穫したての和歌山県産南高梅を仕込む梅酒に徹底してこだわり、梅関連事業を自社の大きな柱に育て、地元名産品と梅酒の魅力を日本全国、世界に伝え続ける、総合酒類・食品メーカー 三代目 社長」 賞

中野 幸治(なかの こうじ)さん/中野BC株式会社 代表取締役社長

プロフィール
和歌山県海南市
中野BC株式会社 代表取締役社長
2005年に家業を継ぐために和歌山に戻り、梅酒を中心とした様々な商品開発や杜氏も経験して日本酒の造りに携わる。
2015年10月、社長に就任。
中野BC株式会社の“BC”は、「Biochemical Creation=生化学の創造」からで、清酒「長久」で培ってきた発酵技術と研究開発をベースに、全国一の生産高を誇る和歌山の農産物「梅・ミカン・山椒・柿」など、和歌山ならではの素材を生かした新しいものづくりに取り組み、バイオ研究開発のCreation(創造)に重点を置きながら、柔軟な経営方針と組織力で 「総合酒類(食品)メーカーのパイオニア」として新しい製品を研究開発し続けている。
COREZOコレゾチャンネル
中野BC株式会社
中野 幸治(なかの こうじ)さんは、和歌山県海南市の中野BC株式会社の三代目社長。季楽里龍神の小川さださんから、地元の和歌山店産南高梅にこだわった梅酒で有名な会社の社長さんがいらっしゃるとご紹介いただいた。
創業者である中野社長のお祖父様は、酒づくりに憧れていたが、いきなり酒蔵をするのは難しいため、和歌山は醤油発祥の地であることから醤油製造を始めて資金を貯め、念願の酒蔵を起業して、焼酎から日本酒、みりん、梅酒、リキュール、…、いろんなカテゴリーのお酒へと拡大していかれた。
中野社長は、大学では機械工学専攻でアルミニウム等を研究をされたとのことで、家業を継ぐには畑が違うようにも思うが、「酒蔵の跡取りといえども、お酒だけではなく、いろんな経験をして、より広い視点からビジネスモデルの拡大や多角経営も目指せる経営者になってほしい」と云うお父様のお考えもあったそうだ。
卒業後、家業のお酒のことは何も知らなかったので、大手酒造メーカーに勤務して、2年間、日本酒の工場でお酒のつくり方を学び、2年間、東京で営業職に従事した。その後、10ヶ月間、中小企業大学校で経営と帝王学を勉強された。
梅酒と梅関連事業を大きな柱にする挑戦

2005年、中野BCに入社後、梅酒を中心とした梅関連商品に軸足を移すチャレンジを開始し、今では、梅酒を中心とする梅関連商品は社業の約7割を占める大きな柱に成長した。
その挑戦には、中小企業大学校では自社分析する授業があり、財務分析や学んだマーケティング手法を自社でどう活用するか等を他の受講生や講師の前で発表する機会が毎月あったので、自社の数字上の実情はある程度把握できていたことと、2002〜4年当時、東京での営業活動の中でお酒のマーケットを観ていると、お酒が飲めない方にリキュールが売れていて、世の中は健康志向が高まりつつあり、「地元の和歌山なら梅酒だろう、この先、梅酒の時代が来るのではないか」という目算があった。
成長の舞台裏
中野社長が戻られる前には、梅酒は5〜10アイテムもないぐらいのラインナップだった。その中には、今でも販売を続けている、梅酒を使ったカクテルの「赤い梅酒(現在の赤紫蘇梅酒)」や「緑茶梅酒」、「蜂蜜梅酒」があったが、もっと和テイストの梅酒カクテルがつくれないか、という想いから、和歌山は柑橘をはじめ果物の産地でもあるので、みかん他、あらゆる和歌山県産の柑橘類、果物を使い、研究開発、試作を繰り返して、5年間で約20アイテムの商品開発をし、売れる商品を選別していった。
お酒は嗜好品なので、お客様の幅広い嗜好とニーズに応えるべくアイテム数を増やしてきたが、種類が豊富だといろいろ選ぶ楽しさも生まれて、需要拡大にもつながった。
リキュールとは、蒸留酒(スピリッツ)に果実、ハーブ、スパイス、ナッツなどの風味を移し、砂糖やシロップなどで甘味を加えて作られたお酒のことで、日本の酒税法では、酒類と糖類その他の物品を原料とし、エキス分が2%以上のものをリキュールと定義されている。
2024年、梅酒関連商品の全面リニューアル
昨年(2024年)9月、約2年をかけた、商品の全面リニューアルが完了した。今回のリニューアルは、4〜5アイテム減らして商品を集約し、デザインテイストを統一することが目的で、中野社長は、若手社員育成も兼ねて、リニューアルと商品開発を若手社員と研究所の女性スタッフたちに任せ、梅酒購買層であり、梅酒を好む年代の感覚を信じて、実際、一切口を出さず、最終判断のみをされた。
昭和60(1985)年代から商品ラインナップにあり、かつて梅酒の売上を牽引していた「赤紫蘇梅酒」や「緑茶梅酒」、「蜂蜜梅酒」のラベルは、既に時代を感じさせるデザインとなっていたり、中野社長が関わって開発された商品は、その都度、ラインナップに加わえられていったので、デザインテイストに統一感がない面があったので、商品ラインナップ全体を統一感のあるものに一新した。

梅酒カクテルは、甘いけれど酸味もあってどっしりとした味わいが特徴である中野BCさんの梅酒の原酒と果汁他をブレンドして商品をつくるのだが、時代の流れによって、味の好みも変わってきているので、糖と酸のバランスを少し調整して、今の若い人たちの味覚にあったライトなテイストに変更した。

リニューアル後、昔からある商品もラベルやパッケージがガラリと変わったので、お客様が戸惑われたこともあってか、一時的に売上が落ちたが、着々と戻ってきているので、全面リニューアルの効果を高め、さらに伸ばしていくアプローチをしているところだ、と中野社長。
中野BCの梅酒づくりへのこだわり
和歌山県は、梅の生産量ランキング1位で、全国の約67%(2022年)を占めており、和歌山の企業である中野BCさんでは、みなべ産を中心に100%和歌山県産梅を使って梅製品を製造し、梅事業を通じて、和歌山産南高梅の可能性を追求し、用途と需要の拡大に取り組んでこられ、梅果汁や濃縮果汁、梅エキス他の梅関連商品にも力を入れておられる。
冷凍梅を使えば、年中仕込みができて、果肉の繊維が壊れやすくなるのでエキスの抽出が早くなるが、どうしても香りが弱くなる。産地にあることで鮮度の良い梅を大量に調達することができる強みを活かし、一切、冷凍品を使用せず、収穫したてのフレッシュな梅のみを使用するため、梅の収穫時期である、6月から7月の1週目が勝負で、熟成度合い、状態を見極めながら全社総出で仕込むことで、芳潤な香りをお酒の中に封じ込め、しっかりとした濃厚な梅酒ができる、と中野社長。
こうして仕込まれた梅酒が原酒として梅酒カクテル他、梅酒関連商品のベースとなる。梅酒の原酒は、梅の収穫時期、タンクに漬け込むタイミングによって、青梅で漬けたタンクの梅酒と完熟に近い梅をつけたタンクの梅酒では、味も香りも全く異なるので、1年中、均一な原酒となるよう、何十本も仕込んだタンクの梅酒をブレンドしておられる。
梅酒の楽しみ方の提案
中野BCさんでは、南高梅と梅酒の可能性を追求して、商品開発をし、さまざまな梅酒の楽しみ方を提案しておられる。
The 梅酒
中野BCさんでは、新鮮な南高梅を使って、しっかりとした濃厚な梅酒をつくる技術があるからこそ、The 梅酒と呼べるような本格梅酒を5種類以上商品展開しておられるが、これは同業他社さんにはないことで、「南高梅」の実の中でも、樹上で日光を十分に浴びて南高梅特有の表面に紅をさした「紅南高」と呼ばれる梅だけでつくる「香る南高 紅南高」、月向農園さんの梅だけでつくる「月向」他、全て味が違い、梅酒そのものを味わいたい梅酒ファンの皆さんに好評で、限定生産のものは発売後すぐに完売してしまうそうだ。
香る南高 紅南高

梅酒の熟成
中野BCさんでは、梅の収穫時期の6〜7月始めに仕込み、11月には一旦梅の実をタンクから取り出して、半年〜1年熟成させて梅酒ができる。1年より、5年、10年と熟成させるとより色が濃くなって、甘さと酸味がまろやかになり、濃厚で芳醇な風味に少しスモーキーさと渋みがあらわれ、年代物のウィスキーのような味わいに梅の旨味が加わったような、いかにも高級という梅酒に変化していくそうで、商品としては、南高梅を15年以上熟成させた「香る南高 VINTAGE」がある。
実際、「月向」の1年ものと10年ものを見せていただいたが、素人目にもはっきり色目の違いが分かる。「香る南高 紅南高」と「香る南高 VINTAGE」の商品写真の色合いを見比べていただけばお分かりいただけると思う。ワインのようにワインセラーで寝かす必要がなく、常温保存で熟成が進むそうなので、購入して熟成を楽しめるのも梅酒の魅力かもしれない。
香る南高 VINTAGE

熟成しないフレッシュな「香る南高 NOUVEAU」
通常の梅酒は、6月に仕込み、半年後、梅の実を取り出した後に熟成を重ねるが、この「香る南高 NOUVEAU」は、取り出してすぐに瓶詰めした新酒。熟成していないので、若々しくフレッシュで、透明感のある風味が特徴。15年以上熟成させた「香る南高 VINTAGE」とは対極の商品だ。

糖度「0」、甘くない梅スピリッツ
貴梅酎
梅酒原酒(アルコール度数20度)を単式蒸留(減圧蒸留)にかけ、梅酒とは異なる梅の凝縮された濃厚な香りと味わいが楽しめる本格焼酎タイプのスピリッツ(アルコール度数25度)。業界初の商品で、製法特許取得済みとのこと。

香雪-KAYUKI-
梅酒原酒(アルコール度数20度)を「蒸留」という工程を加えて、凝縮した梅の華やかな香りと、アルコール分だけを取り出したスピリッツ(アルコール度数45度)。

スピリッツとは、蒸留酒全般を指す名称で、ウイスキーやブランデーなども広い意味では含まれるが、一般的にはそれ以外の蒸留酒を指し、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラは「世界の四大スピリッツ」と呼ばれる。
食中酒としての梅酒
食中酒としては、本格梅酒も含めて梅酒関連商品ラインナップのアルコール度数は12〜20度ぐらいあり、炭酸水で割るとフレーバーを残したまま、度数が6%前後になって、飲みやすくなるので、梅酒を炭酸水で割った「ぷらりハイ(プラム・リキュール・ハイボール)」をおすすめしておられる。
梅酒を世界に
元々、梅酒は中国から伝わったが、中国では砂糖を使わないので、エキス分の少ない梅酒が多いのは、おそらく、かつて砂糖は高級品だったからだろう。日本では、砂糖を適量加えて仕込むことで、梅からのエキスを抽出しやすくなる砂糖の浸透圧の作用により、エキス分の濃厚な梅酒となった。
構成比はまだまだ少ないが、紀州産梅酒のおいしさと文化を海外の方々にも知っておもらおうと輸出にも力を入れていて、始めてから10年以上になり、先ず、梅酒をなんとなく知っているだろう、アジアから営業開拓を開始した。中国、韓国、台湾では、梅が栽培されていて梅酒もあるが、現地の梅酒よりクオリティが高いという評価をいただき、その後、米国、欧州、豪州他へと展開している。現在、輸出高ではアジアが最も多く、30カ国に輸出している。
リキュールは世界中にあり、どこの国でも、梅酒はフレーバーの違うリキュールとして捉えてくれるので、日本のリキュールと紹介すると飲んでいただきやすい。また、お酒の中では、リキュールは飲みやすいという認識が万国共通なので、需要拡大できる可能性は大いにあり、実際、タイには、梅酒だけを扱うバーがあって、今後、そのような店舗も増えるだろうから、現地での適正価格で高品質な梅酒を提供できれば、輸出はまだまだ伸びると考えていて、海外に向けてその国でしか販売していない梅酒の開発他、次の展開を検討中とのこと。
原料梅の確保
昨年(2024年)は梅の凶作年で、例年の半分程度の収穫高しかなく、原料梅の確保にも苦労したが、安定した品質を保持し、供給するのがメーカーの使命なので、企業努力を続けている。
中野社長が戻ってこられた20年前でも、梅生産農家さんの高齢化等で放棄梅林が増え、耕作面積が減少しつつあったので、梅酒メーカーの生命線でもある原料の梅を安定して確保するため、梅農家さんを継続していただけるように適正価格で購入し続けてきたが、さらに状況が悪化していることは認識しており、今後は、梅農家さんを如何にサポートするか、農業法人を設立して生産にも踏み切るか、いろんな方策を検討中とのこと。
梅酒を漬け込む文化をつなぐ
中野社長が戻ってこられた20年前は、梅の一大産地である和歌山の人々にとって、梅酒は自宅でつくるものであって、わざわざ買うものではなかったが、年々、和歌山での消費量も増えている。
その要因として、白浜をはじめ、和歌山の観光地では、何種類かの梅酒をメニューに載せて提供してくださる宿泊施設やレストランが増えて、「和歌山と云えば梅」というイメージが浸透し、多くの他府県からの観光客の皆さんがお土産用、自宅用として購入してくださるようになったこと。そして、コロナ禍前まで開催していた「日本酒BAR」、「梅酒BAR」という酒蔵開放のイベントへの参加者の9割が地元和歌山の方々だったが、梅酒を楽しまれる方が多くいらっしゃる一方で、自宅で梅酒を仕込まない若い世代の人たちが増えているのではないか、と考えられる。
梅酒のメーカーとして、梅酒を製造、販売するだけでなく、梅酒を漬け込む文化を絶やしたくないし、漬け込む人口を増やしたい、という想いもあって、酒蔵見学のオプションで「梅酒漬け込み体験」を実施されている。また、中野社長ご自身も毎年、お子さんが20歳になられた時には、漬け込み年の異なる20種類の梅酒が飲めるように、と漬け込んでおられるそうで、こうして梅酒を漬け込む文化が伝わって、次の世代に引き継がれていくのだろう。
今後の中野BC
和歌山の企業だからこそ、徹底して和歌山産の素材を使うことにこだわり、生産高日本一の和歌山県産梅、それも南高梅を中心に、その用途と需要の拡大を図るため、研究開発を重ね、商品展開をして、地元の名産品や梅酒の食文化、和歌山ブランドの魅力を県外に、そして海外へと伝え続けてきた。
今後も、食前酒にも食中酒にも向くスパークリングの梅酒、熟成を楽しんでいただけるような梅酒、新たなフレーバーをブレンドした梅酒他、色んなニーズに応えられる商品開発を続けていくのはもちろんだが、梅の生産量が安定しなくなりつつある中、今後、梅だけにこだるリスクも想定しておく必要がある。和歌山には他にも名産品があるので、さらにそういった新たな素材にも目を向けて、原料として研究開発を続け、より付加価値の高い商品を開発、提供し続けていきたい、と中野社長。
COREZOコレゾ 「収穫したての和歌山県産南高梅を仕込む梅酒に徹底してこだわり、梅関連事業を自社の大きな柱に育て、地元名産品と梅酒の魅力を日本全国、世界に伝え続ける、総合酒類・食品メーカー 三代目 社長」である。
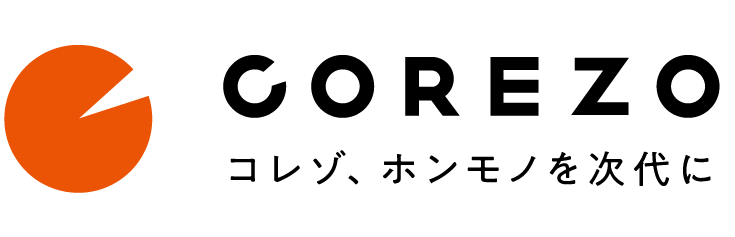
コメント