
目次
COREZOコレゾ 「泉州松波キャベツ生産農家との出会いと交流から、飲食店は生産者がいないと成り立たないことに気づき、全国の生産者と繋がって応援することで、食と生産者の大切さを自店でも伝えるお好み焼き店主」 賞

田中 晶行(たなか まさゆき)さん/株式会社お好み焼きでん 代表取締役

プロフィール
大阪市西成区鶴見橋
株式会社お好み焼きでん 代表取締役
経営理念は「おいしさと健康を笑顔に」
COREZOコレゾチャンネル
お好み焼きでん
自称「ええひと」のトラベルニュース社奥坊社長と季楽里龍神の小川さださんのご紹介で、大阪市西成区鶴見橋にある「お好み焼きでん」さんにご一緒した。伺う道中、約50年振りに鶴見橋商店街を通り、近所に高校時代の友人の家があったことを懐かしく思い出した。
「お好み焼きでん」の代表である田中 晶行(たなか まさゆき)さんは、高校生の頃より、将来は飲食店を経営すると決めておられ、進学するよりも、早く経験を積んだ方が良いというお考えから、叔母さんの自宅兼店舗の近くに串カツの繁盛店があり、よく通っていたのだが、そのお店に惚れ込んで「この店で働かせてください」と、求人も出ていないのに店主に直談判して採用してもらった。
お好み焼きでん開業
将来、何の飲食店をするかを考えた時、商売する上で食材のロスだけは避けたかったのだが、串カツは事前に仕込むのでどうしても仕込みのロスが出る。子供の頃、母親が営んでいたお好み焼き店は、店が忙しい時には、「これ食べとき」と、いつもお好み焼きや焼きそばばかり食べていたので、子供心にあまり良い印象を持っていなかったのだが、注文を受けてから調理し、キャベツ他の食材も多少日持ちもするので、食材ロスがないだろうお好み焼き店に行き着いた。

そのお店で約3年半働いた後、鉄板焼き店を経て、お好み焼き店を3店舗、店長として経験し、開業資金を貯め、叔母さんから経営していた店舗をやめるタイミングで、あとをやらないかと声を掛けてもらい、自己資金で足りない分は融資を受け、喫茶店だった店舗を改装して、現在の鶴見橋で「お好み焼き でん」をオープンした。

「泉州松波キャベツ」生産農家さんとの出会い
お客様の笑顔が見たいと、がむしゃらに働いた。そして開店から1年半後、ラジオ番組に出演する機会があり、お好み焼きなら「松波キャベツ」と紹介された。その松波キャベツを気に入った某局のアナウンサーの呼びかけで、松波キャベツのおいしさを広めようと発足した「松波の会」の第1回目に参加したところ、松波キャベツ生産農家さんである「長左エ門 射手矢農園(以下、射手矢農園)」の射手矢さんとの運命的な出会いがあった。

長左エ門 射手矢農園
「射手矢農園」に訪れ、畑で採れたてのキャベツを食べさせてもらった途端、フルーツのようにめちゃくちゃ甘くてジューシー、そのおいしさに衝撃を受けたそうだ。この「泉州松波キャベツ」の旬は、12月から3月、大阪府泉州地域で栽培され、寒くなると甘みが増し、葉が柔らかく、芯まで甘いのが特徴で、「射手矢農園」さんでは、土作りからこだわり、農薬の使用を極力抑えて、自然に優しい農法で育てられているとのこと。
そのキャベツはもちろん、キャベツをつくっている射手矢さんと云う人に惚れ込み、ランチ営業をやめて「射手矢農園」に手伝いに行くようになった。キャベツ農家さんはキャベツのことを一番よくご存知で、保存の仕方、賄いで食べておられる料理の仕方他、生産農家さんから教えていただいたことをお店で伝えていると、お客様からキャベツがおいしいと云われるようになり、夜だけの営業になっても売上が上がった。
射手矢さんは、田中さんのことを気に入ってめちゃくちゃ応援してくださったそうで、確かに「射手矢農園」さんのWebサイトでは田中さんと2ショットの画像が大きく取り上げられている。有名な農家さんなので、よくメディア取材が入り、「このキャベツを調理した料理を食べられるのはどこのお店?」と云う質問には、お取引先が何十店舗もある中、いつも自分の店を紹介してくださったおかげで、自分のお店にも取材が来るようになり、お好み焼きのおいしさの秘訣を問われた時には、焼き方とか、鉄板の分厚さとか、混ぜ方とかではなく、決め手は「泉州松波キャベツ」だと云い続けていると、「射手矢農園」にも取材が入るようになって、双方向で多くの取材を受けるようになった、と田中さん。
泉州には、「泉州松波キャベツ」の他に「泉州たまねぎ」があり、大玉で、水分が多く甘みがあって、肉厚で柔らかいの特徴で、水にさらさなくてもとても甘いので、オニオンスライスがおすすめだが、「お好み焼きでん」さんでは、厚切りの「泉州たまねぎ」ステーキにして提供しておられ、旬の5~6月には、「泉州松波キャベツ」同様、待ちわびて来店されるお客様も多いとか。

生産者との繋がり
「射手矢農園」に通っていると、射手矢さんは、農家が憧れる農家とも云われる程、農家さんが集まる農家さんで、泉州には、「泉州松波キャベツ」、「泉州たまねぎ」だけでなく、水なすやトマト他もあり、そういう他の作物の生産農家さんもどんどん紹介してもらうようになった。

田中さんは、必ず、生産農家さんのところに出向いて、農家さんの人柄を知り、仲良くなることを心がけておられ、どういうところにこだわってつくっておられるか等を店舗だけでなく、SNSでも発信して応援し、農家さんからも応援される店づくりをしようと全国の生産者さんとのネットワークを広げてこられた。農家さんとのつながりの中で、収穫体験、田んぼアートの制作、その他イベントを他の飲食店さんとも連携して実施されている。
大阪のお好み焼き店なので、極力、大阪のものを使うことを心掛けているが、このような取り組みを続けていると、全国の生産農家さんと繋がるようになり、野菜はそれぞれ収穫時期が限られていて、旬があるので、今では、1年を通じて、この時期には、この生産農家さんのこの野菜、というメニューを提供できるようになった、と田中さん。

人と人のご縁
オープンした当初は、生産者さんのことより、目先の採算ベースに乗せること、自分のことに必死だったが、射手矢さんとの人のご縁がつながったことがきっかけとなって、農家さんだけでなくいろんな方々との人と人のご縁がつながり出した。
何故かはよく分からないが、テレビ出演にも声が掛かるようになり、タレントさんたちともつながって、そんなタレントさんとのご縁から依頼されたTV番組のロケで和歌山県田辺市龍神村を訪れ、現地での受け入れサポートをした季楽里龍神の小川さださんと知り合い、小川さんも田中さんと一緒にロケに来られたタレントさんから誘われて、「お好み焼き でん」に通うようになったそうだ。
大阪の鉄板粉モン文化(お好み焼・たこ焼)が文化庁「100年フード」に認定
2021年、大阪の鉄板粉モン文化(お好み焼・たこ焼)が文化庁の100年続く食文化「100年フード」の近代の100年フード部門(明治・大正に生み出された食文化)に認定され、「お好み焼き」なのか「お好み焼」なのか、「テコ」なのか「コテ」なのか、業界で話し合って統一するよう要請があったが、結局、決まらなかったそうだ。
同業のお好み焼き屋さんは、お互いライバル意識もあってつながりやまとまりは薄いが、皆さん、キャベツがないとお好み焼きはつくれないので、おいしいキャベツには集まり、生産者さんを応援しようと云うことには協力してくれるとのこと。
生産者から学んだ飲食店ができること
ブランド野菜をメインに使い、農家さんを応援するには、適正価格で仕入れることになり、当然、コストにも影響するが、飲食店側でも適正価格で販売できるように、店舗の空間、接客サービス他も含めて、この野菜を使って、このおいしさで、この価格なら満足できるとお客様に思ってもらえるよう努力していて、今では、店頭に並べている野菜そのものを購入されるお客様も増えている。

どこの飲食店さんもお好み焼き店さんもおいしいものをつくって提供されていると思うが、サービス面を含めて、選ぶのはお客様で、農家さんを応援するストーリーが心に響いたお客様が応援してくださると云う良い流れができつつある。
料理人として仕入れた食材の調理はしてきたが、実際に農地に行って、肥料や土づくりから栽培の工夫や苦労を見聞きし、その食材のことを生産者さんの目線でより深く知るようになると、食材に向かう気持ちが違ってくる。「おいしくなぁれ」と念じて育てたら作物もおいしくなるし、「しんどいな〜」と思いながら育てたらそんな作物になる、と農家さんたちはおっしゃるが、いくら良い食材を使った同じレシピのお好み焼きでも面倒くさいなと思ってつくるのとめっちゃおいしくつくりたいと思ってつくるのとでは全然出来上がりが違う。お好み焼きなら、ネギやキャベツを刻んで仕込む時から、その食材を活かしてどうおいしく料理するかと云う気持ちが味にも現れる、と田中さん。

大阪市西成区鶴見橋は、ミナミや天王寺・阿倍野の繁華街から離れ、大阪に住む人でもちょっと行き難い立地にも関わらず、他府県からも来客があり連日盛況なのは、おいしいのはもちろんのこと、この田中さんの親しみやすいお人柄と経営方針に惹かれるお客様も多いのだろうと拝察する。
生きていくのに必要不可欠なのは?

生きていくには食事が不可欠だが、就農人口が減り続けている中、今年の夏も猛暑が続いていて、実際に生産者さんの農地を訪れると酷暑の中の農作業はエグいほど過酷なので、それでも農業は儲かる、なりたい職業にしていかないと、飲食店の経営どころか一般消費者の食生活も成り立たないので、そのために飲食店は何ができるかを考えて行動することが大事。
農家さんが企業と農産物生産供給契約を結んで一番困るのが、天候不順等で不作だった時、そう云えば九条ネギの生産農家さんが不作で契約量が出荷できずに他の農家さんの畑に盗みに入って捕まったという事件があった。供給してもらう側もそう云う農業の実情をよく知って、臨機応変な対応をしないといけないし、昨今、米不足から米の価格が高騰したことからも分かるように、キャベツがあるのは当たり前ではなく、守っていく努力が必要な時代になっている。
今後の取り組み
来年、2026年には、「お好み焼きでん」は、創業20年を迎えるが、田中さんは飲食店をしたくてこの道に入り、この仕事が楽しくて仕方がなく、一度も辛いとも、イヤだとも思ったこともなかったので、これまで続けてくることができた。この先は、若い世代の人たちにもお好み焼き店に興味を持って、やってみたいと思ってもらえるような職業にしていきたい。飲食店には、食材が不可欠だが、仕入れ価格を値切るのではなくて、農家さんには儲けていただけるように連携して、農家の価値や生産された農作物のブランド価値が上がる取り組みを続けていきたいし、そう云う飲食店をやりたいと云う若い人たちを育てていきたい、と田中さん。
田中さんは、泉州松波キャベツ生産農家の射手矢さんとの出会いと交流から飲食店は生産者がいないと成り立たない職業であること、生産者との繋がりがあれば、直接農家さんから新鮮な野菜などが届いてお客様に提供できることに気づき、自店を通じて、「新鮮でおいしい野菜を食べることで、健康でいられる体づくりができ、そこに笑顔が生まれる」ことをお客様にも伝え、全国の生産者と繋がって応援しておられるが、そんな田中さんの意志に共感するお客様(=一般消費者)と飲食店を増やし続けていただきたい。
COREZOコレゾ 「泉州松波キャベツ生産農家との出会いと交流から、飲食店は生産者がいないと成り立たないことに気づき、全国の生産者と繋がって応援することで、食と生産者の大切さを自店でも伝えるお好み焼き店主」である。
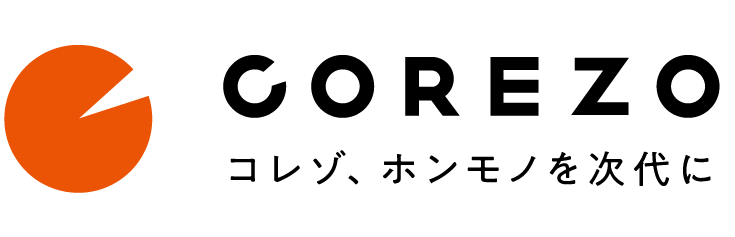
コメント